“頭がいい子”は、生まれつきの才能で決まるものだと思っていませんか?
じつは、“頭の良さ” は習慣でつくられるのです。特別な才能も高額な教材も必要ありません。本記事では、「頭がいい子」にとっては当たり前な “ある習慣” を3つ紹介しています。
どれも普通の家庭ですぐに始められる簡単なものばかり。今日から習慣化をスタートさせれば、お子さんの脳のパフォーマンスはぐんぐん上がるでしょう。
目次
頭がいい子の習慣1:毎日同じ生活リズムで過ごしている
「頭がいい子」のほとんどは、毎日同じ生活リズムで過ごしています。この規則正しい生活こそが、脳の安定したパフォーマンスを支えているのです。
記憶や学習能力に関わる脳の部位は「海馬」です。研究では、十分な睡眠をとっている子どものほうが海馬の体積が大きいことがわかっています。一方で、睡眠時間が短い子どもの脳は、規則正しい生活を送る子どもに比べて発達が遅れやすい傾向があります。
・睡眠時間が短いと、集中力が低下する
・不規則な生活が続くと、記憶力・やる気が低下する
・朝食をとる習慣がない子は、学力が低下しがち
睡眠の質がよい子は、学んだことをしっかり記憶に残せます。また、「ご飯・お風呂・寝る時間がほぼ一定で、朝スッキリ起きることができる子は学習能力が高い」という研究結果もあることから、規則正しい生活を送ることは脳にとっても必要不可欠なのです。
【生活習慣を整える2つのコツ】
・食事の時間を固定する
食事の時間を固定すると、自ずとほかの行動も決まっていきます。まずは、朝食と夕食を毎日同じ時間に固定することから始めましょう
・3日間早起きをさせる
朝ごはんに大好きなおかずを用意するなど “ごほうび” を準備して、まずは3日間早起きにチャレンジしてみましょう。すると、夜も自然と早く眠くなるリズムが生まれます。
子どもに限らず、大人だって「おなかが空いている」「眠い」「身体が疲れている」といった状況では、集中力どころかやる気も出ません。脳が集中力を発揮するためには、「睡眠・食事・運動」が日常にしっかり保証されていることが大切。生活リズムを整えることは、健康面だけでなく学力面でも健やかな向上が期待できるでしょう。

頭がいい子の習慣2:毎日同じ場所で学んでいる
頭のいい子は、毎日決まった場所で学習しています。たとえ短い時間でも、場所を固定することで集中力が高まるのです。
「7回読み勉強法」で知られる山口真由氏は、朝起きたら机に向かって読書をする習慣を徹底しています。「毎朝歯磨きができるなら、毎朝机に向かうこともできるはず」という考えで、起きてすぐ読書できる動線をつくっているそうです。そのため、山口氏にとって生活習慣のなかに読書や勉強が組み込まれていることは、ごく自然なことなのです。
行動と快感を結びつけている脳の線条体は、いわゆる「やる気スイッチ」。脳は「行動」をイメージさせるとやる気スイッチが入る仕組みになっているため、勉強する場所をあらかじめ決めておくのがおすすめです。毎日同じ時間ならルーティン化しやすいため、さらに効率がよいでしょう。
【おすすめの場所&タイミング】
・起きたらすぐにダイニングテーブルで読書
・朝ご飯を食べる前にダイニングテーブルでドリル
・学校から帰ったらすぐに勉強机で宿題
・寝る前にベッドで暗記
記憶には「短期記憶」と「長期記憶」がありますが、勉強における記憶とは「長期記憶」でなければ意味がありません。脳の長期記憶を司る部分に情報を刻むためには、覚えて忘れて覚えて忘れて……を繰り返して反復する必要があるため、毎日少しずつでもいいので “覚える・思い出す” 時間を意識的につくることが大切。頭のいい子は、歯を磨くように自然に「同じ場所で学ぶ習慣」を身につけているのです。
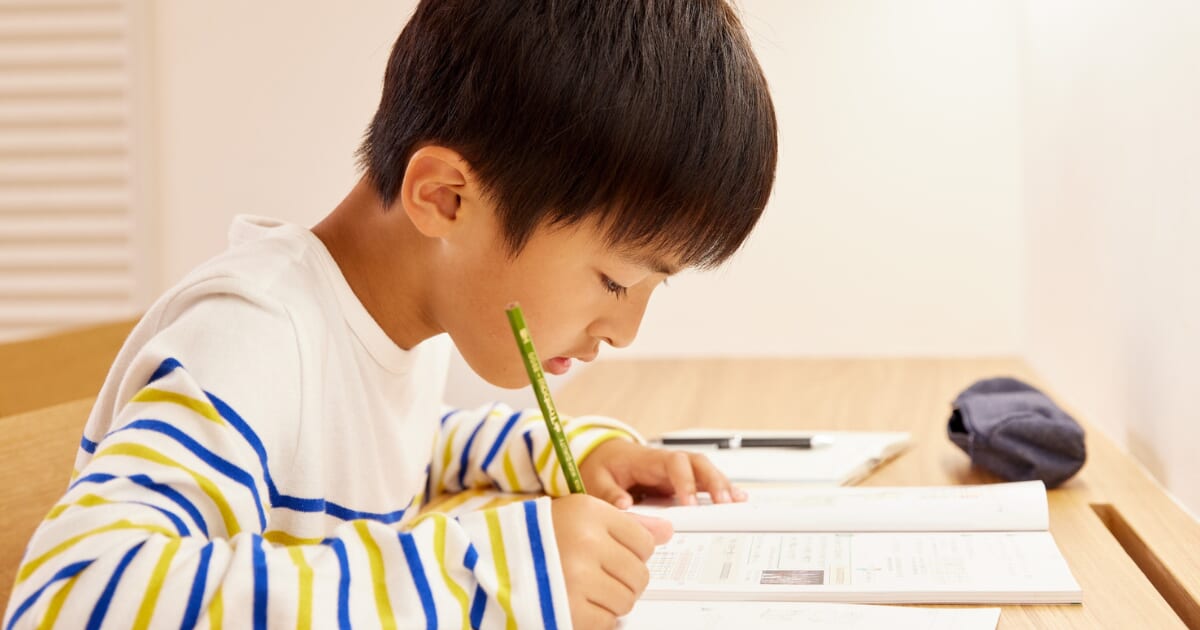
頭がいい子の習慣3:よくお手伝いをしている
お手伝いが習慣化している子は、学力が高くなるだけでなく、将来社会的に成功する確率も高くなることがさまざまな調査からも判明しています。
なぜなら、お手伝いをすると「時間の感覚」が身につくからです。「夕飯の準備は5時から、配膳は6時まで」「準備する時間を考えて、10分前には配膳に取りかかろう」といった経験を重ねることで、時間を意識する習慣が自然と身につきます。
勉強を効率的にこなすためには、自分で1日の時間をコントロールできるようになることが大切です。お手伝いで身についた「時間を意識する習慣」は、「24時間をコントロールする力」につながっていきます。「お手伝い」が「時間の感覚」を身につけさせ、「時間の感覚」が「生活習慣」を身につけさせ、「生活習慣」が「高い学力」をもたらすというわけです。
【おすすめのお手伝い】
・買い物袋に商品を入れる
・洗濯物を畳む
・配膳
・食器を洗う
・テーブルを拭く
また、「お手伝い」は自制心を育むためにとても有効。自制心がある子どものほうが数学力や言語能力が高くなるというデータや、アメリカの大学入試の成績がいいというデータもあります。自制心と学力の関係は、あらためて研究結果を見るまでもなく、多くの人が納得できる関係性ではないでしょうか。勉強をしなければならないときには、「遊びたい」といった気持ちを抑えて勉強することができるのですから、学力が伸びるのも当然です。
***
「頭がいい子」たちは、決して特別な才能が備わっていたり、特殊な環境で勉強したりはしていません。ただ共通しているのは、「生活リズムを整える」「毎日同じ場所で学ぶ」「お手伝いをする」といった毎日の小さな習慣です。これら3つの習慣を、焦らず長い時間をかけて積み重ねていくことで、子どもの考える力や集中力はぐんぐん育っていきます。今日から1つだけでも、家庭で試してみませんか?
(参考)
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|スポーツを習えば体力が向上するとは限らない!? 子どもの体力アップの秘訣・3か条
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|寝るのが遅いと自己肯定感が下がる。デメリットだらけの「子どもの睡眠不足」
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|子どもの脳が集中力を発揮するメカニズム。脳がほっとする時間も必要です
STUDY HACKER|学力向上は生活習慣の確立と時間の使い方で勝負が決まるーー東大主席卒・NY州弁護士 山口真由さんインタビュー【第2回】
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|記憶力の要は「記憶の仕方」にあり。親が知っておくべき「記憶の脳科学」
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|子どもの「やる気」と「集中力」を引き出す脳科学的テクニック
STUDY HACKER|1ヶ月で4,000単語を覚えた男の「最強の暗記術」がすごかった。
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|「お手伝い」が子どもにもたらすいくつものメリットーーお手伝いの習慣が高い学力につながる理由
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|子どもを成長させつ料理体験を! 『夏野菜たっぷりおかずマフィン』【小学生の自由研究(家庭科)】
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|お手伝いで子どもの「自制心」が育つ“脳科学的メカニズム”
















