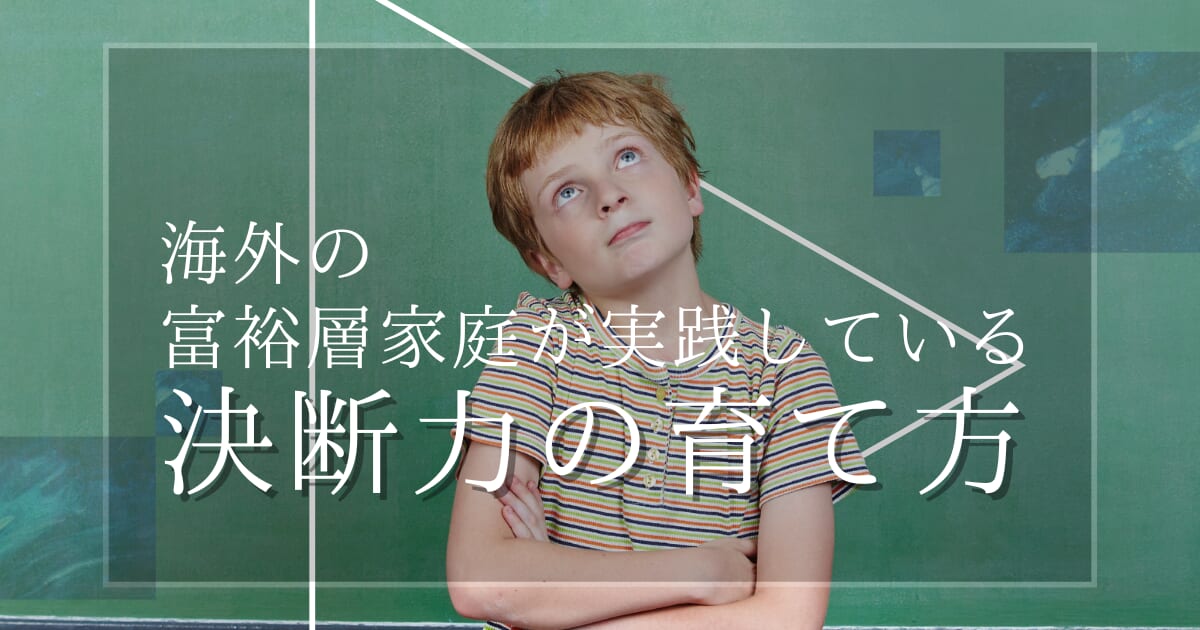「どっちがいい?」と聞いても「わからない」「どうしよう」ばかり。優柔不断で決められない子どもに、つい先回りして決めてしまう——そんな経験はありませんか?
それは愛情ゆえのことですが、長い目で見ると、子どもが自分で判断する機会を奪ってしまっているかも。幼いわが子も、いずれ大人になれば自分で自分の人生を切り開いていかなければなりませんよね。
そのためにも必要なのが、人生の岐路に立ったときに「自分で決める力=決断力」です。海外の富裕層家庭も幼少期から重視し、研究でも効果が実証されています。そこで今回は、優柔不断な子ども、決められない子どもの「決める力」を育むための5つの方法を紹介します。
今日からできる!「決める力」を育む5つの方法
わが子の「決める力」を育てたい! そう願う親御さんに向けて、今日からできることをご紹介します。
方法1:2つの選択肢から選ばせる
日本小児学会会長で医学博士の高橋孝雄氏によると、子どもは2歳ごろから2つの選択肢の中から選べるようになります。
- × 「今日の夜ごはん、なにがいい?」(選択肢が多すぎて困惑)
- ○ 「今日の夜ごはん、ハンバーグとカレーライス、どっちがいい?」
4歳くらいになると、4つの選択肢のなかからひとつを選べるまでに成長するので、子どもの意思決定能力の成長過程を見ながら選択肢を増やしていってもいいですね。
方法2:判断のヒントを添えて聞く
家庭教育の専門家・田宮由美氏は、子どもがなかなか決められないのは「頭のなかで判断材料が整理しきれていない」ことがあるそうです。
そんなときは、親が判断のヒントを具体的に伝えてあげましょう。
- 例:「半袖と長袖、どっちを着る? 今日は少し寒くなるみたいよ」
この一言で、子どもは「寒くなるなら長袖にしよう」と自分で考えて決められます。

方法3:嫌いなものから除外させる
優柔不断でなかなか決められない子もいますよね。田宮さんは、「心が動かないほうや嫌いなほうを尋ねると、すぐに答えられることもある」といいます。
- レストランで苦手なものを除外して選択肢を減らす
- 宿題が複数あるとき「いまはどれをしたくないか」と聞く
こうした工夫が決断を促すことにつながります。
方法4:「なんでもいい」を禁句にする
米国公認会計士の午堂登紀雄氏は、海外の富裕層の家庭では、幼少期から「自分で決める習慣」をつけることを意識していると紹介しています。使う文房具、着る洋服、習い事、食べたいメニュー。すべてを子ども自身に選ばせるのです。
「なんでもいい」や「どっちでもいい」は禁句。大事なのは自分の意思を表明する習慣をもたせることだといいます。
実際、ドイツの大学の研究では、子ども時代に「決められたスケジュールの中で遊んでいた」人よりも「自由に遊んでいた」人のほうが、大人になって社会的に成功している傾向が高いことがわかっています。
方法5:間違った選択も受け止める
子どもの判断が明らかに間違っていたら? まずは「なんで……」という顔をせず受け止めてあげることが大切です。親の考えと違っていても、まずは「なるほど。そういうアイデアもあるね」と頷いてあげましょう。
そのうえで、午堂氏は次のような声かけを提案しています。
- 「こういうことが起こる可能性はない?」
- 「もしこうなったらどうする?」
これは子どもの判断を否定するのではなく、追加情報を提供することです。子どもは経験が少ないため、もっている情報も選択肢も限られています。親ができるのは、子どもの世界観を広げるサポートです。
公認心理師の佐藤めぐみ氏によると、親が過剰に管理する「ヘリコプターペアレント」のもとで育った子は、大人になっても「指示待ち人間」になりがちだそう。小さな失敗や試行錯誤を重ねることで、子どもは自分で考え、決断する力を身につけていくのです。
***
子どもの「決める力」を育てることは、決して難しいことではありません。日常生活の中の小さな選択から始められます。
愛するわが子だからこそ、失敗させたくないと思うのは当然です。でも、小さな失敗や試行錯誤を重ねることで、子どもは自分で考え、決断する力を身につけていきます。
(参考)
STUDY HACKER こどもまなび⭐︎ラボ|親が先回りしたら「自己決定力」は育たない。幼くても決断力を伸ばせる声かけのコツ
PHPファミリー|わが子を「自分で決められない大人」にしないために
KIDSNA|「決められない子」にしないために。これからの時代に必要な判断力とは
プレジデントウーマン|富裕層が子供の教育で重視する4つのこと
Hanakoママweb|自分で決めさせる。子どもの人生を左右する「意思決定力」の育て方【小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て・11】
AllAbout 暮らし|優柔不断な子供の決断力を高める!親の言葉のかけ方