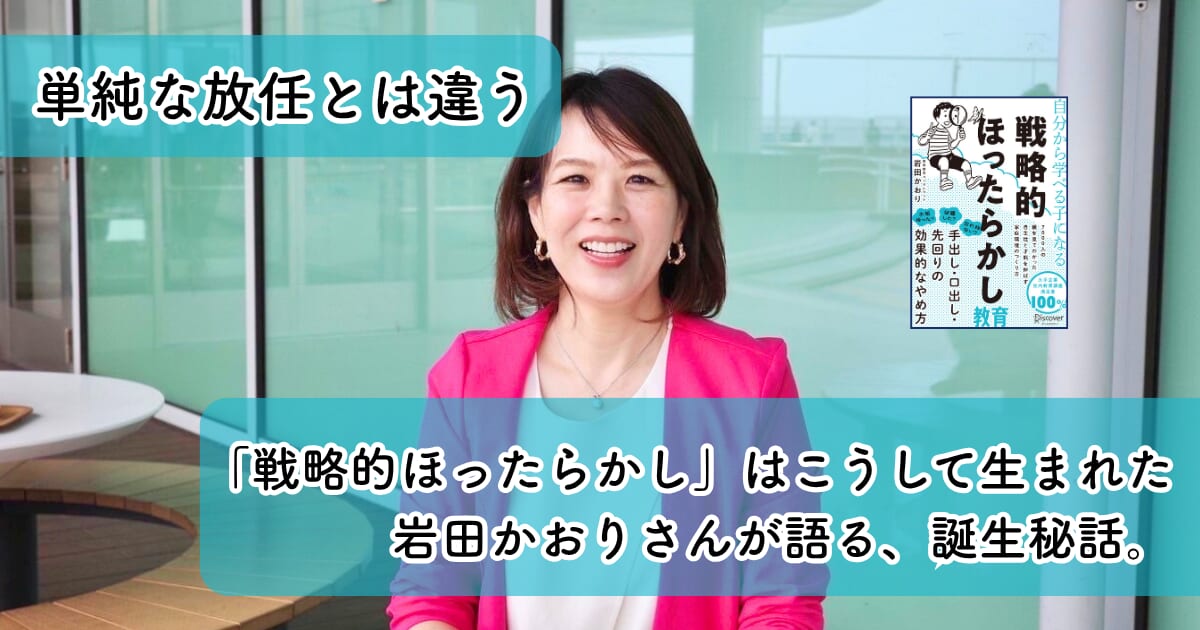「戦略的ほったらかし教育」のネーミングに込められた真意とは?
前回、ご自身の子育て迷走時代について語ってくださった岩田かおりさん。今回は、このユニークなメソッドがどのようにして生まれたのか、その誕生秘話に迫りました。
また、早期教育や中学受験熱が高まる現代において、岩田さんはどのような思いを抱いているのでしょうか。
目次
なぜ「ほったらかし」なのに「戦略的」なのか?
――まず気になるのが「戦略的ほったらかし教育」というネーミングです。この考え方はどのように生まれたのでしょうか?
岩田さん:「戦略的ほったらかし教育」という考え方は、私自身の子育て経験のなかから生まれました。親が一生懸命に声をかけたり管理したりするほど、子どもも親も苦しくなってしまう。けれども「何もしない放任」では成長につながらない。その狭間で悩んだときに気づいたのが、「仕組み」こそが子育てをラクにし、子どもを伸ばす鍵になるということでした。
たとえば「生きているだけで自然と運動量が増える環境」を整えれば、無理に「運動しなさい!」と言わなくても体力がつくのと同じです。子どもの日常のなかにも、自然と頭を使ったり、自分で考えたりする仕掛けをちりばめておけば、親がガミガミ言わなくても学びは回り始めます。
つまり「戦略的ほったらかし教育」とは、親が放っておくのではなく、子どもが自ら動き出す仕組みを戦略的に用意して、あとは信じて任せること。子育て講座を10年運営しているなかで、このネーミングがしっくりくるようになり、書籍のタイトルにしました。
――つまり、単純な放任ではないということですね。
岩田さん: はい、「単純な放任」とは違います! 戦略的ほったらかしは、子どもが自立していくための環境を大人があらかじめ整えたうえで、あとは子どもに任せるという考え方です。
たとえば、本当に何も言わずに放っておいたら、子どもはどうしても目先のおいしさに流されて、白米とお味噌汁よりもグミやジュース選びますよね(笑)。でも大人は「一時的においしいもの」と「長期的に体によいもの」の違いを知っています。
だからこそ、子どもにとって本当に必要なものは用意しておいて、子どもの意向に従い過ぎず「どう選ぶか」を子どもと一緒に考えていくことも重要です。完全ほったらかしにしたら「歯磨きしなくていい」「ご飯食べなくていい」みたいなことになっちゃいますから。
幼児教室で感じた決定的な違和感
――メソッド開発のきっかけとなった体験について詳しくお聞かせください。
岩田さん:子ども2人を幼児教室なしで国立大学付属小学校へ合格後に、教育の才能があるのかもしれないと思い幼児教室で講師として働くようになったんです。そこで繰り広げられていることが「子どもがやりたいと言う前にやらせる」ということに驚きました。
たとえば、リボン結びを教える時に、紐を出して「うさぎちゃんの耳できたかな」とか言って、子どものご機嫌をとりながらやらせるんですけど、私は「何やってるんだろう、こんなに機嫌とって」って思いました(笑)。
私の場合は、子どものご機嫌をとることはせず、楽しそうにリボン結びをしている姿を子どもに見せるんです。すると子どもたちは「やらせて! やらせて!」と言ってくる。でもすぐには渡さないで、「私もまだ上手じゃないからダメ」なんて言って、さらに「やりたい欲」を高めるんです(笑)。
――子どもの「やりたい」気持ちを最大限に引き出してから始めるということですね。
岩田さん: そうです。そうすると、子どもにとって「自分が真剣に取り組みたいこと」になっているので、集中してスッとできるようになるんです。一方、幼児教室では気乗りしない子どもたちの機嫌をとりながら必死に教え込んでいる。
ある子はやりたくないから椅子から離れて行くし、寝そべる子もいるし。お迎えに来たお母さんに「できた」「できなかった」を報告する時間があるのですが、その結果でお母さんの顔が一気に変わるんですよ。でも、そんなに焦らなくても誰もが小学2年生ぐらいになったらできることなんですよね。

早期教育をどう見るか
――早期教育についてはどのように感じていらっしゃいますか?
岩田さん:「早期教育」という言葉自体には少し違和感があります。というのも、日本で言われる早期教育は、「みんなと同じ正解を導き出すこと」や「言われたことに従うこと」が中心になりがちだからです。
たとえば、受験の直前でもないのに「鉛筆は先生の合図があるまで触ってはいけません」など厳しいルールを強いるような幼児教室には、正直疑問を感じます。本当に危険なものなら別ですが、鉛筆くらいなら触ってみたっていいですよね。そういうちょっとした「好奇心の芽」を摘んでしまうのはもったいない。
結局のところ、子どもにとって一番大切なのは「学ぶって楽しい」と思えること。そこさえ育めれば、後からいくらでも知識は身につけられると考えています。私は、子どもが自らの意思で手を使う・足を使う・頭を使うといった「自分の体験を通じて学ぶこと」は大切だと思っていて、そういう取り組みは積極的に応援しています。
――教育情報とのつき合い方についてはいかがでしょうか?
岩田さん: 教育本や教育のスタイルは、一旦聞いて話半分で「じゃあ、うちの子にはどう生かせるんだ」というカスタマイズ能力が必要です。
思考優位になって「この教育本にはこう書いてた」「この教育方法はこうだから」っていうところにとらわれちゃうんじゃなくて、感覚的に見て、明らかに目の前の子どもが嫌がってるとか楽しんでいない方法なら、その方法は、絶対に引っ込めるべきです。
中学受験との向き合い方
――中学受験についてはどのようにお考えでしょうか?
岩田さん:勉強ってすごく楽しいものだから、やることは本当にいいと思うんです。でも、スタートが早すぎて、おもしろさを感じられないまま嫌いになっちゃう人が多いのがもったいない。あと、スポーツに熱中したい時期なのに勉強にシフトさせるとか、そのタイミングを子どもを見て決めるのではなくて、まわりの情報を見て決めちゃうのはもったいないですね。
――時代も変わってきているのでしょうか?
岩田さん: 一昔前は黄金のルートと言われていて、中高一貫校行って、いい大学行って、大手企業に就職したら安泰みたいな時代でしたが、いまはそんな保証がない時代が来てるんです。いまは本当に何ができるのか、どういう情熱を自分がもっているのかが求められる時代です。
あまりに早くに中学受験にカスタマイズしちゃうと、つねに相手の求める正解を合わせるおもしろくない人間になっちゃうっていうのもあるかもしれません。
――率直にお聞きしますが、「戦略的ほったらかし教育」が向かない子どもや家庭もあるのでしょうか?
岩田さん: 正直に言うと、あると思います(笑)。家業を継ぐ、わかりやすく言うと「絶対に医者に育てる」とか、「東大に行かせる」って決めているご家庭には向かないかもしれないですね。
このメソッドは子どもの意思が入っているので、勉強好きになった結果、その職業になるかもしれないし、ならないかもしれないって感じなんです。親が職業や大学を決めている場合は、自分で決めさせるというところからすると、全く反対の部分にありますから。

3人の子どもで違ったアプローチ
――お子さん3人それぞれで、アプローチを変えられたのでしょうか?
岩田さん: うちで言うと、2番目の子はすごくひとつのことに突出してのめり込むタイプなんです。過集中する、没頭するタイプで、ひとつのことを高いレベルでやりたいという感じの子どもでした。
1番目と3番目は、ひとつのことにそこまで集中しないんです。たとえば電車も好きだし、車も好きだし、虫も好きみたいな感じなんですけど、2番目は「電車しか好きじゃない」みたいなタイプでした。そのため、お料理と同じように、この素材がどうやったら活きるのかを日々考えながら接していました。
――それぞれの個性を見ながら調整していくということですね。
岩田さん: そうですね。だからマニュアル通りにはいかないんです。でも、それが子育てのおもしろさでもあります。ひとりひとりに合わせて寄り添える、安心のオーダーメイドなんです。
手抜きでも教養は広がる
――忙しいなかでも実践できる方法はありますか?
岩田さん:できます。忙しい方にも実践していただけると思います。教養を広げるっていうのはいつでもどんな場面でもできて、たとえばミネラルウォーターを見て「ミネラルってどういう意味なんだろうね」って調べたり。
2つの大きさが違うペットボトルを並べて、「これは310ml、こっちは500mlで、このサイズ感で全然違うんだね」とか話すなど、ちょっとした工夫でどんどん教養が広がっていくんです。そうすると、もっと大きいペットボトルを見たときに「これ2リットルって書いてるよ」「そうそう、2リットルは2000ミリのことなんだよね」みたいな話になっていく。
ドリルをやらせるとかだと、つねにつきっきりにならないといけないけど、教養を広げるっていうのは、いつでもどこでもできるんです。
親の「軸」があれば大丈夫
――最後に、教育方針に迷いがある親御さんにメッセージをお願いします。
岩田さん: 情報がたくさんありすぎて迷ってしまう気持ち、すごくよくわかります。SNS情報や周囲の人の意見に振り回されると、迷い疲れてイライラに陥りますよね。「うちの子にはこれが合う」「わが家はこうしていこう」と、自分のなかに明確な基準をもつことが重要です。
一番大切なのは親自身が「軸」をもつことなのですが、自分軸をもつことで判断が早くなり、余計な迷いや不安に時間とエネルギーを奪われなくなります。結果として、子どもに必要なサポートを的確に届けられるようになり子育てができるようになりますよ。

【次回予告】 第3弾では、岩田家の3人のお子さんたちの現在について詳しく伺います。心配だった時期、学校でのトラブル、そして現在の親子関係まで。お子さんたちはいま、この教育をどう振り返っているのか? リアルな本音に迫ります。
★岩田かおり著『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』では、具体的な実践方法や「天才ノート」のやり方など、いますぐ使えるメソッドが詳しく紹介されています。
■ 家庭教育コンサルタント・岩田かおりさん インタビュー一覧
第1回:「私、ダメな親かも。」その不安、『戦略的ほったらかし教育』著者・岩田かおりさんも同じでした
第2回:単純な放任とは違う「戦略的ほったらかし」はこうして生まれた|岩田かおりさんが語る、誕生秘話
第3回:「うちの子、このままで大丈夫?」『戦略的ほったらかし教育』著者・岩田かおりさんが、実体験で語る
【プロフィール】
岩田かおり(いわた・かおり)
家庭教育コンサルタント、株式会社ママプロジェクトJapan代表取締役。幼児教室勤務、そろばん教室の運営を経て、「子どもを勉強好きに育てたい!」という想いから、独自の教育法を開発。「子どもを学び体質に育てる」と「親を幸せ体質にする」ことを目指し、親がガミガミ言わずに勉強好きで知的な子どもを育てる作戦『戦略的ほったらかし教育』を全国へ展開中。また、3児の母親で、『戦略的ほったらかし教育』を実践した子どもたちは、中学生で起業、経団連の奨学生としてインドへ高校留学、学費全額奨学金で海外大学進学、塾なしで慶應義塾大学合格など、3人とも自分で自分の道を切り開いてきた。著書に『「天才ノート」を始めよう!』(ダイヤモンド社)がある。最新刊は『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』(ディスカヴァー)。