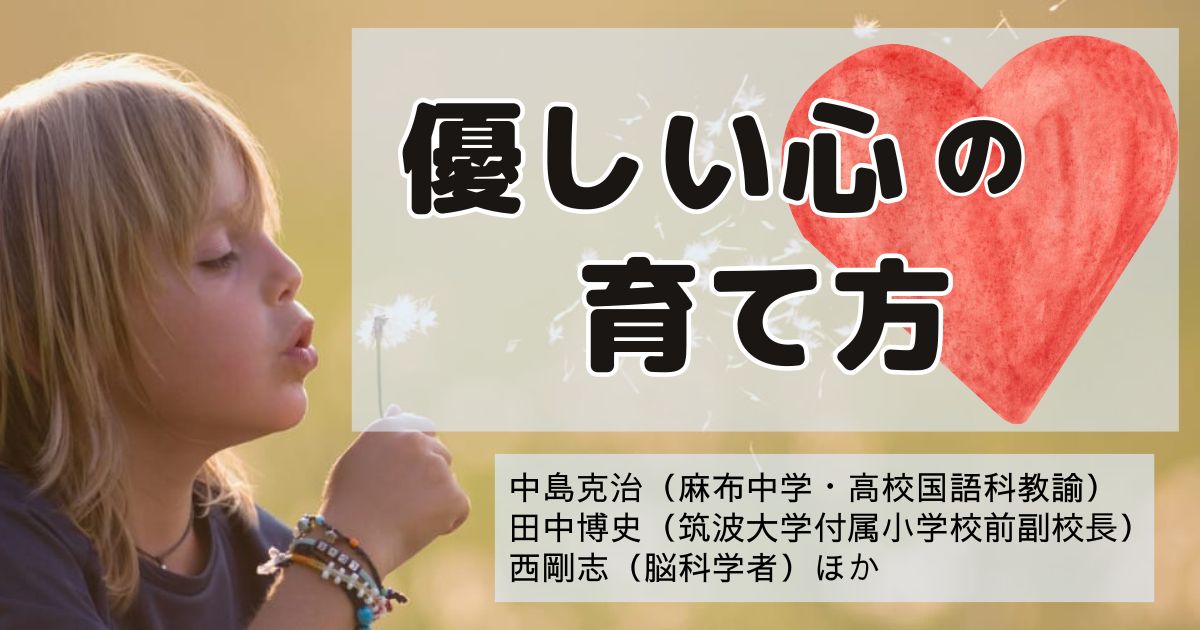「優しい心をもった人間に育ってほしい」「他人を思いやれる人になってほしい」――わが子にそんな願いを抱いている保護者の方は多いはず。しかし現代の子どもたちは、かつて当たり前だった “思いやりを育む機会” を得るのが難しくなっています。
社会の変化にともない、他者との摩擦やぶつかり合いが避けられがちな今、「思いやり」は自然に育つものではなく、“意識的に育てる力”になりつつあります。本記事では、教育や脳科学の専門家たちの意見をもとに、「思いやりの心」が育ちにくくなった現代の背景と、その育み方について探っていきます。
目次
「思いやり」はなぜ育ちにくくなった? 現代の子どもたちが直面する“体験不足”
「思いやり」は、他者への関心や共感を土台にした非認知能力のひとつです。かつての子どもたちは、異年齢の友人や大人たちと関わりながら、自然や遊びのなかで多様な体験を重ねてきました。おもちゃの取り合いで喧嘩をしたり、年上の子に怒られたり、時には泣かされたりするなかで、相手の気持ちを想像したり、自分を抑えて折り合いをつけたりといった社会的スキルが育まれていたのです。
ところが現代では、親や保育者がトラブルを未然に防ごうとする傾向が強まり、子ども同士で衝突や葛藤を乗り越える機会が減っています。さらに、異年齢の子どもや地域の大人と関わる場面も少なくなり、“察する力” を自然に培うことが難しくなっているのです。
スイング幼児教室の矢野文彦氏は、こうした「察する力」は「優しさ」そのものであると話します。そして、その優しさを備えた人のまわりには自然と協力者が集まり、人生を豊かにする可能性が広がります。つまり、思いやりの心は人間関係の土台であり、これからの社会を生き抜く力ともいえるのです。

子どもの共感力を伸ばすカギは「絵本」だった! 親子でできる心のトレーニング【中島克治氏】
絵本には、子どもの心を優しく育む力があります。麻布中学・高校で国語を教える中島克治氏は、「絵本の世界に触れている子どもとそうでない子どもには、思いやりや優しさの点で明確な違いが出る」と指摘します。
絵本の多くは、「こういう子どもになってほしい」「こういう世界が大切だよ」という作者の願いが込められています。現実の喧騒から少し離れた静かな世界で、登場人物の感情や葛藤を追体験することで、子どもは自然と共感力を育んでいくのです。
また、繰り返し読むことで物語が心に深く刻まれ、「もし自分がこの立場だったら……」と想像する力が養われるのも、絵本の大きな魅力。これはまさに、思いやりの源となるでしょう。
さらに、読後に「自分ならどうする?」と問いかけてみると、子どもの視野が広がります。お話のなかの “優しい行動” を、日常に結びつけてあげることも効果的。たとえば、「○○ちゃんが泣いていたとき、△△くんみたいに声をかけてあげられるといいね」というように、絵本の世界を現実とつなげる言葉がけが、実際の行動へとつながっていくでしょう。絵本は、子どもにとって “思いやりを練習する場所” にもなるのです。
【思いやりの心を育む方法】
- ストーリーに共感できる絵本を選び、親子で一緒に読む
- 登場人物の気持ちを一緒に考える対話を取り入れる
- お気に入りの絵本を繰り返し読むことで、感情移入を深める
もっと詳しく!
麻布中高の国語教師が断言。「絵本の読み聞かせ」の教育効果はやっぱり絶大だった!
「困っている人に手を差し伸べられる子」になる! 思いやりがチーム力を高める理由【松尾英明氏】
「思いやり」は、人と協力して生きていくうえで欠かせない力です。千葉大学教育学部附属小学校を経て、現在は千葉県公立小学校の教諭である松尾英明氏は、現代における “他者を思いやる心” の重要性を強調しています。
誰もが得意・不得意を抱えているからこそ、思いやりのある行動がチーム全体の力を引き出します。たとえば、困っている友だちに手を差し伸べたり、自分の得意を活かして人を助けたりすることができる子どもは、集団の中で自然と信頼を集めていくでしょう。逆に、周囲を気にせず自分のことばかり優先する子どもは、チームの一員としての役割を果たすことが難しくなるのは明らかです。
家庭でも、兄弟姉妹や家族との日常的な関わりのなかで「どうすれば相手が気持ちよく過ごせるか」を考える場面をつくることが、思いやりの力を育む第一歩となります。
たとえば、子どもの「得意なこと」と「やりたい気持ち」に注目して、それを活かせる機会を意識的に設けてみましょう。「お皿を運ぶのをお願いできるかな?」「○○くんの字は読みやすいから、みんなに書いてくれるとうれしいな」など、小さな頼みごとでも子どもの自信は積み重ねられます。その結果、他者への思いやりを源とした “役に立てる喜び” を育んでいくのです。
【思いやりの心を育む方法】
- 家族で役割分担や協力の体験を意識的に取り入れる
- 子どもに「誰かの役に立てた」経験を積ませる
- 苦手な人や困っている人への声かけを促す
もっと詳しく!
求められるのは「想像」「創造」「協働」の力。「困っている子」がいてありがたい!?

「優しさ」は脳が育てる! 自制心と思いやりの深いつながりとは?【西剛志氏】
「人が他者に思いやりをもったときと、自制心を働かせたときには、脳内の同じ部位が活性化することが明らかになっている」と述べるのは、脳科学者の西剛志氏です。
たとえば、自分が遊びたいおもちゃを譲ったり、相手の気持ちを考えて行動を控えたりする行為は、いずれも「自分の欲求を抑えて他人を優先する」点で共通しています。つまり、思いやりの根底には自制心があり、それを鍛えることが優しさにつながるのです。
そこで西氏は、自制心を育む手段として「お手伝い」をすすめています。なぜなら、誰かの役に立ったことで親から感謝されたり、ほめられたりする経験が、「人のために動くって気持ちいい」と思えるきっかけになるから。こうした日常の積み重ねが、思いやりのある行動を無理なく習慣化させてくれるのです。
ゲームやスポーツなどの遊びにも、自制心や思いやりを鍛えるチャンスが潜んでいます。たとえば、順番を守る、ルールを守る、負けても相手をたたえるといった行動も、まさに「自分をコントロールする力」。こうした経験を重ねることで、子どもは他人と気持ちよく関わる術を学びます。親は普段から「今の行動、優しかったね」「がまんできたね」と声をかけ、心の成長を言葉にして伝えていきましょう。
【思いやりの心を育む方法】
- 日常のお手伝いを通じて「誰かのために動く」経験を増やす
- 自制心が求められるゲームやスポーツに取り組む機会をつくる
- 思いやりある行動をしたときに、具体的にほめて伝える
もっと詳しく!
お手伝いで子どもの「自制心」が育つ“脳科学的メカニズム”
小さな“気づき”が大きな優しさに変わる! 親ができる思いやりの育て方【田中博史氏】
筑波大学付属小学校前副校長の田中博史氏は、「思いやりは大きな事件で示されるものだけでなく、日常の小さな行動の積み重ねから育つ」と話します。たとえば弟の靴をそっと片付けるなど、周囲への気遣いは「誰かのために行動する」という思いやりの第一歩です。
そこで効果的なのは、こうした行動をした直後にほめるのではなく、少し時間をおいて改めて伝える “貯金ほめ”。日常の些細な気づきを見逃さず、「あなたなら安心して任せられる」と伝えることで、子どもの自信や信頼感を育て、次の思いやり行動を促します。
さらに、親が日々のなかで子どもの優しい行動を認め、言葉で伝えることは、子どもにとって「親が自分を見ている」「認めてくれている」という安心感につながります。この安心感が、思いやりの根幹となる心の安定を支えるのです。
こうした小さな積み重ねがやがては大きな信頼関係となり、子どもが周囲の人と良好な関係を築く基盤となります。親自身も、日常のなかで思いやりの気持ちを意識し、家庭内で実践することが何よりのお手本になるでしょう。
【思いやりの心を育む方法】
- 子どものささいな気づきや優しい行動を逃さず観察する
- 行動の直後でなく少し時間をおいてほめる“貯金ほめ”を試す
- 親自身も日常のなかで思いやりを示し、言葉や態度で伝える
もっと詳しく!
子どもを「褒めて伸ばす」には、ときに親がずる賢くなることも必要!?

思いやりってどう育てるの? 親が知っておきたい5つのQ&A
Q1. 思いやりは何歳ごろから育てるべきですか?
A. 思いやりは特定の年齢から突然育つものではなく、乳幼児期から少しずつ芽生えていく力です。「お友だちにどうぞができた」「泣いている子を見て心配そうにした」など、小さな反応も立派な第一歩。幼いうちから身近な人とのやりとりを通して、人を思いやる土台を育んでいきましょう。
Q2. 兄弟げんかばかりで思いやりが育っていない気がします……
A. 兄弟げんかこそが思いやりを学ぶ大切なチャンス! 兄弟で言い合うなかで「どうすればうまく伝わるか」「相手に譲るとはどういうことか」を体験できます。ポイントは、親がすぐに介入せず、気持ちに共感したうえで解決を見守ること。子ども同士のやりとりを“学びの場”として活かしましょう。
Q3. 「思いやりなさい」と言っても、なかなか伝わりません。どうすればいい?
A. 行動を促す言葉より、「思いやりってどんなことだと思う?」と考えさせる声かけがおすすめです。絵本の登場人物の行動を一緒に振り返ったり、「今、○○ちゃんのこと助けてくれたね」と具体的にほめたりすることで、子ども自身が“思いやりってこういうことか”と実感できるようになります。
Q4. 家では優しいのに、外ではわがままに見えてしまいます……
A. 家庭は子どもにとってもっとも安心できる場所なので、思いやりの行動が育ちやすいのは自然なこと。外でその姿が見られないのは、緊張や照れ、自分を守る意識が働いている可能性も。焦らず、家庭で思いやりの行動を繰り返し経験させることで、徐々に外でも発揮できるようになるでしょう。
Q5. 思いやりと「がまん」は同じですか? 子どもが無理していないか心配です。
A. 思いやりは「他人を大切にする気持ち」、がまんは「自分の気持ちを抑えること」。たしかに似ている部分もありますが、両方のバランスが大切です。子どもが誰かのために頑張ったときは、その気持ちをしっかり認め、「ありがとう」や「えらかったね」と声をかけて、無理が続かないよう見守ってあげましょう。
***
思いやりの心は、人とつながり、協力しながら未来を生きていく力の基盤です。現代の子どもたちにとって、それはもはや「自然に身につくもの」ではなく、環境や親の関わりによって育まれる力へと変化しています。ですが、プレッシャーに感じたり身構えたりする必要はありません。本記事でご紹介したように、絵本や家族とのやりとり、日常の小さな出来事――それらを通じて、子どもたちの優しさの芽を育てていきたいですね。
文/野口燈
(参考)
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|非認知能力は育っているか? 子どもが「目をキラキラさせる世界」があれば安心です
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|【冒険力の育て方】スイング幼児教室が教える、乱世を生き抜くための「4つの力」
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|麻布中高の国語教師が断言。「絵本の読み聞かせ」の教育効果はやっぱり絶大だった!
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|求められるのは「想像」「創造」「協働」の力。「困っている子」がいてありがたい!?
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|お手伝いで子どもの「自制心」が育つ“脳科学的メカニズム“
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|子どもを「褒めて伸ばす」には、ときに親がずる賢くなることも必要!?