世界最高峰の舞台でMVPに輝いた大谷翔平選手。その圧倒的な強さの裏には、幼少期から家庭で築かれた “関わり方” がありました。
ある取材では、父・徹さんが「翔平を本気で叱った記憶はほとんどない」と語っています。厳しい練習や管理型の英才教育ではなく、日常の声かけや家庭文化そのものが、子どもの主体性や挑戦する姿勢を支えたと言うのです。
今回は、大谷家の子育てから「今日から再現できる2つの習慣」を紹介します。
目次
大谷翔平は “押しつけず、任せる家” で育った
父・徹さんが語った「翔平を叱った記憶はほとんどない」という一言は、大谷家の子育ての核心を表しています。父は社会人野球選手、母はバドミントン国体選手という “スポーツエリート一家” でありながら、幼少期の大谷家は想像されるようなスパルタ式の練習とは無縁でした。
毎日の練習量を親が細かく管理したり、できないことを叱責したりすることは一切なかったそうです。それよりも、子どもが何に興味をもち、どんなふうに取り組むのかを尊重し、「やりたいならやりなさい」「やめたいならやめなさい」と、まず「本人に任せる姿勢」が徹底されていました。
家庭環境も独特です。「こうあるべき」「絶対にこうしなさい」といった決めつけやルールを必要以上につくらず、自然体で過ごす時間が多かったと紹介されています。
その結果、大谷家の3きょうだい全員が「反抗期らしい反抗期がなかった」と、母・加代子さんは話しています。親子関係が「対立」ではなく「対話」で保たれていた証といえるでしょう。この土台があったからこそ、あとに紹介する “問いかけのコミュニケーション” や “子どもを否定しない姿勢” がしっかりと機能したのです。

【大谷家の子育て1】頭ごなしに「ダメ!」と怒らない
スポーツライターの吉井妙子氏が大谷翔平選手をはじめとする「超一流選手」の親を取材してわかったのは、「頭ごなしに怒らないこと、そして子どもの考えを否定しないこと」という共通点でした。
父・徹さんも母・加代子さんも「大谷選手を厳しく叱ったことはほとんどなかった」と口をそろえており、大谷選手本人も「ほとんど怒られた記憶がない」と語っています。吉井氏は、その理由をこう説明します。
ネガティブな叱責を受けずに育った子どもは、自分の考えを信じて成長できるのです。

「自己肯定感」を育てる【5つの対応】
教育ジャーナリスト・中曽根陽子氏が「自己肯定感が高い子どもの親は、子どものありのままを受け止め、やりたいことをまず認めてあげる」と語っています。
一方で、「子どもをできない存在としてとらえ、自分が正しいと思っていることを押しつけて、子どものやりたいことを否定してしまう」親の子どもは、自己肯定感が低くなりがちだと指摘しています。
「ありのままを受け止める」とは、具体的にどんな関わり方なのでしょうか。大谷家で大切にされていた5つの対応を見てみましょう。
・子どもがやりたいことを、まず認める
・うまくいかないときは、一緒に考える
・「できない」ではなく「どうすればできるか」を考える
・親自身が、挨拶や片付けを率先してやる
・子どもの小さな頑張りに「ありがとう」を伝える
頭ごなしに否定しない。子どもの考えを認める。その積み重ねが、ありのままの自分を認められる自己肯定感を育て、挑戦し続ける力になったのです。

【大谷家の子育て2】「問いかけ」で本人に考えさせる
もうひとつ、大谷家の子育てで象徴的なのが、 “問いかけ” を通して、子ども自身に考える機会を与える関わり方です。
「次はどうしてみる?」
「いま何が必要だと思う?」
スポーツドクター・辻秀一氏の著書『メンタルドクターが教える 個性を輝かせる子育て、つぶす子育て』(フォレスト出版)のなかでも、「大谷家の両親は子どもの考えを否定しない」姿勢が紹介されています。
「こうしなさい」と大人の答えを押しつけるのではなく、「あなたはどうしたい?」と選択権を渡すことで、子どもは自然と、自分の行動に責任をもつ経験を積むことができるのです。
「自分で判断する力」を育てる【5つの問いかけ】
子どもの判断力について、教育ジャーナリスト・おおたとしまさ氏は、「親が子どもをコントロールして勉強や習い事をさせると、指示されないと動けない、自分で決められない人間になってしまう」と警鐘を鳴らしています。
大切なのは、子どもが自分自身で考え、決める経験を積み重ねること。そのために親ができるのが “問いかけ” です。問いかけは、主体性・自制心・思考力といった非認知能力を育むうえで非常に重要になります。
子どもが自分で考えるきっかけをつくる問いかけの例としては、次のようなものが効果的です。
「どう思った?」
「次に同じことがあったらどうする?」
「いま困っていることは何?」
「それをやっているとき、どんな気持ちだった?」
「自分だったら、どうしたいと思う?」
おおたとしまさ氏の言葉を借りれば、「ぼーっとする時間」を通して子どもは「なにをしているときに自分は幸せなのか」を知り、それが「人生の羅針盤」になります。問いかけは、その羅針盤を見つける手助けをするコミュニケーションなのです。「答えは子どもがもっている」と信じて、考える時間を渡す姿勢こそが大切です。
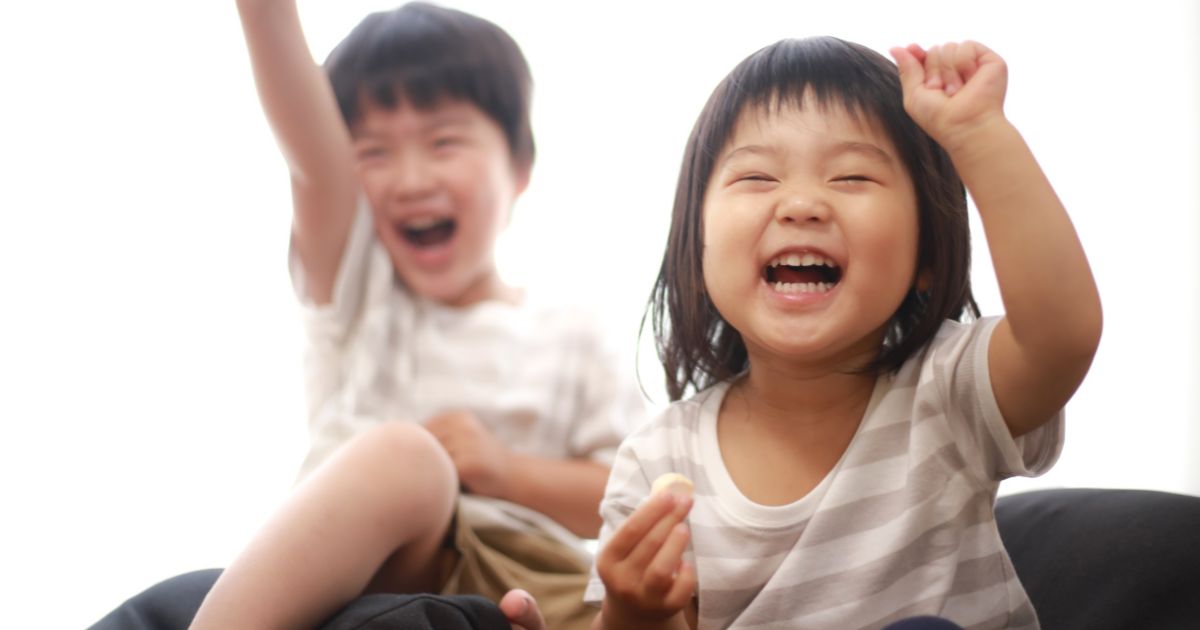
大谷家の “2つの習慣” は、今日からどの家庭でもできる
MVPに輝いた大谷翔平選手の強さを支えた大谷家の子育てに、特別な英才教育はありませんでした。
高額な習い事も、厳しいスパルタ指導も、細かなスケジュール管理もなし。それでも世界最高峰の舞台で活躍する人間が育ったのは、家庭に2つのシンプルな習慣があったからです。
- 子どもの考えを否定しない
- 子どもに問いかける
この2つの習慣が、子どもの主体性と挑戦力を大きく育てていました。問いかけは、子どもに「自分で考える力」を与えます。否定しない姿勢は、「自分の考えを信じる力」を育てます。どちらも、今日からすぐに実践できることばかりです。
完璧な親である必要はありません。ひとつでもいいので、日常のなかで声かけを変えてみてください。その小さな習慣の積み重ねが、子どもたちに「自分で未来を切り開く力」を育てていきます。
***
大谷翔平選手の活躍に驚かされるたび、「才能がすごい」と思いがちです。でも、その才能を最大限に引き出したのは、家庭での日常的な関わり方でした。問いかけること、子どもを信じて任せること。どちらも特別な準備はいりません。今日の夕食後、お子さんに「そのとき、どう思った?」と聞いてみることから始めてみませんか。
(参考)
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|「教育虐待」のやっかいな実態。今の子どもには “決定的に足りない” 時間がある
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|自己肯定感が「高い子の親」と「低い子の親」。驚くほど全く違う、それぞれの特徴とは
女性自身|大谷翔平「有能感」を育てた両親の叱らない“肯定教育”
ダイヤモンド・オンライン|大谷翔平と藤井聡太「天才の親」に共通する、たった1つの心構えとは?
















