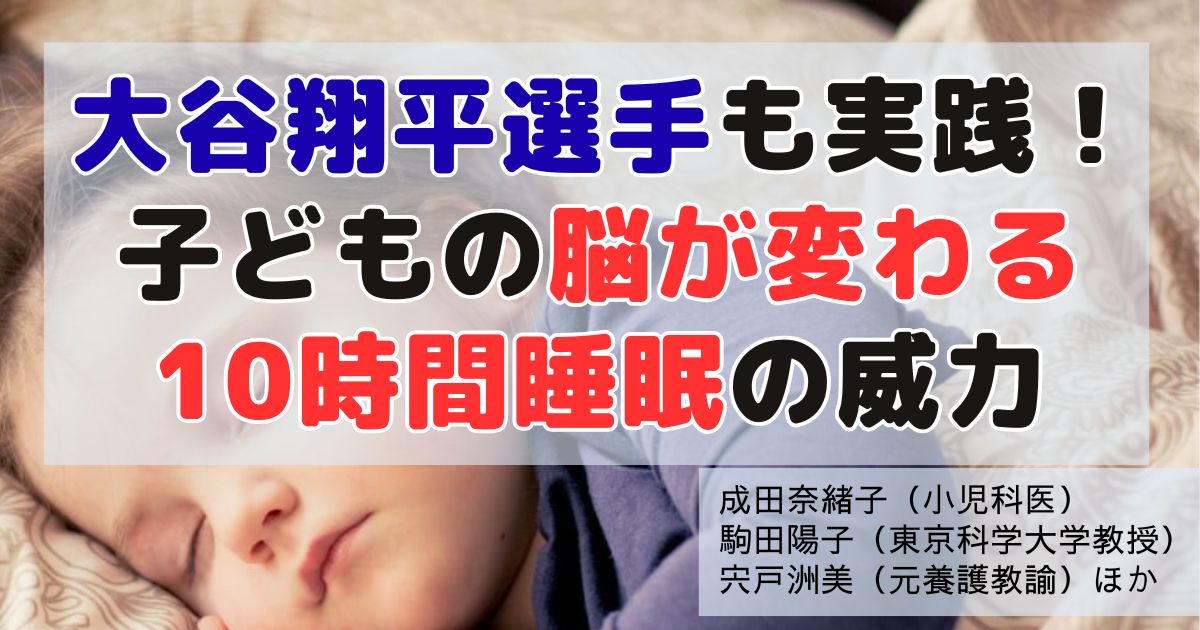メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手は「1日に10時間の睡眠をとっている」というのは有名な話ですよね。 世界最高峰のアスリートが睡眠を最重要視していることからも、最高のパフォーマンスには質の高い睡眠が不可欠だということがわかります。
しかし現実は、スマホやゲームの影響で十分な睡眠をとれていない子どもが急増中。本記事では専門家の意見をもとに、子どもの睡眠不足がもたらす影響や、理想的な睡眠時間、寝かしつけの工夫、夜更かしを防ぐポイントなどを解説。子どもの睡眠に関するお悩みを抱えいる保護者の方は必読です!
目次
子どもの成長を支える「睡眠習慣」の本当の役割
■宍戸洲美氏(元養護教諭)
子どもにとって十分な睡眠は、単なる休息ではなく「成長の土台」となるもの。睡眠不足は脳や体の発達に直結し、感情のコントロールや学習意欲にも大きな影響を与えます。
夜更かしや不規則な生活が続くと、集中力の低下やイライラが増えるだけでなく、肥満や生活習慣病のリスクも高まるというデータも。実際に、授業中に眠そうな子どもほど学習効率が下がり、友人関係のトラブルにつながることも少なくありません。
また、睡眠中には成長ホルモンが分泌され、骨や筋肉の発達、記憶の整理が行われます。つまり「寝る子は育つ」は科学的にも裏づけられているのです。親は、「睡眠不足は性格の問題ではなく、環境や習慣に起因する」という視点をもちましょう。
【子どもの睡眠習慣を整えるポイント】
- 就寝時刻を決め、毎日ほぼ同じ時間に寝かせる
- 夜はテレビやスマホなど明るい画面を避け、部屋を暗めにする
- 睡眠不足を「性格の問題」とせず環境要因として考えて生活習慣を見直す
もっと詳しく!
スポーツを習えば体力が向上するとは限らない!? 子どもの体力アップの秘訣・3か条
理想的な睡眠時間は? 年齢別の目安と日本の現状
■成田奈緒子氏(小児科医)ほか
「結局、子どもは何時間眠れば十分なのか」という問題について、専門家は「5歳で11時間、小学生で10時間程度が理想」と提示しています。米国睡眠財団の基準でも同様に、幼児は10~13時間、小学生は9~11時間、中高生は8~10時間の睡眠が望ましいとされています。
ところが日本の子どもは、世界的に見ても就寝時間が遅く、平均睡眠時間も短い傾向にあるのだそう。夜更かしが常態化すると、学習や運動に必要なエネルギーが不足するだけでなく、翌日の気分の落ち込みや集中力低下を引き起こします。
たとえば、22時に寝る子と23時半に寝る子では、翌朝の表情や授業中の態度に明らかな差が生じるのです。理想の睡眠時間の目安を意識して、家庭で「何時に布団に入るか」をルール化することが、習慣づけの第一歩と言えるでしょう。
【子どもの睡眠習慣を整えるポイント】
- 子どもの年齢に合った睡眠時間を把握する
- 起床時間を基準にして、逆算して就寝時刻を決める
- 平日・休日の就寝起床リズムを崩しすぎない
もっと詳しく!
子どもの脳をきちんと育てる「正しい睡眠」
“世界一寝不足” な日本の子ども。「11時間37分」が示す、眠りにまつわる切実な問題

睡眠不足が学習・発達に及ぼす意外な影響とは
■駒田陽子氏(東京科学大学教授)
睡眠と成績には深い関係があることをご存知でしょうか。睡眠不足の子どもは、テストの点数や授業の理解度が低下しやすく、長期的には学力差にもつながることがわかっています。これは、記憶を整理・定着させる働きが睡眠中の脳でおこなわれるためです。
特に記憶の司令塔である海馬は、十分な睡眠がなければ機能が低下するということがわかっています。また、睡眠不足は感情の安定にも影響し、自己肯定感の低下や友人関係のトラブルにも結びつきます。
たとえば「寝不足でイライラして友達とケンカが増える」といった事例は珍しくありません。さらに、成長期の体づくりやホルモン分泌にも関わるため、長期的に見ると心身の発達そのものを阻害してしまう危険があるのです。学習面・発達面の双方からも、睡眠の重要性は見過ごせませんね。
【子どもの睡眠習慣を整えるポイント】
- 毎日の睡眠が「学習効率」に直結することを意識する
- 学習時間よりもまず睡眠時間を優先する意識をもつ
- 人間関係のトラブルは寝不足が原因で起こることもあると親子で話し合う
もっと詳しく!
寝るのが遅いと自己肯定感が下がる。デメリットだらけの「子どもの睡眠不足」
ぐっすり眠れる! 子どもをすんなり寝かしつける工夫
■成田奈緒子氏(小児科医)
寝かしつけのカギは「親の心の余裕」です。親が焦ったりイライラしたりすると子どもはかえって眠れなくなってしまうため、まずは入眠を促す環境づくりを整えましょう。ポイントは体温と室温を調整すること。
眠るには副交感神経が優位になる必要がありますが、その際に体温は自然と下がっていくのだそう。入眠のタイミングで体温を下げるには、入浴は就寝1時間前までに済ませるのが理想です。また、子どもは大人より体温が高いため、厚着や掛け布団の重ねすぎはかえって寝苦しさを招くことも。エアコンは「親が少し肌寒い」と感じる程度に設定するのがおすすめです。
さらに、寝室を落ち着いた雰囲気に整えることも効果的。照明を暗めにし、静かな音楽や絵本の読み聞かせでリラックスできる空間をつくるとよいでしょう。毎晩のルーティンが「眠る合図」となり、入眠がスムーズになりますよ。
【子どもの睡眠習慣を整えるポイント】
- 就寝の1時間前までに入浴を終える
- 室温は「少し涼しい」と感じる程度に調整する
- 親自身がリラックスして子どもに「安心感」を伝える
もっと詳しく!
親の緊張で子どもは寝つけない? 寝かしつけに必要な「親のリラックス」

夜更かし・スマホ依存を防ぐためにできること
■成田奈緒子氏(小児科医)ほか
夜更かしの大きな要因の一つがスマホやゲーム機です。デジタル機器の画面から出る強い光は、眠気を誘うホルモン「メラトニン」の分泌を妨げるのため、寝る直前まで触れている状態は避けたいですよね。
とはいえ、大人でも自制するのが難しいデジタル機器を子どもに我慢させるのは、大人以上に困難がともなうもの。できれば、物理的な仕組みで時間制限を徹底させましょう。たとえば、Wi-Fiを夜10時で自動停止する、リビングに充電ステーションを設置するなど、親子でルールを徹底できる仕組みを導入するのがおすすめです。
また、休日と平日の睡眠リズムの差が「ソーシャルジェットラグ」を生み、時差ボケのように心身のリズムを乱すことも。実際、「休日に遅くまでゲームをして月曜の朝がつらい」という子は多くいます。夜更かしやスマホ依存を防ぐには、家庭全体で「夜は眠るための時間」と意識を共有することが不可欠です。
【子どもの睡眠習慣を整えるポイント】
- スマホやゲームの使用時間を「仕組み」で制限する
- 就寝前は部屋を暗めにして、光の刺激を避ける
- 休日もできるだけ平日と同じ時間に起きる
もっと詳しく!
なにより睡眠が基本! 親の「ブレない」態度が、子どもの脳を育てる
スポーツを習えば体力が向上するとは限らない!? 子どもの体力アップの秘訣・3か条
「起きる時間」を意識させるだけ! 子どもの早起きを楽にするちょっとしたコツ
家族みんなで取り組む「睡眠習慣づくり」
■駒田陽子氏(東京科学大学教授)
子どもの睡眠習慣というのは、家族全員の生活リズムに大きく左右されます。日本では親子の添い寝が一般的で、親が夜遅くまで起きていると、子どもも同じように夜更かししがちな傾向があり、子どもだけに「早く寝なさい」と言っても効果は薄いのです。
正しい睡眠リズムを習慣化するには、家族みんなが「睡眠を大切にする姿勢」を共有することが不可欠。たとえば、親もスマホを夜遅くまで見ない、就寝前は家族でリラックスできる習慣をもつなど、小さな工夫が子どもの生活リズムに直結することを忘れないようにしましょう。
また、休日も親が朝寝坊せずに起きることで、子どもの起床時間も安定します。睡眠習慣は「子どもの問題」ではなく「家族の生活意識そのもの」です。親自身がモデルとなり、家庭全体で健やかな生活リズムを築いていけるといいですね。
【子どもの睡眠習慣を整えるポイント】
- 親も一緒に「早寝早起き」を心がける
- 食事や入浴など、家族で生活リズムをそろえる
- 家族で「寝る前の過ごし方」を工夫して共有する
もっと詳しく!
“世界一寝不足” な日本の子ども。「11時間37分」が示す、眠りにまつわる切実な問題

子どもの睡眠に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 子どもが寝る前に本を読むのはよいですか?
A. 読み聞かせはリラックスにつながり、安心感を与える効果があります。ただし、長くなりすぎないよう注意しましょう。
Q2. 昼寝はどれくらいさせても大丈夫?
A. 幼児なら30分〜1時間程度がおすすめ。遅い時間の昼寝は夜の寝つきを妨げるため、午後3時までに終えるのが理想です。
Q3. 子どもが「眠くない」と言ってなかなか布団に入らないときは?
A. 「眠りなさい」と強制するのではなく、部屋を暗くする・静かな音楽を流すなど、眠りに入りやすい環境を整える工夫をしましょう。
***
子どもの睡眠習慣は、学習や心の安定に直結する大切な生活習慣です。夜更かしやスマホの使用が増える現代だからこそ、親が意識的に環境を整え、家族で取り組むことが重要。今日からの小さな工夫で、子どもは「よく眠り、よく育つ」生活リズムを身につけていくでしょう。
(参考)
STUDY HACKER|月・水・金は筋トレ、火・木は勉強……そんな朝活は9割続かない。継続の達人が守っている朝活習慣化ルール
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|スポーツを習えば体力が向上するとは限らない!? 子どもの体力アップの秘訣・3か条
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|子どもの脳をきちんと育てる「正しい睡眠」
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|“世界一寝不足” な日本の子ども。「11時間37分」が示す、眠りにまつわる切実な問題
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|寝るのが遅いと自己肯定感が下がる。デメリットだらけの「子どもの睡眠不足」
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|親の緊張で子どもは寝つけない? 寝かしつけに必要な「親のリラックス」
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|なにより睡眠が基本! 親の「ブレない」態度が、子どもの脳を育てる
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|「起きる時間」を意識させるだけ! 子どもの早起きを楽にするちょっとしたコツ