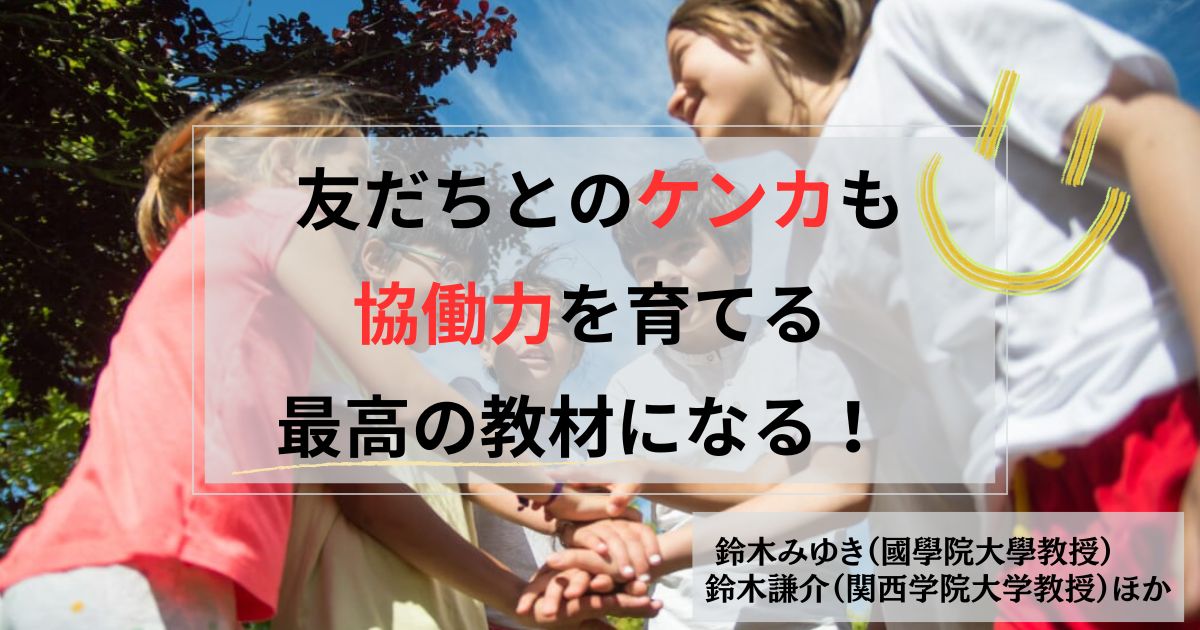「うちの子、友だちとうまくやっていけるかしら」「もっと協調性のある子に」――そんな悩み、ありませんか? でもじつは、いまの時代に必要なのは “ただ仲良くする力” ではないのです。
グローバル化が進む現代で求められるのは、「自分らしさを保ちながら、違う考えの人とも力を合わせて目標を達成する力」――それが「協働力」。
「協調性と何が違うの?」「どう育てればいい?」そんな疑問にお答えします。この協働力こそ、お子さんの将来を大きく左右するカギ。教育専門家が教える「協働力の育て方」を、いますぐ家庭で始められる具体的な方法でご紹介。きっと「これならわが家でも!」と思える内容です。
目次
「ひとりで頑張る」だけでは足りない。子どもに協働力が求められる理由
コミュニケーション能力が重視される現代社会において、人に合わせる力や空気を読む力などが過度に求められるようになりました。もちろんそれらはあるに越したことはありませんが、集団生活において必要とされる「協働力」の本質はもっと深いところにあります。
教育ジャーナリストの中曽根陽子氏は、いまの子どもたちに必要なのは「21世紀型能力」であり、そのなかでも「自ら考え、課題を発見し、他者と協力して解決していく力」が不可欠だと語ります。特にグローバル化が進む現代、多様な価値観をもつ人と協力し合うことの重要性は、ますます高まっていると言えるでしょう。
また、玉川大学教育学部教授の大豆生田啓友氏は、「自己決定力と協働性は表裏一体」であるとしたうえで、自分の考えを大事にしながら他者とともに生きる力こそ、自分らしく豊かに生きるための土台となると話します。
子どもが協働力を育むには、「自分の意見をもつこと」や「違う価値観と出会うこと」が欠かせません。そのためには、家庭や学校など日常生活のなかで、多様な人や考え方に触れる機会を意識的につくることが大切です。親子の会話でも、「あなたはどう思う?」といった問いかけを通して、自分と他者の考えを往復する習慣を育てていきましょう。

協働力は「ただの協調性」じゃない? 個性がチームの力になるとき【松尾英明氏】
「本来の協働力とは、チームの総合力を最大化する力」と話すのは、千葉大学教育学部附属小学校を経て、現在は千葉県公立小学校教諭の松尾英明氏です。
たとえば、「算数が得意だけど作文が苦手な子」と「表現力に優れているが計算は苦手な子」が協力すれば、互いの力を補いながら成果を出すことができますよね。このように、集団のなかで一人ひとりの個性や得意を活かし合い、力を合わせて成果を出せるように導いたり、まとめたりする力を意味します。
そのために必要なのは、「みんな同じ」であることではなく、「みんな違って、それがいい」と認め合う姿勢。そして、子どもが自分の特性を理解し、強みを自信に変えていくことです。家庭でも、「苦手を責めず、得意を伸ばす」関わり方を心がければ、子どもは自然と他者と力を合わせる喜びを体感できるようになるでしょう。
また、苦手なことがあっても「恥ずかしい」と思わず、「得意な人に頼る」ことをポジティブに捉えるのも、協働力を育てるうえで重要な視点です。たとえば、子どもが「これ、○○ちゃんに手伝ってもらったんだ」と嬉しそうに話すような体験が増えれば、それは確実に協働の感覚が育っている証拠。失敗や苦手を “チームで補い合うこと” にポジティブな価値を見いだせるような声かけや関わりが、親にできる最大のサポートです。
【協働力の伸ばし方】
- 子どもの得意を見つけて「助かるよ、ありがとう!」とフィードバックする
- 苦手なことがあっても「誰かと協力すればできるよ」と伝える
- チーム活動や係活動などを積極的に経験させる
もっと詳しく!
求められるのは「創造」「創造」「協働」の力・「困っている子」がいてありがたい!?
家族が「最初のチーム」になる。協働力は家庭から育てよう!【ボーク重子氏】
ライフコーチのボーク重子氏は、「家族こそが最初のコミュニティ」であり、協働力を育てる最も身近な場であると語ります。たとえば、家庭内でのルールづくり。親が一方的に決めるのではなく、「どうすれば家族みんなが快適に過ごせるか」を子どもと話し合いながらルールをつくる経験は、子どもにとって貴重な協働体験となります。
また、「週末の家族掃除」や「晩ごはんの準備当番」など、目標を共有し、役割を担い合う活動も効果的です。それにより、責任感や思いやり、感謝といった社会性の芽が自然と育まれていきます。さらに、スポーツ活動や遊びを通じて、年齢の違う人たちと「協力して楽しむ」経験を重ねることも、家庭でできる立派な協働体験の実践となるでしょう。
ボーク氏は、「家族を “目的のあるチーム” と捉えることが大切」だと述べています。具体的には「来週のピクニックの準備を分担しよう!」など、家族全員でゴールを共有するようなイベントがあると、協働の意味が実感しやすくなるはず。小さな家庭内プロジェクトの成功体験は、「一緒にやると楽しい」「助け合うって気持ちいい」という感覚が子どもの心に芽生えるきっかけになるでしょう。
【協働力の伸ばし方】
- 家族会議でルールや目標を子どもと一緒に決める
- 家事などで「子どもの役割」をつくり、感謝を伝える
- スポーツや遊びで「協力して楽しむ」経験を大切にする
もっと詳しく!
「ルールを守れる子ども」はこうして育つ。親が子に与えるべき大事な“時間”

“知らない人とやる” から、ぐんぐん伸びる! 自然体験が育てる「真の協働力」【鈴木みゆき氏】
自然体験には、子どもの心と体を育てる多くのチャンスが詰まっています。とくに、親子だけでなく、地域の人やほかの家族と一緒に過ごす「ファミリーキャンプ」などの機会は、協働力を伸ばす絶好の場です。國學院大學人間開発学部教授の鈴木みゆき氏は、こうした自然体験を通して、「他者と協力する力」や「社会のなかでのふるまい」を子どもが自然に学ぶことができると話します。
たとえば、キャンプ中の役割分担や、お兄さん・お姉さんとのやりとり、親以外の大人と接する経験は、子どもにとって「斜めの関係」を築く貴重な学びの一環に。また、年上の子から技や知識を教わったり、自分が年下の子に何かをしてあげたりするなかで、子どもは「人と関わる心地よさ」を体感していきます。つまり、日常の延長にある自然体験は、協働力の基礎を築く「生きた学び」の場と言えるでしょう。
さらにこうした体験は、親自身の意識を変えるきっかけにもなります。キャンプでほかの親と協力するなかで、自然と大人同士のコミュニケーションも活性化され、それが子どもたちにも伝播することに。親が楽しそうに協働する姿を見せることこそが、子どもにとっての最高の教材になるのです。
【協働力の伸ばし方】
- 親子で参加できる自然体験や地域イベントに積極的に参加する
- 年齢の違う子や大人と関わる機会をつくる
- 体験後は、「どんな協力ができた?」とふりかえりをしてみる
もっと詳しく!
「大人の愛」と「協働力」が子どもを大人に導いていくーー親以外の人との交流によって広がる子どもの視界
「ケンカになる前に話せる子」に。“アサーティブ” な子が育つ親子の対話術【鈴木謙介氏】
関西学院大学教授の鈴木謙介氏は、協働力を育むうえで「アサーティブコミュニケーション」の重要性を説きます。これは、自分の意見を率直に伝えながらも、相手を否定せず尊重する話し方のこと。「自分はこう思うけど、あなたの考えにも一理あるね」と伝えられる子どもは、どのような場所・状況でも仲間として信頼されやすくなるのは明らかですよね。
アサーティブな姿勢は、家庭のなかでも育てることが可能です。鈴木氏によると、「子どもが親に頼みごとをするとき」がチャンスなのだそう。たとえ親が忙しくても、「いま言いたいことがある」と自分の伝えたいことを受け入れてもらえた経験は、子どもの自信と交渉力を育ててくれるでしょう。
また、親子間で対立が起こったときは、子どもの意見を最後まで聞き、丁寧に話し合うことが、協働スキルを鍛える実践の場にもなります。加えて、兄弟や友だちとのけんかの場面も、協働力を育てる好機です。すぐに介入せず、双方の気持ちを整理し、納得できる方法を一緒に考えましょう。そうすることで、子どもは「話し合いで問題を解決できる」という実感を得られます。このように、小さな衝突の積み重ねが大きな協働力の礎となるのです。
【協働力の伸ばし方】
- 子どもが意見を伝えてきたときは最後まで耳を傾ける
- 対立したときは「どうすればお互い納得できるか」を一緒に考える
- 日常のやりとりのなかで「伝え方・聞き方」の工夫を一緒に練習する
もっと詳しく!
“ひとりの天才”を目指すよりも大切なこと。“みんなで協力”できる力の絶大な価値

協働力はこうやって伸ばす! よくある5つのQ&Aで不安をまるごと解消
Q1. 「協働力」と「協調性」はどう違うのですか?
A. 協調性は「人に合わせる力」、協働力は「異なる考えをもつ人と、目的を共有しながら力を合わせる力」です。協調性が受け身になりがちなのに対し、協働力は主体性と他者理解の両方を必要とする、より実践的で能動的な力だと言えるでしょう。
Q2. 家庭で協働力を育てるには、何から始めればいい?
A. まずは「家族というチーム」でできることから始めましょう。たとえば、家事の分担、家族イベントの計画、ルールづくりなどです。「一緒に考える」「役割を果たす」「感謝を伝える」といった経験の積み重ねが、協働力の土台になります。
Q3. 子ども同士でけんかしたとき、親はどう対応するのが正解?
A. すぐに介入するよりも、子どもたちの話に耳を傾け、それぞれの気持ちを整理できるよう促すのが理想です。「どうすればお互い納得できるか考えてみよう」といった声かけが、問題解決力と協働スキルを伸ばします。
Q4. 学校では協働力をどう伸ばしているのでしょうか?
A. 学級活動、係活動、グループ学習などを通じて、子どもたちは他者と協力する体験を重ねています。家庭でもその経験に関心をもち、「今日は誰と協力したの?」「どんな工夫をしたの?」と対話を深めることで学びの定着が期待できるでしょう。
Q5. 年齢によって協働力の育て方は変えるべき?
A. 幼児期は「一緒にやってみる」遊びや生活体験、小学生以降は「自分の意見を伝える」「話し合いに参加する」経験がカギとなります。発達段階に応じて、体験の量と質を変化させながら関わることが大切です。
***
「自分だけが頑張る」でも、「人に合わせるだけ」でもない――協働力とは、違う価値観をもつ相手と目的を共有し、ともに前に進んでいく力です。これからの社会では、自分の意見をもちつつ他者も尊重できる子どもが、仲間から信頼され、活躍できるようになります。家庭や地域、自然体験など、身近なところから協働の力は育めます。まずは親子で「一緒に取り組む」小さな経験から始めてみましょう。
文/野口燈
(参考)
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|親の役目は我が子の「自己探求の力」を育むこと。“理想の子ども像”を押し付けてない?
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|親が先回りしたら「自己決定力」は育たない。幼くても決断力を伸ばせる声かけのコツ
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|求められるのは「創造」「創造」「協働」の力・「困っている子」がいてありがたい!?
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|「ルールを守れる子ども」はこうして育つ。親が子に与えるべき大事な“時間”
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|「大人の愛」と「協働力」が子どもを大人に導いていくーー親以外の人との交流によって広がる子どもの視界
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|“ひとりの天才”を目指すよりも大切なこと。“みんなで協力”できる力の絶大な価値