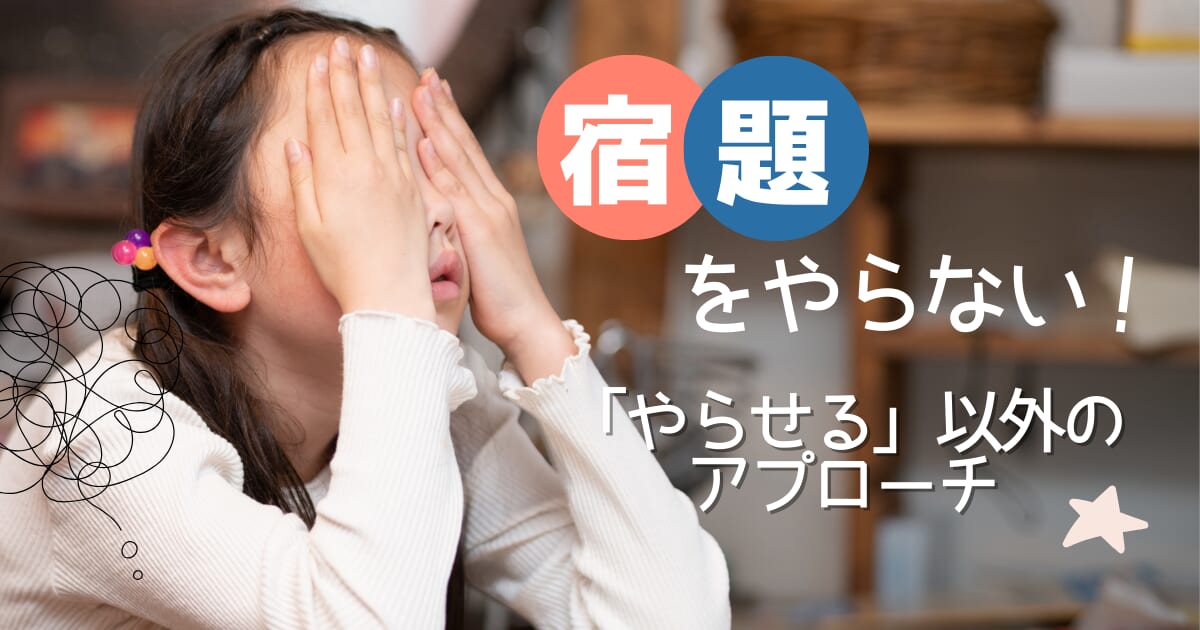夏休みや日々の家庭学習の場面で、多くの親が直面する悩み――「うちの子が宿題をやらない!」。やらない理由を問い詰めてもケンカになり、手を貸しすぎれば親の宿題に。では、結局どうしたらいいのでしょうか。
今回、こんなお悩みが届いています。
息子が宿題をやりません。ほっといていいでしょうか。(10歳男の子ママ)
多くの家庭で一番ストレスになるのは、「宿題=親の責任」と化すこと。親が毎日イライラして声をかけ続けると、子どもは「勉強=叱られること」と刷り込まれ、宿題が “学び” ではなく”苦痛”に変わってしまいますよね。
この記事では、元小学校教諭の経験をもとに、実際に宿題をやらない小学生の子どもへの具体的なアプローチ方法を原因別に整理してみます。
ライタープロフィール
元小学校教員
小学校教員・英語専科教員として12年間勤務、これまでに2,000人以上の子どもたちを指導。現在は、教育分野での執筆活動をはじめ、クリエイターやファミリーサポート・里親支援など多方面で活動中。2児の母。
イギリスやアメリカへの留学経験を通じて学んだペアレンティングの視点を軸に、日本の家庭でも実践できるヒントをお届けします。
目次
回答:「やらない」は怠けではなく “サイン” かも!――まずは原因を探ろう
子どもが宿題を拒むと、親はつい「サボっている」「反抗している」と受け止めがちです。しかし、「やらない行動」は多くの場合、困難や学習への抵抗感のサインであることがあります。
よくある理由:
- 疲れていて集中できない
- 単調すぎて退屈、やる意味を感じない
- 内容が難しすぎて手が出ない
- 「やらされ感」に反発している
- 学習に関する困難を抱えている
まずは「なぜやらないのか」を観察し、子どもに聞くことから始めましょう。原因によって、アプローチ方法が変わってきます。上記の理由からひとつずつ解説していきます。
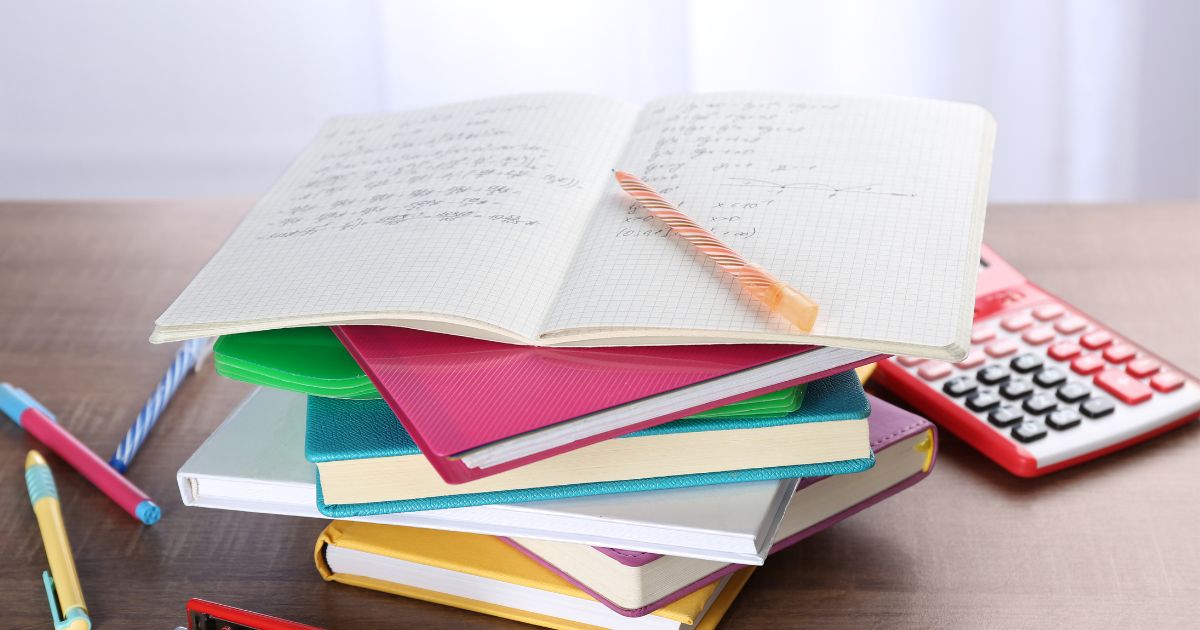
原因①:疲れていて集中できない→「時間・空間の確保を」
【アプローチ1】落ち着いて宿題ができる時間・空間を確保する
5・6時間の授業、友達との関わり、給食当番や掃除、習い事……小学生もハードな一日を過ごしています。無理に宿題をやらせるのではなく、子どもの状態に合わせた時間や環境を整えることが大切です。
まずは「お帰りなさい、今日はどんな一日だった?」と子どもの気持ちに寄り添うところから始めてみてください。さらに、しっかり睡眠や食事はとれているか、悩んだり困ったりしていることはないかじっくり観察してください。ほかにも、習い事を詰め込んでいっぱいいっぱいになっていないかも改めて確認しましょう。
そのうえで、落ち着いて宿題ができる時間・空間を確保してあげましょう。
具体的な方法:
- 十分な休息を取ってから宿題に向かう時間をつくる
- 「宿題をやったら夕飯」などできそうな時間を一緒に考える
- 机から気を散らすものを移動させ、環境を整える
- 「リビング・居間」など、家族の気配が感じられる場所で取り組む
多くの家庭では、個室よりもリビング・居間など、家族の気配が感じられる場所の方が、子どもは安心して集中できるケースが多いようです。また、どうしても時間がとれない、とても疲れている場合は、無理にさせる必要はありません。担任の先生に、事情を説明しましょう。先生も夜遅くに宿題をやってほしいとは思っていません。
原因②:単調すぎて退屈、やる意味を感じない→「宿題はやらずに置き換え」
【アプローチ2】思い切って柔軟な学びに置き換えることを提案する
「この宿題って意味あるの?」「何で何度も同じ字を書くの?」と自分自身も小さい頃に思ったことがあるのではないでしょうか? 実際に、イー・ラーニング研究所の「2022年:子どもの日常的な宿題に関する調査」によると、親自身も約3割が日常的な宿題を「必要だと思わない」と回答し、その理由の7割超が「 “ただ” こなす学習になっているから」でした。実際に、多くの学校で宿題のあり方が見直されているのが現状です。
本当の学びとは、子どもが「なぜ?」「どうして?」と自然に思えることから始まるものです。その目的であれば、宿題を別の学びに置き換えることも十分可能ではないでしょうか。
私自身が実際に過去に認めた例:
- 自由研究代わりに、家族の旅記録
- 計算ドリルの代わりに、クラスのみんなへの問題づくり
- 日記の代わりにスケッチと俳句
- 漢字学習の代わりに好きな物語の書き写し
学校や担任の先生によっては「代わりにこれをやりました」と提出して認められるケースもあります。担任の先生に事前に相談してみると、意外と柔軟に対応してもらえるかもしれません。

原因③:「やらされ感」に反発している→「やる・やらないを子どもが選択」
【アプローチ3】子どもに選択権を渡す
「いま宿題やりなさい!」と言った瞬間の子どもの表情。ムッとした顔、「やろうと思ったのに!」と反抗的な態度……。これは決してわがままではなく、誰だって一方的に指示されるより、自分で行動するタイミングを決めたいと思う人間として自然な反応です。
そこで効果的なのは、子どもに選択権を渡すことです。子どもたちに「どうする?」と選択肢を与えた時の目の輝きは特別なものがあります。
具体的な方法:
- 「いつやる?」と時間を一緒に決める
- 「どこから始める?」と取り組む順番を選ばせる
- 「今日は何時間くらいかかりそう?」と見通しを立てさせる
- 計画表を一緒に作る
子どもに選択権を渡しても、それでもどうしても宿題に向かわない日もあるでしょう。そんな時は、無理にやらせずにそのまま学校へ。提出できずに先生に指摘される → 恥ずかしい思いをする → 次から工夫する。このプロセス自体が、責任を引き受ける学びになります。
原因④:内容が難しすぎて手が出ない→「できるところだけ」
【アプローチ4】できるところだけ取り組み、段階的に復習を
宿題を広げるがなかなか進まないなら、内容が難しすぎて手が出ないかもしれません。これは決して「やる気がない」わけではなく、「どこから手をつけていいか分からない」状態です。
まずは一緒に問題を見て、どこまでできるかを確認します。「5分だけ」「1ページだけ」と小さく区切り、できる部分から始めましょう。小さな「できた」を積み重ねることで、子どもは自信を取り戻していきます。
具体的な方法:
- 最初の1問を一緒に解いて見せる
- 似たような簡単な問題から練習する
- わからない問題には付箋を貼って、後で先生に聞くよう促す
場合によっては、ひとつ前の単元を復習する必要があるかもしれません。この場合も担任の先生に相談することで、個別の学習(宿題)計画を考えてもらえることもあります。掛け算ができなければ割り算ができないように、子どもがどこでつまずいているのか見極めることが肝心です。
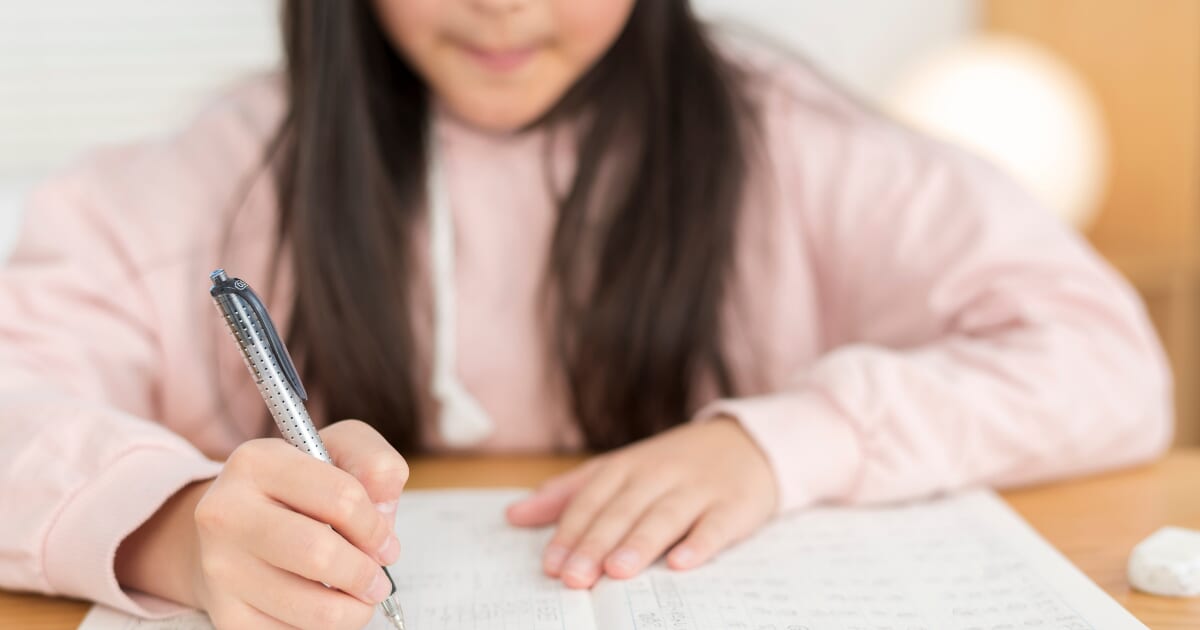
原因⑤:学習に関する困難を抱えている→「専門的サポートを」
【アプローチ5】専門的サポートを活用する
文字がマス目に収まらない、計算の順序が覚えられない、読むのにかなり時間がかかる……。これらが継続的に起こる場合、学習方法を工夫するだけでは解決しない根本的な困難があるかもしれません。
このような場合は、その子の特性に合った学習方法を見つけることが最優先です。たとえば、書字が困難ならタブレット入力、計算が苦手なら電卓使用など、「できる方法」を探すことで、本来の学習内容に集中できるようになります。
具体的な方法:
- 担任の先生・学年主任への学習面の相談
- スクールカウンセラーへの発達面の相談
- 教育センターや専門機関での学習特性検査
- その子に合った学習支援ツールや方法の検討
大切なのは「宿題をやらせること」ではなく、その子にあった学びを探すことです。
***
宿題の本質は「子どもが自分で学ぶこと」。親の役割は「やらせる」ことではなく、子どもが「やりたい」と思える環境と機会を整えること、です。
「宿題をやらない」姿に親はつい不安になりがちですが、宿題そのものは教育のゴールではありません。むしろ宿題を通して、自分で選ぶ力、責任を引き受ける経験、学びを楽しいものに変える工夫を育むことの方が、ずっと大きな意味をもつのではないでしょうか。
(参考)
株式会社イー・ラーニング研究所|「2022年:子どもの日常的な宿題に関する調査」
ベネッセ教育情報|夏休みの自由研究、やらなくてもOK?どう取り組む?保護者のホンネ調査