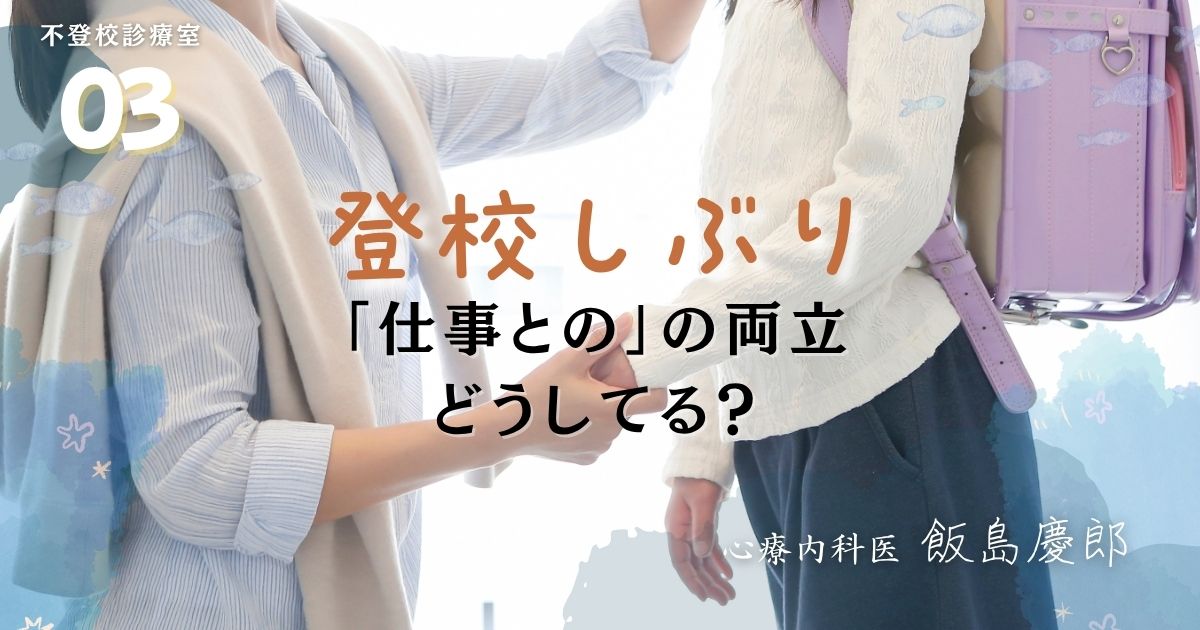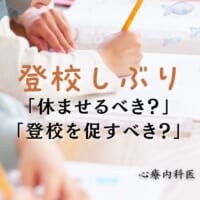「今日も学校に行かない」「どうしても行きたくない」——子どもがこんなことを言う日が増えてきた。こうした登校しぶりが続くなかで、働く親は「子どもに寄り添いたい」気持ちと「仕事はどうしよう……」という不安のあいだで板挟みになります。
文部科学省の調査(令和5年度)では、小中学生の不登校は約34万6千人と過去最多を記録しました。内訳を見ると、小学生が約13万人、中学生が約21万6千人となっており、この数は11年連続で増加傾向にあり、初めて30万人を突破しました。
登校しぶり・不登校は決して特別なことではなくなりつつあります。しかし一方で、多くの保護者が「誰にも相談できない」と感じているのも現実です。特に働く親にとっては、子どもの登校しぶりは突然やってくる課題として、日々の生活に大きな影響を与えています。
今回届いたお悩みは、こちら。
今回も、不登校/こどもと大人の漢方・心療内科 出雲いいじまクリニック 院長の飯島慶郎先生の監修のもと、働く親が直面する「登校しぶりと仕事の両立」について回答していきます。
監修者プロフィール
精神科医・総合診療医・漢方医・臨床心理士
不登校/こどもと大人の漢方・心療内科 出雲いいじまクリニック 院長。島根医科大学医学部医学科卒業後、同大学医学部附属病院第三内科、三重大学医学部付属病院総合診療科などを経て、2018年、不登校/こどもと大人の漢方・心療内科 出雲いいじまクリニックを開院。
多くの不登校児童生徒を医療の面から支えている。島根大学医学部精神科教室にも所属。
目次
基本的には仕事を続けることをおすすめします
まず「登校しぶり」と「不登校」の違いを知っておきましょう。文部科学省では、病気や経済的理由を除いた年間30日以上学校を休んだ場合を「不登校」と定義しています。それより前の段階で、学校に行きたがらない状態が続くのが「登校しぶり」です。
今回のお悩みは「登校しぶりが続いている」段階での相談です。その前提をもとにお答えしてきます。
あまりに忙しく、全くお子さんとの時間が取れないという場合は論外ですが、そうでなければ基本的には仕事を続けることをおすすめします。親が仕事を続けることで、経済的安定を保ちながら適度な距離感を維持でき、社会とのつながりも保てます。どうしてもお子さんを一人にしておけない事情が生じた時点で離職を検討するべきでしょう。お子さんと一緒にいる時間を増やすことも大切ですが、親子といえどもずっと一緒にいるとなると互いに息が詰まることもあるものです。基本的には長期間におよぶことの多い不登校援助の場において、親の「逃げ場」、子の「逃げ場」をあえて用意しておくことも大切かもしれません。

ほかの家庭では「登校しぶり」と「仕事」の両立どうしてる?
では、実際に登校しぶりを経験している働く親たちは、どのような工夫をしているのでしょうか。さまざまな家庭の実例を見てみましょう。
◆午後からの在宅勤務で調整
◆夫婦分担制で負担を軽減
◆学校との連携で午後登校を実現
◆子どものペースに合わせた柔軟対応
◆祖父母の協力で朝の時間をサポート
◆ファミリーサポートで専門的な見守り
対応策は一つではありません。登校しぶりの原因や、家庭の状況、仕事の性質、子どもの年齢や性格によって、最適な対応方法は大きく異なります。ポイントは以下です。
- “朝の時間” にこだわらず、登校のハードルを下げる
- ひとりで抱え込まず、家族やサポート機関に協力を求める
- 学校の先生や、養護教諭、スクールカウンセラーとしっかり連携をとる
- 「今日は無理そう」と思ったら、家庭で心と体の休息時間に切り替える判断をする
特に、担任の先生や養護教諭と事前に相談し、子どもの状況に応じた対応方法を決めておくことで、親も安心して対応できるようになります。無理に登校させることで状況が悪化するのを防ぎ、長期的な視点で子どもをサポートしていくことができます。

“親の心の余裕” がいちばんの支えになる
登校しぶりと仕事の両立を考えるうえで最も重要なのは、親自身の心の余裕を保つことです。子どもは、親の「安心感」「余裕感」にとても敏感で、親が焦ったり不安になったりすると、その感情を敏感に察知してしまいます。
親の心に余裕があると、子どもも安心して自分の気持ちを伝えられるようになります。そうした信頼関係が、登校しぶりの根本的な解決につながっていくのです。登校できた日も、できなかった日も、子ども、そして親自身も責めないことが回復への土台となるのです。
***
完璧な両立を目指すのではなく、その日その日の子どもの状態に合わせて柔軟に対応することが何より大切です。親の心に余裕があれば、子どもも安心して学校生活に向き合えるようになります。
ひとりで抱え込まず、家族や学校、地域のサポート資源を積極的に活用しながら、子どもと一緒に歩んでいきましょう。登校しぶりは必ず改善できる課題です。焦らず、長期的な視点をもって、子どもの成長を見守っていきましょう。
文部科学省|令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
子ども家庭庁|こどもまんなか応援サポーター 子育て支援の制度まとめ
子どもの権利相談窓口(チャイルドラインなど) 子どもが直接相談できる窓口
NPO法人フリースクール全国ネットワーク| 民間による居場所の提供