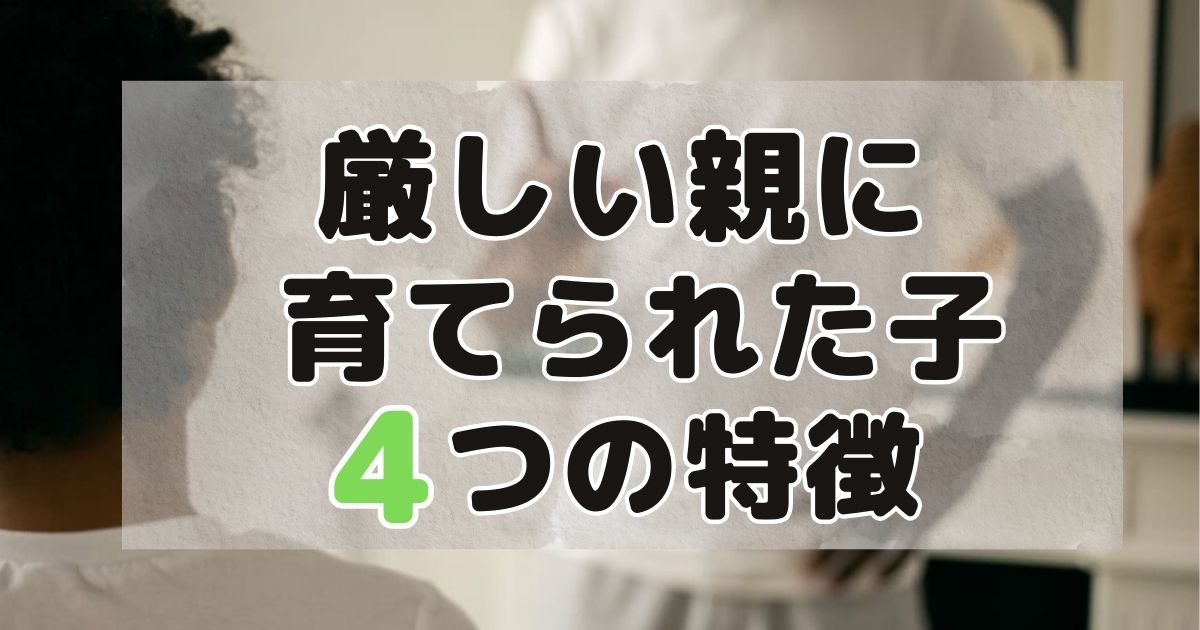「厳しいしつけは本当に子どものためになるの?」と悩む保護者の方は少なくありません。子を思うがゆえの厳しさはよい影響をもたらすこともありますが、過度になるとわが子の心に負担をかけることも。本記事では、親が厳しい家庭で育った子どもの特徴やメリット、つらいと感じたときの対処法を解説します。
目次
「うちはちゃんと子どもをしつけている」という実感を得たい親たち
わが子に注意したあとに、「ちょっと厳しすぎたかな……」「感情的に叱ってしまった……」と反省したことがない親はいないのではないでしょうか。親といっても人間なので、子どもの言動に対していつでも冷静に対応するのは不可能です。でも、「まわりに比べて、うちはしつけに厳しすぎるかな?」「いやいや、甘やかすよりは数倍マシ!」と揺れ動くこともありますよね。
もちろん適度なしつけは、お子さんの将来に必ず役に立ちます。あいさつや礼儀、人間関係でのマナーや社会性など、一般的な常識を身につけさせるためにも、親のしつけは必要不可欠です。
一方で、「叱る=しつけ」と考える保護者も多く、厳しく叱ることがしつけの一環として許容されているケースも。臨床心理士の村中直人氏は、「人前で迷惑をかけたり、食事のマナーが悪かったりしたときに『こうやるの!』と厳しく叱ると一度は修正されるため、これで親は “ちゃんとしつけた” という実感を得やすい」と指摘しています。
しかし、叱るという行為で子どもを思い通りに動かしたとしても、親側は育児や教育へのモチベーションが上がるものの、“叱られる側” の子どもは強いストレスを受けてネガティブな感情に支配されてしまうといいます。
次項では、「親が厳しい子どもの特徴」として、心理や行動に表れるサインについて解説していきましょう。

親が厳しい子どもの特徴|心理や行動に表れる4つのサイン
親が厳しい家庭で育った子どもには、どのような特徴が見られるのでしょうか。専門家の見解は以下のとおりです。
1. チャレンジすることを恐れるようになる
親から厳しく叱られ続けた子は、チャレンジを恐れたり、粘り強く頑張ったりすることが苦手になる傾向があります。村中氏によると、叱られ続けると、脳の機能が一時的に低下する状態がつねに起こるため、脳が「防御モード」になるのだそう。
本来は危機的な状況下で発動される「防御モード」に切り替わると、戦うか逃げるか、どちらかの行動を選択しなければなりません。子どもが叱られる場合、叱ってくる相手は親や先生など自分よりも権力があるため、逃げる(=言うことを聞く、とっさに謝る)ことがほとんどでしょう。
また、新しいことにチャレンジして、試行錯誤しながら粘り強く頑張る状態を「冒険モード」といい、村中氏によると「冒険モード」と「防御モード」は同時に成立することができないのだと言います。つまり、親から叱られ続けた結果、何かに挑戦したり、努力して頑張り続けたりすることを避けるようになってしまうのです。
2. 他人を信じられず対人関係が不安定になるので人間関係に悩みがち
「子どもに対するしつけが厳しすぎる環境で育った人は、“アダルトチルドレン(AC)”と呼ばれる特徴をもつことがある」と指摘するのは、児童精神科医さわ氏です。ACは、アイデンティティや感情が不安定だったり、他人を信じられなかったりと、さまざまな苦しみを抱えたまま大人になっている人のこと。どことなく「生きづらさ」を抱えているため、人間関係に悩みやすいのが特徴です。
「どうしてできないの!」「何度も言ってるでしょ!」「あなたは本当にダメな子」など、親から人格を否定するような言葉をかけらて続けて育つと、「どうせ自分はダメな人間だ」と思い込むようになるのは容易に想像できます。
不完全でもありのままの自分を認めてもらえないと、自分に自信がなくなるだけでなく、他人を信じられなくなって人間不信に陥りかねません。「厳しく叱るのは、子どもが将来困らないため」という親の言い分も理解できますが、過度な厳しさは、わが子の「生きづらさ」につながる危険をはらんでいることを忘れずに。
3. 完璧主義で「~~すべき」思考にとらわれやすいため、しょっちゅう自己嫌悪に陥る
早稲田メンタルクリニック院長の益田裕介氏は、「厳しい親というのは、“べき思考”である可能性が高く、子どもの教育において多様性や創造性を認めない」傾向があると話します。ゆえに、そのような環境で育つ子どもは、大人になってから「~~すべき」「~~しなければならない」という思考に陥りやすいと指摘しています。
しかし実際は、理想とする完璧な自分になるのは至難の業であり、多くの人は理想と現実の折り合いをつけながら生きていくもの。ですが「べき思考」が強い人の場合、「自分は本当はこうしなきゃならないのに、できていない自分が情けない……」と必要以上に自分を責めてしまうのです。
過剰な向上心に苦しめられるだけでなく、自分を責めた結果動けなくなり、動けないことでまた「自分はなんてダメなんだ」と自己嫌悪に陥るという悪循環にハマってしまう――。それは確実に、“生きづらさ”の大きな要因になるでしょう。
4. 親に隠しごとをしたり問題行動を起こしたりする
必要以上に厳しく注意し続ける=子どもに「ダメ出し」を何度も繰り返すことに苦言を呈するのは、心理学者の植木理恵氏です。ダメ出しというのは、本人は自分が失敗したことを十分理解しているにもかかわらず、追い打ちをかけるように責めること。テストの点数が悪く、クヨクヨしている子どもに対して、「なんでこんな点数とったの?」「勉強が足りなかったんじゃない?」などと言葉をかぶせるのはNGです。
植木氏によると、「親から『あなたはできない』というメッセージを日常的に受け取っていると、子どもは萎縮し、親に隠しごとをするのが習慣になる」のだと言います。「これを言ったらまたお母さんに怒られる」「できないところを見られたら、またお父さんに注意される」と考えるだけで気を抜けないため、バレないように隠しごとをするようになるのも納得ですね。
さらに、そのようにして蓄積されたストレスを、友だち関係や学校で発散しようとして問題行動を起こす子も少なくないようです。親の前ではおとなしく、いい子を演じていても、その歪みはいずれ別の形で表出します。わが子を厳しくしつけることばかりに目を向けずに、時には「できなくても、まあいいか」とおおらかな気持ちで接することも大切です。

適度な厳しさがもたらす “よい影響”
親のしつけが「厳しすぎる」場合には注意が必要ですが、一方で適度な厳しさが子どもによい影響を与えることも。厳しいしつけのもとで「やるべきことをきちんとやる」習慣が身についた子は、学習や仕事においても粘り強く、責任感のある態度をとれる傾向があります。
たとえば「打たれ強さ」や「まじめさ・几帳面さ」。このふたつは、親が適度に厳しさをもって子どもに接してこそ育まれる要素だといえるでしょう。
ライフコーチのボーク重子氏は、「親が子どもに課題や挑戦を与えること自体は悪いことではなく、そのなかで『失敗してもいい』という姿勢を見せることで、子どもは回復力(レジリエンス)を育む」と語っています。つまり、ある程度の負荷がかかる環境であっても、親が見守りながら挑戦させることで、子どもは困難に直面しても諦めない心を養っていけるのです。
また、児童心理学の専門家である森下正康氏は、「幼児期における『自己抑制(=我慢する力、感情や衝動をコントロールする力)』の発達は、思いやりや攻撃性の抑制といった社会的スキルの基盤となる」と述べています。このことからも、幼児期に欲求を我慢する経験や根気強さを鍛えることは、将来的な自己制御力や自己管理能力の発達にも寄与していることがわかります。
もちろん、こうした特性が発揮されるためには、子どもが過度なストレスを感じない環境づくりを前提としなければなりません。厳しさと愛情のバランスが取れていれば、子どもはしっかりと現実に向き合い、社会に適応していく力を身につけていけるでしょう。
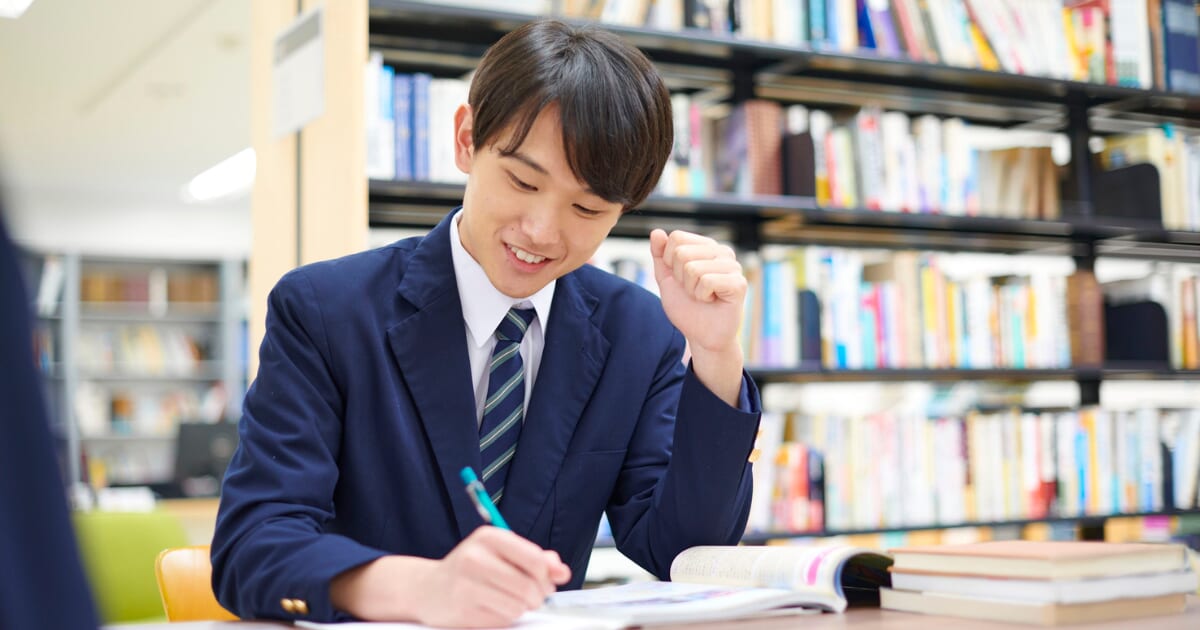
親子でつらいと感じたときの対処法|親も子もラクになるために
「本当は厳しくしたくないのに、まわりの目を気にしてしまう」「子どもが自分に対して萎縮しているように感じる」「厳しさとおおらかさのちょうどよいバランスで子育てしたい」など、わが子への対応にお悩みなら、ぜひ次の対処法を参考にしてください。
対処法1:子どもに完璧を求めすぎない
「子どもを叱らずに自分で考えられる力を育ててあげたほうが、子ども自身の生き抜く力も伸びていく」と村中氏が指摘するように、子どもの将来のためを思うなら、口出しするのをぐっと堪えることも時には必要です。
たとえば宿題を「やる・やらない」で叱りたくなった場合、とっさに「早く宿題しなさい!」と言えば親はスッキリするでしょう。しかし、「本当にいま、このタイミングで宿題を終わらせないとだめなのか」「この年齢の子に対して、そこまで完璧にできることを求めるのは妥当なのか」といったん立ち止まることで、子どもが自主的に課題に取り組む力を育めるのです。
対処法2:「自分の人生の中心は自分」であることを忘れない
『自分で考えて学ぶ子に育つ声かけの正解』(ダイヤモンド社)の著者でベネッセ教育総合研究所主任研究員の庄子寛之氏は、「子どもをコントロールしようとしないことが大事」と述べたうえで、「まず親がゆとりをもち、子どものことばかり考えず、自分の人生を楽しむために何をすべきか考える」ことをすすめています。
たとえば、おいしいものを食べたりショッピングをしたり、趣味を楽しんだりと、“自分の人生を豊かにする大事な要素のひとつに子育てがある“くらいの考えに変えると、ぐっとラクになりますよ。
対処法3:「叱るタイミング」を変えればスムーズに伝わる
先述したように、叱られているときの子どもの脳は「防御モード」になり、理解力が低下するため、一生懸命伝えても子ども自身にはいまいち届いていないことも。村中氏は、本当に子どもに伝えたいなら、何も起きていない「平時」に伝えることをおすすめしています。お互いに落ち着いた状態で丁寧に伝えることで、子どもは自分で「どう行動したらいいか」を冷静に考えられるようになるのだそう。
また植木氏は、食事中に食事マナーを注意するのは「心理的にマイナスが大きい」と指摘します。食事によって得られるのは、栄養だけでなく「リラックス効果」も高いため、注意ばかりされていると、同じ食事内容でも消化機能が落ちて栄養摂取効果が下がるという研究結果も。マナーやお行儀は、食事の時間以外のときにしっかり教えてあげることをおすすめします。
対処法4:信頼できる人や機関に相談する
子どもへの怒りやイライラの原因として「まわりの子と比べてわが子が劣っているような気がする “不安” や、自分ばかりが家事や育児をしているといったパートナーへの “不満” が要因になっていることもある」と指摘するのは、『感情的にならない子育て』(かんき出版)の著者で子育てアドバイザーの高祖常子氏。それだけでなく、疲れや睡眠不足など体の不調もイライラの原因として考えられます。
それらの原因を解消するために、支援センターやスクールカウンセラーに相談したり、パートナーと具体的な生活のスタイルについて話し合ったりするのも選択肢のひとつです。自分ひとりで無理してこなすのではなく、一時預かりやファミリーサポートも積極的に利用しましょう。親自身の心の余裕が、子どもとの向き合い方に変化をもたらしてくれるはずです。
***
親のしつけが厳しすぎると、子どもの心にはさまざまな影響を及ぼす可能性があります。一方で、適度な厳しさは子どもの社会性や粘り強さを育むもの。本記事を参考に、厳しさと愛情のバランスを見つめ直し、親子がともに心地よく過ごせる関係を築いていきましょう!
(参考)
講談社コクリコ|しつけ・指導「叱らず」やる方法 臨床心理士に聞く
講談社コクリコ|「叱っても意味がない」子どもを叱り続けるリスクを専門家が解説
プレジデントウーマン|しかれば叱るほど学びと成長が遠ざかる…夏休みの親必読「子どもを叱っても誰も得しない」脳科学的根拠
PHP研究所 nobico|子どもを厳しく叱る必要ってあるの?児童精神科医が出した答え
早稲田メンタルクリニック|親に厳しく育てられた人がなぜ自己肯定感が低いのか?「べき思考(白黒思考)」になりやすいのか?
ダイヤモンドオンライン|子どもに「しつけ」をしすぎていませんか?
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|子どもが親の失敗から学ぶもの。「やり抜く力」を育むなら“格好悪い親”であれ
幼児期における基本的情緒形成とその障害に関する研究|幼児期の自己制御機能の発達ー幼稚園での子どもの特徴と親子関係ー
ダイヤモンドオンライン|子どもがすぐ感情的になり、言うことを聞かない。どうすれば?
マイナビ子育て|厳しいしつけや叩くことから卒業を!親子で安心できる我が家を作るためにできること|高祖常子さんインタビュー 前編