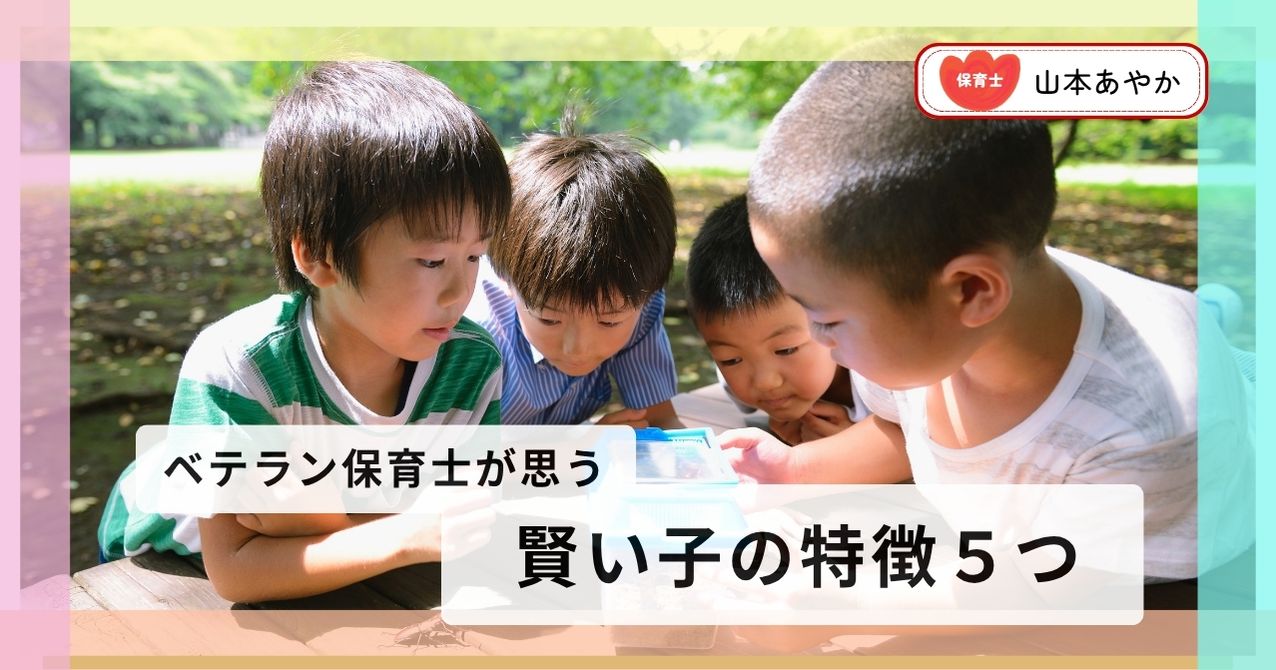「将来有望な子」や「賢い子」といえば、どのような子どものことを想像しますか? じつは、小さいうちから文字や数字を覚えたり、わがままを言わず素直に大人の言うことを聞いたりする子どもが必ずしも賢い子というわけではありません。
大切なわが子には、将来有望な子になってほしいもの。保育園に通う乳幼児期は、のちにつながる学習意欲を育む時期でもあります。さまざまな物事に興味・関心をもち、いかに視野を広くもてるかどうかが将来性につながるのです。
今回は、保育士歴10年の筆者が、保育室での何気ないやりとりを通して保育士が感じる賢い子の特徴について5つまとめました。親として、子供の将来のためにできることもお伝えしますのでチェックしてみてくださいね。
ライタープロフィール
保育士
児童学科で4年間学び、保育士資格や幼稚園教諭一種免許を取得。保育士として約10年勤務。現在、小学生2人を育てながら「働きながら子育てする大変さ」と対峙中。ワーキングマザーが安心して子どもを預けられるよう、さまざまな情報を発信します。
目次
賢い子1. 活動のなかで自分なりの気づきをもてる
保育活動のなかで、保育士は子どもたちにさまざまな声かけを行ないます。しかし、賢いと思う子どもは、声をかけるまえに自分なりの気づきをもつことができます。
- お散歩中に「きのうよりもさむいね」と気づく
- 薄い色を見て「おはなにげんきがないね」と言う
- おもちゃが足りないときに「これをかわりにしよう」と考える
🏠子どもの「気づき」を大切に:
日常のなかでの不思議に気づき、「なぜ?」「どうして?」の疑問が多くなるほど学びが深まります。自然に周囲に目を向けられる子どももいますが、大人が好奇心をくすぐる問いかけをするのもおすすめです。
- 季節を感じられる食べ物を食べる
- 野菜や果物を切り断面を見せる
- 棒でいろんなものを叩いて音の違いを聞く
- 種から植物を育てる
- あいさつをしながら近所を無目的にお散歩する
最初から答えを導き出すのではなく、子どもが自分で気づけるよう促すことも大切です。「信号にはいろんな色があるね」など、目線を誘導させる声かけだけでOK。そこから子どもがあちこちにある信号を見つけたり、色が変わったりすることに自分で気づくようになります。

賢い子2. お友だちの気持ちを思いやることができる
思いやりの心は、誰かが教えて習得できるものではありません。小さなうちからそのような素振りが見られる子どもは、あきらかに将来有望な子と呼べるのではないでしょうか。
- 泣いているお友だちに自然に声をかけられる
- 顔色が悪いお友だちにすぐに気づく
- お友だちに困ったことがあったときにいっしょに解決策を考える
🏠「感じる」ことで心を育てる:
子どもは五感でさまざまなことを感じながら、豊かな心を育んでいきます。思いやりや気遣いなどができる将来性には、心のゆとりが欠かせません。時間に追われることなく、自由遊びやぼんやりできる時間を多く設けるなど、子どもの心が動く余裕をもつことが大切です。
- 遊具のない広場で観察や探索を楽しむ
- さまざまな廃材を使って自由に工作を楽しむ
- 本物のガラスコップを使ってお茶を飲む
- たまごを自分で割り優しい持ち方を知る
- 動物と触れ合う機会をもち命の尊さを学ぶ
絵本を読みきかせたり、多くのリズムやメロディに触れたりする経験も子どもの知性を育みます。何より大切なのは、子どもが「楽しい」と感じられる体験を積み重ねることです。

賢い子3. 「なぜ」が口癖で知りたがる姿勢がある
新しいことや疑問に思ったことに対して「知りたい」という好奇心や学びの意欲をもっている将来有望な子は、就学後の学習能力に大きな伸びが見られます。
- 「なんで葉っぱは落ちてきちゃうの」と季節の事象に疑問をもつ
- 「どうして夜になると暗くなるの?」と日常のなかで疑問をもつ
- 「クレヨン誰かに食べられた!?」とものの増減に注目する
🏠疑問や興味を大切に育てる:
「なぜ?」「どうして?」という疑問を受け止め、一緒に考える時間をつくることが重要です。すぐに答えを教えるのではなく、子どもと一緒に考えたり調べたりする過程を楽しみましょう。
- 図鑑や本を一緒に見て答えを探す
- 「なんでだろうね?」と一緒に考える時間をつくる
- 実験や観察を通して答えを見つける
- 子どもの疑問をメモして後で調べる
- 「すごい疑問だね!」と子どもの好奇心を認める
すぐに答えを教えたくなりますが、一緒に考えたり調べたりする過程こそが子どもの成長につながります。正解を知ることよりも、疑問をもち続ける気持ちを大切にしてあげてください。

賢い子4. いろいろなことをつなげて考えられる
生活で起こるさまざまな出来事には、あちこちにつながりがあります。そのような視点に気づき、表現できることも将来性の特徴といえるでしょう。
- 絵本を見て「もし私だったら〇〇するかな~」と主人公と置き換えて考える
- 前日の遊びの経験を活かし、翌日の遊びをさらに発展させる
- さまざまな素材を見て「これは固いから〇〇に使えるね」とアイディアがひらめく
🏠関連性を見つける力を育てる:
日常の出来事や体験を関連付けて話すことで、論理的思考力を育むことができます。子どもが経験したことと新しい発見をつなげる声かけを心がけましょう。
- 「昨日の〇〇と似てるね」と関連性を指摘する
- 「もしも」の話を一緒に楽しむ
- 料理や工作で材料の特性を話し合う
- 絵本の登場人物の気持ちを想像して話す
- 季節の変化と生活の変化を関連付けて話す
このような会話を重ねることで、子どもは物事の因果関係や共通点を見つける力が自然と身についていきます。急がずに子どものペースに合わせて、楽しみながら取り組むことが大切です。

賢い子5. 好きなことに集中できる
夢中になる時間は、子どもを成長させる大きな鍵になります。その集中時間を誰かがお膳立てするのではなく、自ら集中ができる将来有望な子どもは伸びしろいっぱいです。
- パズルを完成させるまで、ほかのことには目もくれず集中し続ける
- 納得のいかなかった製作を翌日も続けて行なう
- アリがどこから来てどこへ行くのかじっと観察を続ける
🏠「考える時間」を十分に確保する:
自分で十分に考え、試行錯誤することで思考力や集中力を身につけられます。大人からのサポートが手厚すぎると、このような力はなかなか身につきません。忙しい日々のなか「子どもに任せる」「子どもなりの答えが出るまで待つ」というのはなかなか難しいものですが、時間と心に余裕があるときはぜひ意識してみてくださいね。
- ブロックが崩れないようにするにはどうしたらいいかな?
- どうすればお片づけの箱に全部入るかな?
- どう持ったらうまくコップにお茶を注げるかな?
- なかなかボタンが留められないのはどうしてかな?
- この絵は何を使って描こうかな?
過干渉を控えて見守ることは、本当に難しいことです。介入しすぎず見守る場面を意識的につくることで、子どもの将来性につながるチャンスをつくれます。集中しているときはそっと見守ることに徹する。自分でできる力を尊重することが成功体験につながり、もっと難しいことに挑戦しようとする力をつけられます。

要注意! 親が勘違いしがちな「将来性」のサイン
知識や学力だけでなく、人間性や行動の面でも「将来性」は表れます。しかし、将来有望な子というと「頭のよさ」だけをイメージしがち。そこで注意したいのが、将来性への過度な期待と勘違いです。
その時期だけの能力だけでなく「将来に良い影響が持続される力」が身につくよう、注意すべき将来性をチェックしてみましょう。
勘違い1. 文字・数字を習得できた
2~3歳のうちに数字やひらがなを理解したり、名前を漢字で書けたりすると、やはり「すごい!」と思いますよね。子どもの努力も認めてあげるべきではありますが、文字・数字の習得は、いずれ段階を踏んで学ぶ機会が設けられているもの。そこに固執してしまうと、子どもの成長や個性を見逃してしまう可能性があるため注意が必要です。
勘違い2. 暗記している知識が豊富
国旗や電車、虫の種類などに詳しく、多くの知識をもちあわせている子どもはすばらしいですよね。しかし、暗記できたことや知識が多いことに対してのみ注目してほめると、意味を理解しようとせず手当たり次第に暗記するようになってしまいます。このような子どもの賢さは、知識そのものではなく「好きなものを知ろうとする探究心や集中力」です。
勘違い3. 難しい言葉を使って会話する
大人と同じような言葉を使って表面的な模倣を行なうことよりも、言葉の意味をしっかり理解することや、状況により使い分けることがなにより重要です。また、自分の考えや気持ちを言葉で伝えられることも将来性のひとつ。難しい言葉を使っているかどうかよりも、正しいタイミングで正しい言葉を使えるかどうかに注目したいですね。
勘違い4. なんでも人よりも早くこなせる
いつもまわりの子どもよりもなんでも早くできると、必然的にすごいと認識される傾向があります。しかし、自分のペースで物事を深く考えたり、試行錯誤しながら集中して取り組む力こそが真の賢さにつながっていきます。要領がよいことと将来性は分けて考えられるとよいでしょう。
勘違い5. 大人の言うことを聞ける
なかでも注意したいのが、大人の言うことをおとなしく聞ける子どもが将来有望だという勘違いです。大人を困らせることがないだけで将来有望だと感じてしまうのは、とても危険です。指示に従うことや失敗しないことではなく、本当の将来性につながる好奇心や問題解決能力を育てられるようにすることが大切です。
***
乳幼児期に見られる「勉強ができる!」という賢さは、一時的なものに過ぎません。年齢を重ねるごとに周囲との差がなくなり、それだけでなく「以前は誰よりもできていたのに」という劣等感を覚えてしまう可能性があります。
子どもの将来性や知性を育むためには、ただ知識を与えるだけでなく子ども自身が「気づき」「考え」「感じる」環境をつくることが大切です。子どもはスポンジのようにさまざまなことを吸収します。のちの学びを大きく広げられるよう、子どもの好奇心を大切にしてあげたいですね。