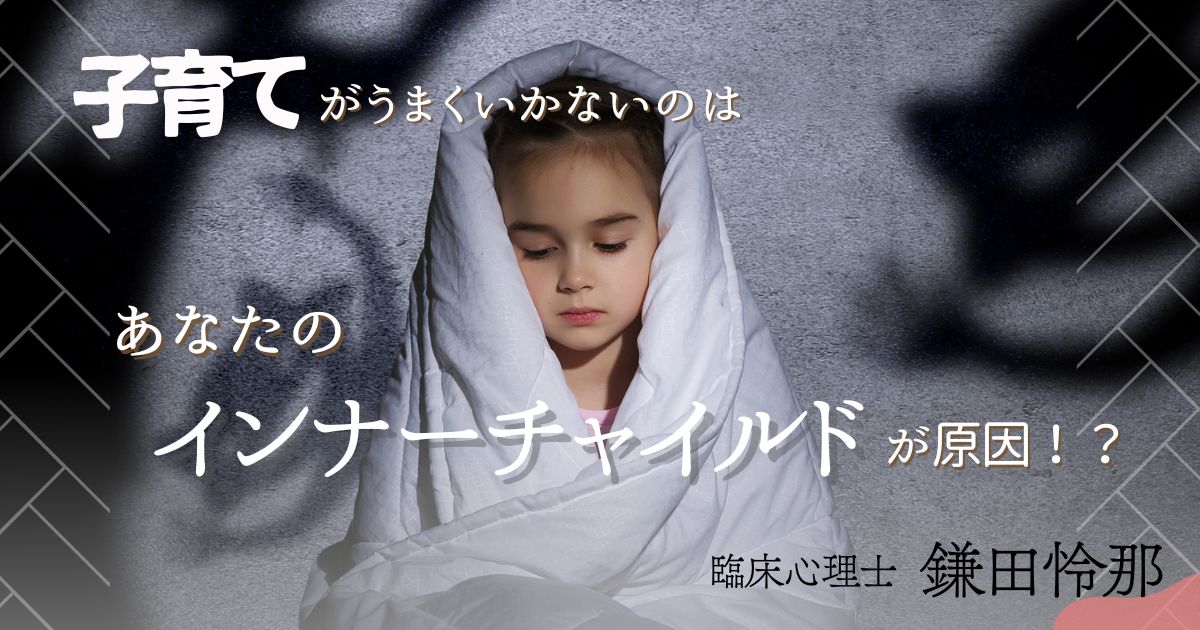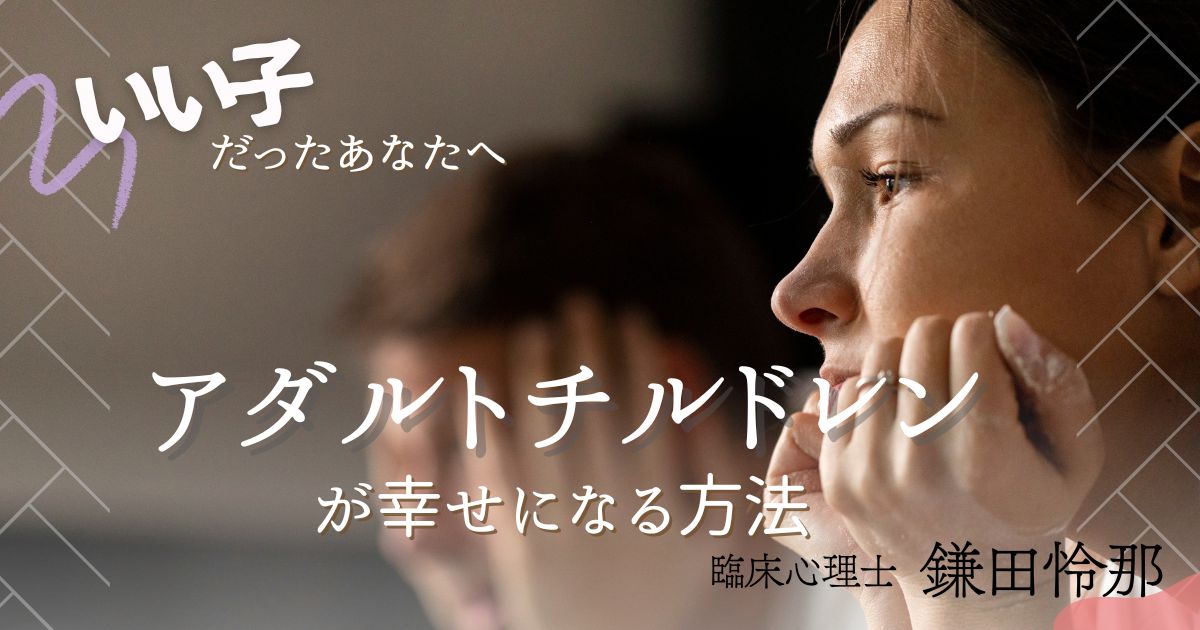「子どもが言うことを聞かないだけで、なぜこんなにイライラするんだろう」
「子どもの泣き声を聞くと、胸の奥がざわざわして落ち着かない」
「『もう知らない!』と言って部屋を出てしまい、あとで罪悪感でいっぱいになる」
こうした体験は、多くの親が抱える共通の悩みでもあります。SNSで見かける「理想の親」と自分を比べて、「私って最低な母親かも」「なんでこんなに感情的になってしまうんだろう」と自分を責めてしまう方も少なくありません。
でもじつは、こうした感情の嵐には理由があります。それは、あなたの心の奥に住む「小さなあなた——インナーチャイルド」が関係している可能性があるのです。この小さなあなたは、まだ癒されていない傷を抱えたまま、いまのあなたの子育てに影響を与えているのかもしれません。
今回は、なぜ子育てで感情的になってしまうのか、その背景にある「インナーチャイルドの正体」と、具体的な「インナーチャイルドの癒し方」について、臨床心理士・鎌田怜那氏の監修のもとお伝えします。
ライタープロフィール
臨床心理士・公認心理師
子どもの発達・アタッチメントの専門家。子どもの強みを見つけ、親子関係を豊かにするサポートしています。自身も3児の子育て中。専門家であっても、子育てでイライラやモヤモヤは避けられず……母親であることを楽しめるよう、心理学の知識を日常生活に活かすスキルを発見・実践しています。子育ての悩みを「悩める幸せ」として、共に成長しましょう!
目次
インナーチャイルドって何? なぜ子育てで苦しくなるの?
あなたのなかに住む「小さなあなた」
インナーチャイルドとは、私たちの心のなかにいまも生き続けている「子どもの頃の自分」のことです。特に、幼い頃に十分に愛されなかった部分、理解されなかった気持ち、我慢を強いられた想いが、大人になったいまでもあなたの心の奥で静かに影響を与え続けています。
インナーチャイルドには健全な側面と傷ついた側面があります。健全なインナーチャイルドは、好奇心や創造性、素直な感情表現など、大人になっても私たちの生活を豊かにしてくれる特性です。一方、傷ついたインナーチャイルドは、幼少期の否定的な体験によって形成され、現在の生きづらさや子育ての困難に関係しています。
たとえば、こんな経験はありませんか?
- 子どもが「ママ見て見て!」と言うとき、なぜかイライラしてしまう
- 子どもが甘えてくると「ひとりでやりなさい」と突き放したくなる
- 子どもが失敗すると、必要以上に心配になったり怒ったりする
これらの反応は、いま目の前にいるお子さんへの反応というより、あなたのなかの「小さなあなた」が反応している可能性があります。

なぜ子育てでインナーチャイルドが騒ぎ出すの?
子育ては、私たちが子どもだった頃の記憶を呼び覚ます体験の連続です。お子さんの姿に、昔の自分を重ね合わせることで、封印していた感情が蘇ってくるのです
自分の無意識の感情や欲求を他者に投影する「投影」という防衛機制があり、また人間には幼少期の関係パターンを無意識に繰り返す傾向があります。
よくあるパターン:
- 子どもが泣くと「泣くんじゃない!」と言いたくなる
→ あなた自身が泣くことを許されなかった経験 - 子どもがだらだらしていると異常にイライラする
→ 「ちゃんとしなさい」と言われ続けた子ども時代 - 子どもの成績が気になって仕方ない
→ 親に認められるために頑張り続けた過去
これは決して自分を責めるべきことではありません。ただ、過去の経験が現在の反応に影響している、ということを理解することが大切なのです。

あなたのインナーチャイルドのタイプは?
子育ての場面でよく現れるインナーチャイルドの傷ついた側面7つのタイプをご紹介します。あなたはどのタイプに当てはまりますか?
1. ケアテイカー(世話役)
このタイプは、幼い頃から家族の世話をする役割を担ってきた人に多く見られます。親が病気がちだったり精神的に不安定で、子どもながらに親の面倒を見なければならなかった経験や、「お兄ちゃん/お姉ちゃんなんだから」と弟妹の世話を任され、自分のニーズより家族のニーズが常に優先される環境で育った結果として形成されます。また、家族の愚痴を聞く相談役のような立場に置かれることで、他者の感情的なケアを担う習慣が身についてしまうのです。
- 他人のニーズを自分より優先してしまう
- 子どもや家族の世話を完璧にしようとする
- とても寛容で、愛情で全てを解決しようとする
- 大切なものを奪われると激しい怒りを感じる
子育てでの現れ方:「私が全部やってあげなきゃ」とひとりで抱え込みがちになります。子どもが困っていると、本人が学ぶ機会を奪ってでも手を出してしまったり、家族のために自分の時間や体調を犠牲にしてしまうことがよくあります。
2. オーバーアチーバー(頑張りすぎる人)
このタイプの背景には、条件付きの愛情で育った経験があります。成績や成果でしかほめられず、「○○ちゃんの方が上手」と常に他の子と比較され、失敗すると愛情を引っ込められるような環境で育ちました。「いい子なら愛してあげる」「頑張った時だけ認めてあげる」といった条件付きの愛情しか受けられなかったため、成果を出すことでしか自分の価値や愛情を感じられなくなってしまったのです。
- 自分にも子どもにも高い期待を持つ
- 成功や成果を通して愛されようとする
- 外からの評価を強く求める
- 平凡さや怠惰に我慢できない
子育てでの現れ方:子どもの成績や習い事の成果が気になりすぎる傾向があります。他の子と比較して「うちの子は大丈夫かしら」と心配になったり、子どもが失敗すると自分が失敗したような気持ちになってしまうことがあります。
3. アンダーアチーバー(自信のない人)
このタイプは、幼少期に自信を徹底的に奪われる経験を重ねてきています。「ダメな子」「何をやってもうまくいかない」と言われ続け、挑戦するまえから「どうせできない」と決めつけられたり、兄弟姉妹と比較されて劣等感を植え付けられました。失敗を厳しく責められることで挑戦する意欲を奪われ、何もしなければ失敗もしないという回避的な対処を身につけてしまったのです。
- 自己価値が低く、自分の能力を信じられない
- リスクを取るのが怖い
- 批判を避けるために小さくなっていようとする
- 目標を立てても達成が困難
子育てでの現れ方:「私なんかが子育てできるのかな」と常に不安を感じています。他のママたちと比べて自分はダメだと思い込んだり、子どもに何かを教えるときも「私が教えて大丈夫かな」と自信がもてないことがよくあります。
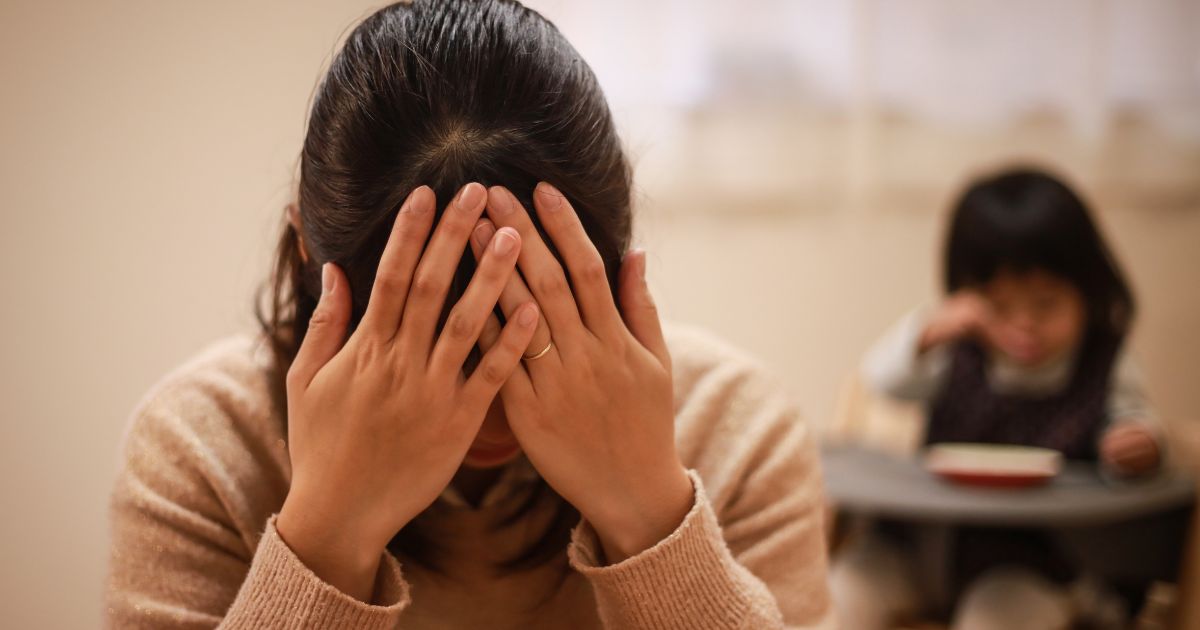
4. レスキュアー(救世主)
このタイプは、家族の問題を子どもなりに解決しようとしてきた経験から形成されます。両親の喧嘩や経済的困窮など、家族の抱える問題に対して「あなたがいないとダメ」と過度に頼られたり、自分が犠牲になることで家族の平和を保った経験を重ねています。弱い立場の人を守ることで自分の価値を感じるよう学習し、助けることでしか愛情や承認を得られないと信じるようになったのです。
- 強い正義感を持っている
- 周りの人を助けることで自分の価値を感じる
- 他者を「助けが必要な人」として見がち
- 殉教者的な態度を取ることがある
子育てでの現れ方:子どもの問題を全て解決してあげようとする傾向があります。子どもが友達とトラブルになったり、学校で困ったことがあると、すぐに親が出て行って解決しようとしたり、子どもの代わりに謝ったりしてしまうことがあります。
5. ライフオブザパーティー(ムードメーカー)
このタイプは、家庭の重い雰囲気を明るくしなければならないと感じて育った人に見られます。感情を表現すると「そんなことで」と否定されたり、悲しみや怒りを表現することが許されない環境で、おどけることで注目や愛情を得る経験を重ねてきました。本来の感情を押し殺し、常に明るくふるまうことで家族の機嫌をとり、愛情を確保する戦略を身につけたのです。
- いつも明るく、新しいことに挑戦したがる
- 社交的で、みんなを楽しませようとする
- 痛みや悲しみを見せないよう隠す
- 周りを幸せにすることで愛を得ようとする
子育てでの現れ方:家庭を常に明るく保とうとして、自分の疲れや悩みを隠してしまいます。子どもの前では絶対に泣かない、いつも笑顔でいなければと思い込んで、本当はしんどいのに「大丈夫、大丈夫」と言い続けてしまうことがあります。
6. イエスパーソン(断れない人)
このタイプは、幼少期に自分の意見や感情を表現することが許されない環境で育った経験から形成されます。「わがまま」と言われることへの恐れや、他者を失望させることへの強い不安を抱えている人も。従順であることでしか愛情や承認を得られないと学習してしまった結果、自分のニーズを後回しにする習慣が身についていまったのです。
- いつも他人を喜ばせようとする
- 対立や衝突を避けたがる
- 「NO」と言うと罪悪感や恥を感じる
- 自己犠牲が美徳だと信じている
子育てでの現れ方:ママ友の頼みを断れず、自分が疲弊してしまいがち。子どもの要求に対しても「ダメ」と言うことに罪悪感を感じ、適切な境界線を設けられないため、子どもに振り回されてしまいます。夫婦間では役割分担の話し合いができず、対立を避けるあまりひとりで抱え込んでしまい、負担が偏ってしまうことがよくあります。
7. ヒーローワーシッパー(崇拝者)
このタイプは、「いい子」であることでしか愛されなかった経験から形成されます。自分の意見を言うと怒られたり無視されたり、「わがまま」と言われることを極度に恐れるようになりました。従順であることが唯一の生き残り戦略となり、自分の気持ちや意見を押し殺してでも他者を喜ばせることで、関係性を維持しようとする習慣が身についてしまったのです。
- 権威のある人や完璧な人を理想化する
- 「完璧な親」の模範を常に探している
- 自分を犠牲にすることでしか愛されないと思っている
- 他人をお手本にして生き方を決めたがる
子育てでの現れ方:「○○さんみたいな完璧なママになりたい」と自分を追い込んでしまいます。SNSで見かける素敵なママや、育児書に書かれている理想の母親像と自分を比べて、「私はダメな母親だ」と落ち込んだり、完璧を目指して疲れ果ててしまうことがあります。

ひとりの人のなかに複数のタイプが存在することがあります。また、ときと場合によって異なるタイプが現れることもあります。これは矛盾ではなく、それぞれの環境で身につけた生き残り戦略が使い分けられているのです。
アダルトチルドレンとの関連性
インナーチャイルドと密接に関連する概念としてアダルトチルドレンがあります。機能不全家族で育った人が大人になっても抱える心の傷や行動パターンを指し、インナーチャイルドケアと合わせて理解することで、より深い自己理解につながります。
子育てに現れるインナーチャイルドの影響
ケース1:過干渉になってしまうAさん
ケース2:感情的になってしまうBさん
よく考えてみると、私の子ども時代って、両親が共働きでとても忙しくて。『静かにしていなさい』『いい子にしていなさい』ってよく言われていました。泣いたり騒いだりすると、すごく嫌な顔をされたんです。なんでこの子たちは自由にできるの?』っていう、ちょっと羨ましいような複雑な気持ちも混じって、つい強く反応してしまうのかもしれません」(4歳と2歳の男の子ママ)
ケース3:他のママと比較してしまうCさん
じつは子どもの頃、私自身『○○ちゃんのお母さんがよかった』『○○ちゃんの家に生まれたかった』いう感情がありました。自分の家はいつも散らかってて、母も暴言がひどく……。いまでもその比べる癖が抜けてないのかもしれないし、そんな同じ思いを子どもにさせたくないと無意識に思っているのかもしれません。」(5歳男の子ママ)
インナーチャイルドを理解することで、感情的な反応が起きたときに「これは過去の記憶による反応かもしれない」と気づけるようになります。では、日常的に実践できる方法をご紹介します。

インナーチャイルドを理解して癒す方法
インナーチャイルドとの向き合いは、一度きりではなく継続的なプロセスです。日常のなかで徐々に癒していく段階的なアプローチをご紹介します。
ステップ1:気づく(観察と認識)
子どもに対してイライラしたり、不安になったりしたとき、まずはその場で一度立ち止まって感情を観察しましょう。感情は悪いものではなく、あなたのインナーチャイルドからの大切なメッセージです。その瞬間に自分自身に問いかけてみてください:
「体のどの部分に緊張や不快感がある?」
「この反応の強さは、いまの状況に見合っている?」
同じような場面で繰り返し強い感情が湧く場合、そこにインナーチャイルドからのメッセージが隠れています。たとえば、子どもが宿題をやらずにだらだらしているのを見て異常にイライラした場合、「私自身が子どもの頃、『ちゃんとしなさい』と言われ続けていたなあ」という気づきがあるかもしれません。
ステップ2:向き合う(ジャーナリングによる深い対話)
気づきが生まれたら、ジャーナリング(書く療法)でインナーチャイルドと深く向き合います。インナーチャイルドケアとしても有効です。まず、感情をそのまま書き出してみましょう:
子どもが宿題をしないのを見て、胸がざわざわした。
なぜこんなに反応するんだろう?
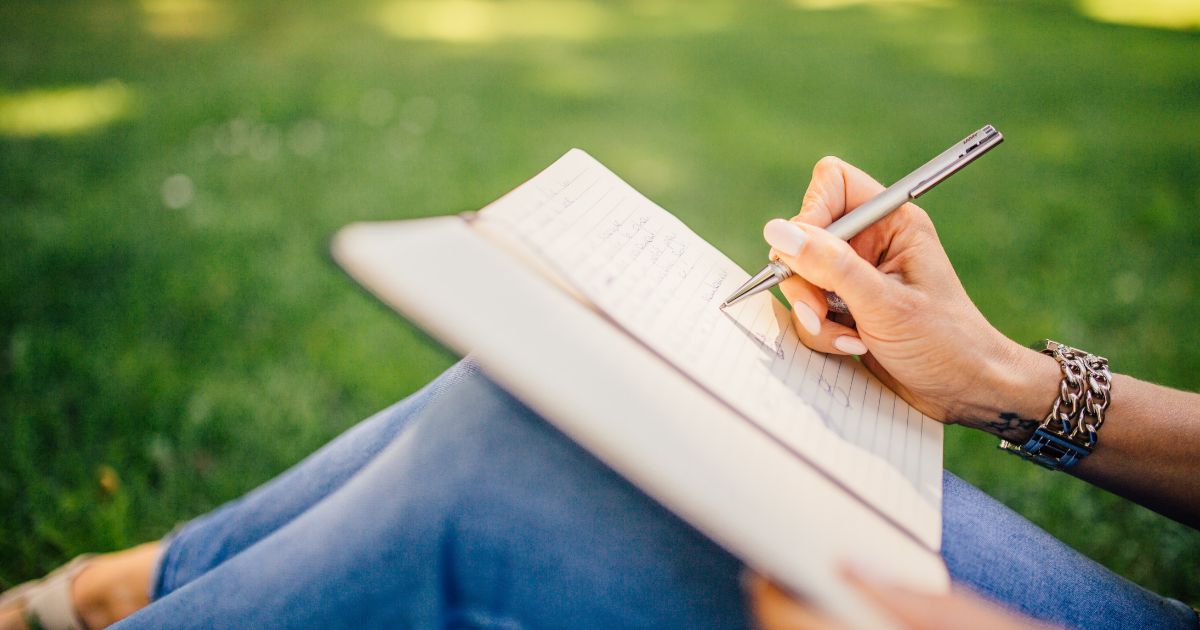
ステップ3:受け入れる
ジャーナリングを通して気づいた感情や過去の体験を、否定せずに受け入れます。「イライラしちゃダメ」ではなく「いま、イライラしているんだな」と、ただ感情を認めることから始めましょう。「こんな風に感じるのも当然だった」「過去のつらい経験がいまも影響しているのは自然なこと」と、自分を責めずに理解してあげることが大切です。
「あなたの気持ちはとても大切」
「いまはもう安全だよ」
週に一度、その週で感じた強い感情を振り返り、子ども時代の自分に「あの時は辛かったね、でも十分頑張っていたよ」と優しい言葉をかけてあげる時間を作ってみてはいかがでしょうか。この習慣により、自分の感情パターンを理解し、より穏やかな子育てができるようになるかもしれません。
ステップ4:行動を変える
理解と受容を基盤に、実際の子育ての場面で新しい反応パターンを少しずつ身につけます。たとえば、子どもが宿題をしない場面で、以前なら「なんでやらないの!」と感情的に怒っていたのを、一呼吸置いて「宿題、一緒にやってみる?」と声をかけるように変えていくのです。
感情的になってしまった後の対処も重要です:
・自分の感情について年齢に応じて説明:「ママも人間だから、時々感情的になっちゃうの」
・一緒に解決策を考える:「今度はどうしたらいいかな?」
継続的な実践のために
完璧を目指さず、「今日は一度だけでも立ち止まれた」という小さな成功を認めることから始めてください。月に一度、自分の成長を振り返る時間を持つことで、変化を実感できるはずです。
パートナーや信頼できる友人とジャーナリングの内容を共有することで、より深い理解と癒しが得られます。ひとりで抱え込まずに、支えてくれる人と歩んでいくことが大切です。

周りの人との協力とサポート
子どもに手を上げてしまうことがある、自分をコントロールできない状態が続く、過去のトラウマが強く影響しているといった場合は、カウンセラーや心理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門的なサポートを受けることは恥ずかしいことではなく、自分と子どもを守るための大切な選択です。
***
自分のインナーチャイルドに気づき、向き合うことで、感情的になる場面が少しずつ減り、子育てに心の余裕が生まれます。また、自分が子どもの頃に経験した嫌なパターンを子どもに繰り返さずに済むようになるでしょう。
ただし、すぐに変われるものではありません。焦らずに少しずつ、自分のペースで向き合っていくことが大切です。感情的になってしまっても自分を責めずに、「今日は少し気づけた」「前より冷静になれた」と小さな変化を認めながら、子どもと一緒に成長していきましょう。