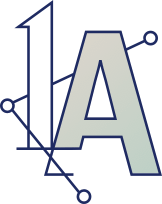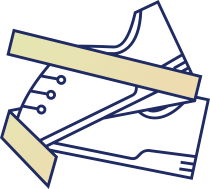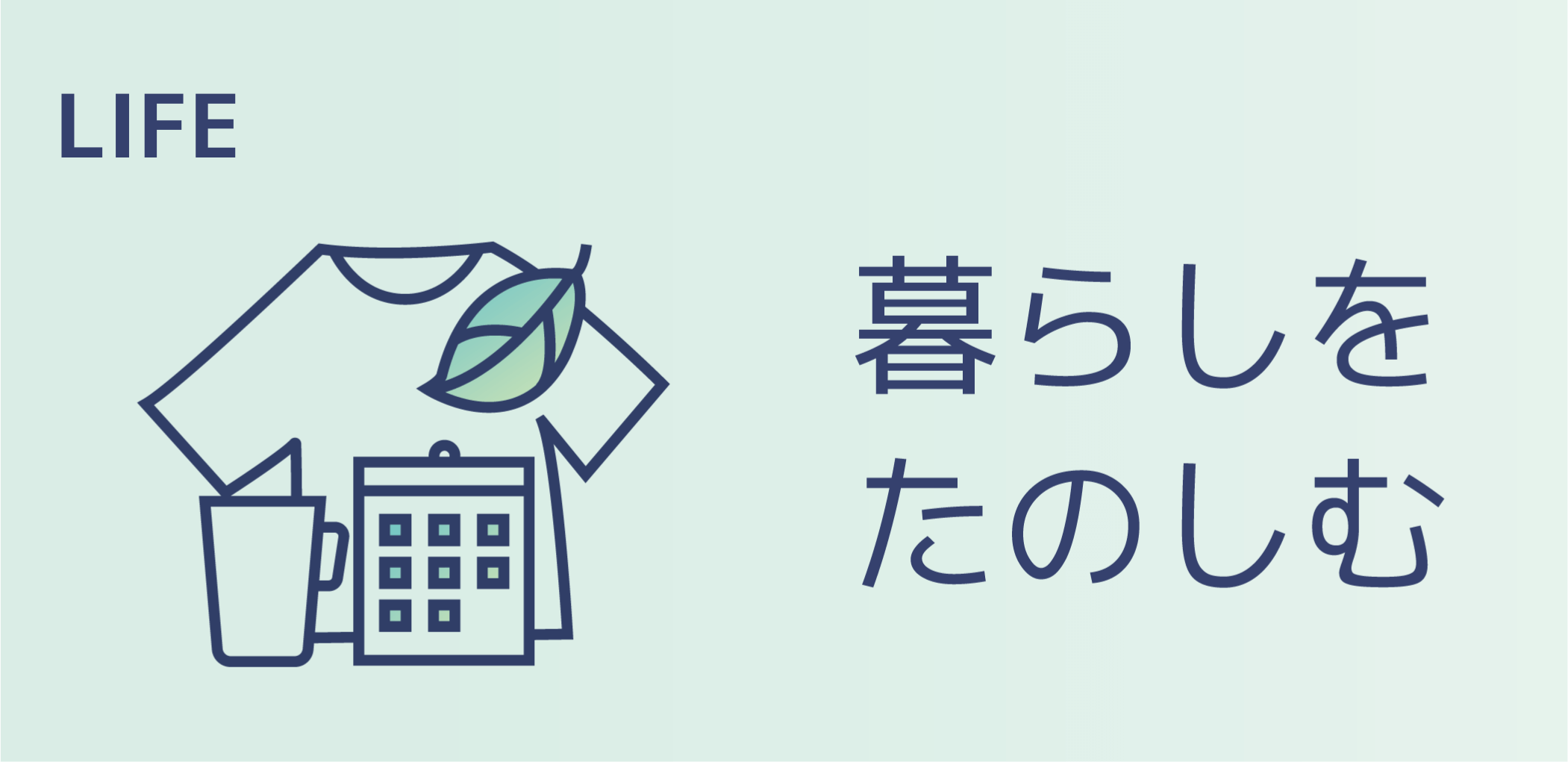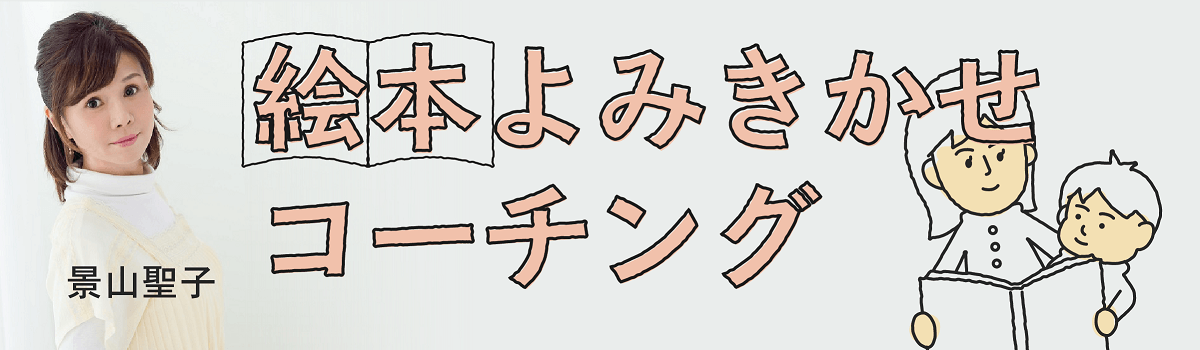熊さん
八っつあん
熊さん
八っつあん
熊さん
ご隠居さんではありませんが、
1970年代を通じて、イギリスロマン派詩人の研究者、EDハーシュはアメリカ、ヴァージニア大学で教鞭をとりました。英文学者としての教育研究に携わるハーシュは、あることに気づきます。
特に貧しい家庭的背景を持つ学生達は、英語ネイティブであるにもかかわらず、目の前の文章が読めないことがしばしばあったのです。また、そういった学生たちはエスニックマイノリティであることも多かったのです。
英語を読むために必要な能力は文法と単語だけではない。書かれた文章の背景にある文化や歴史をある程度知っていて初めて「読む」ことが可能になる、とハーシュは確信します。
ところが、こうした文化的な知識は、「分かっていて当然」「なんとなく知っている」とされていることが多く、系統立てて教えられないことが多いのです。
文化リテラシーとは、その文化に育った人間であれば、あまり学んだ覚えもないうちに知っていて、必ずしも説明することさえない一般的な前提を知っていること、とでも言いかえれば良いでしょうか。
ライタープロフィール
ケンブリッジ大学英文学博士
早稲田大学文学研究科英文学修士、英サセックス大学英文学修士、英ケンブリッジ大学英文学博士。早稲田大学アジア太平洋研究科講師、早稲田大学教育学部英語英文学科准教授を経て、現在は英リーズ大学で教鞭をとる。
専門はイギリス文化、文学だが、日本語英語両方のアカデミックライティングにも長年携わっており、英語のアカデミックライティングはイギリスでの教育経験もある。プライベートではバイリンガルの子供二人をイギリスで育てる母親。
著書にThe Pageant Fever(早稲田大学出版)共著『これから研究を書くひとのためのガイドブック』(ひつじ書房)など。
目次
冒頭の会話、ピンときましたか?
たとえば、冒頭の熊さんと八っつあんの会話は、現在50歳程度以上の日本の方であれば、おそらく違和感がなく「読める」はずです。
落語の世界の長屋に出てくる登場人物で、八っつあんと熊さんはあわてんぼうでそそっかしく、どこかピントがずれています。対する「ご隠居さん」は落ち着いた、物知りで色々と説明をしてくれる役回りです。
一体落語のどの演目にこの二人が出てくるのかは知らなくても、そこまでわかっていれば冒頭の文章を「読む」ことは簡単です。
「ははあ、これはこれから新しい概念の説明をしようとしているのだな。そのためのつかみ、というか、間抜けな質問をする役割としてこの二人が出てくるのだな」と、判断がつきます。(ということはそれほど重要ではないのだから、読み飛ばしていいのだな、という判断もつくわけです!)
逆にその程度の漠然とした知識がないと、今度は上の文章はどちらかというと混乱を招くものとなるはずです。
このコラムは小さなお子さんをお持ちのご両親に向けて書いていますから、「全くピンとこない」「なんとなく時代劇っぽいなとは思ったけど……」という方も多いかもしれませんね。背景知識が理解を変えてしまう例の一つです。

「文化リテラシー」論の是非
どうやら文化リテラシーは子供のうちに身につけたほうが良いらしい、と考えたハーシュは次のように結論付けます。
貧しい家庭や、マイノリティ家庭出身で、自然にアメリカでメインストリームとされる文化的な知識に触れることのない子供達には、こうした「知っていて当然」とされる知識を系統的に与えることが必要なのではないか。
ハーシュは1983年、自説を論文として発表し、続き1987年にベストセラーになったCultural Literacy: What Every American Needs to Know(邦題『教養が、国を作る』)を出版します。
アメリカ人が知っているべきことを巻末にリストアップしてあり、それを読むだけで「この程度のことを知らないと恥ずかしいのだな」と認識できるのも人気の理由の一つだったのかもしれません。
実際にはこの本はアメリカの小学校教育の制度を変えるべきだという議論の本であり、その議論には私は必ずしも賛成しません。
また、ハーシュの議論は2010年代からのイギリスの公教育のあり方に強く影を落としています。ハーシュが提唱したCore knowledge (中核となる知識)イギリス版を用いて教育を始めた小学校もあります。そして、導入にあたっては教育現場や教育学者からの批判も出ています。もちろん「効果が出た」とする声もあるのですが。
細かい議論にはここでは立ち入りませんが、反論の一つとして、「文化」というものが、必ずしも固定したものではなく変化し続けるものであることをあげておきます。先ほどの落語の例でもわかるように、一つの世代にとっては「自然な」知識が、下の世代にとっては「ピンとこない」ものになるような変化も自然と起きるでしょう。
また、一体誰が、何を「知っておくべき共通の文化的知識」とするのかにも、社会の中での力関係が強く働きます。ハーシュが文化リテラシーの概念を提唱した頃は、今まで英語圏で無視され続けてきた女性や、有色人種の作品群を再評価しようという動きの最中でした。ですから、固定化した「あるべき文化知識」を教えようとする(ように見える)ハーシュの議論は大きな反論を呼びました。そうした反論には非常に大きな説得力があります。
文化は受け継がれるだけではなく、私たちが主体的に作り上げていくものでもあるのですから。
幼少期の楽しい文学体験が将来国際社会を生き抜く力に
けれど、それでも、前提となる文化知識の欠如は「その文化の外部から入ってくる人たち」にとっては大きな障壁になります。
日本に生まれ育ち、日本の文脈の中でのみ育った人間にとっては当然日本流の文化リテラシーが身につくわけですが、それと英語圏での共通知識の間には、やはり差があります。
また、自分が自然と身につけた文化リテラシーのみを「当然のもの」としていても、おそらくいつか異なる社会や文化と向き合っていく上で、限界があるでしょう。
日本で生まれ育つ小さな人たちと英語圏の文化リテラシーとの関係について考えるときに私が思うのは、ハーシュの言うように「系統立てて教え込む」べきだ、ということではありません。
公教育で系統立てて教えようとすると、どうしてもテストによる評価が入ってくるでしょう。それが望ましいことなのかどうかは、教育学の専門の方の判断を待つべきだと思っています。
そうではなくて、小さな人たちが好奇心の赴くまま面白いお話にワクワクしているうちに、うっすらと「違う知識が必要な世界があるのだな」ということを感じていてもらえるといいな、ということなのです。
ですから、もともとは英語で書かれた詩や小説が、小さなお子さんをお持ちのご両親の本棚にあるといいな、と私は思っています。
「こうなるんだ、不思議だね」「おもしろいね」という会話が、いつか、成長したとき、ぱちり、とより複雑な知識の網にはまり込み、より大きな世界の文脈の理解の手助けになる日が、きっと来るだろうと信じているからです。
(参考)
E.D. Hirsch, Cultural Literacy: What Every American Needs to Know, Vintage Book Edition (New York: Random House, 1988)
エリック・ドナルド・ハーシュ(E.D. Hirsch), 中村保夫 訳(1989),『教養が、国を作る』, ティビーエス・ブリタニカ.