「IQや学力テストなどでは測れない、心の働きにかかわる能力」を意味する「非認知能力」の詳細な分類は研究者により大きく異なり、数十項目に及ぶとされる場合もあります。それら多種多様な能力のなかで、「非認知能力育成のパイオニア」と呼ばれるボーク重子さんが「とくに重要」と語るのが、「自制心」と「社会性」です。その重要性はどこにあるのか、子どもの自制心と社会性を育む方法と併せて解説してもらいます。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人(インタビューカットのみ)
目次
人生の幸せと成功に直結する「自制心」
いわゆる「非認知能力」の幅はとても広いのですが、私自身のなかでは、自己肯定感、自己効力感、自制心、主体性、柔軟性、共感力、社会性の7つに分類してとらえています。これらはいずれも大切な力ですが、とくに重要なものを挙げるなら、自制心と社会性になるでしょうか。
自制心とは、「自らの感情や欲望、衝動をコントロールし、理性的に行動する力」のことです。私は、自制心こそが、人生の幸せと成功に直結する非認知能力だと考えています。なぜなら、自制心は、「望ましい行動の習慣化」につながるからです。
自制心を広義の意味でとらえるなら、「未来を見通す能力」とも言えます。自制心が育っている子は、「いまこれをしないと、あとでまずいことになるからきちんとやろう」「いまこれをやったら、将来的にこんなメリットがある」というように考え、やるべきこと、やったほうが自分のためになることを自ら選ぶことができます。
勉強を例にとってみれば、本来もっている頭のよさが同じ子どもがふたりいるとして、勉強しなければならないときにそうできるのか、あるいはできないのかで将来的に大きなちがいが生まれることは明らかです。
加えて、自制心は「良好な人間関係構築」にも寄与します。ハーバード大学のある研究では、人間の幸福にもっとも貢献するものは良好な人間関係だと示されています。
では、そうしたいい人間関係を築くときに必要なものとはなんでしょうか? さまざまな要素があると思いますが、自制心もそのひとつであることは確かです。多様な個性をもつ他人とのかかわりのなか、誰だって感情的になることもあるでしょう。でも、「この場で感情的になるのはいけない」「言っていいことといけないことがある」といった自制心を働かせることで、人間関係をこじらせてしまうケースが大きく減るのです。

集団のなかで生きていく人間に不可欠な「社会性」
もうひとつの社会性は、「あらゆる集団のなかで自らをスムーズに機能させる力」のことで、これもまた、良好な人間関係の構築につながる力です。
とくに、「和の文化」をもち周囲との調和や協力を重んじる日本では、子どもに対する親の願いとして、「まわりに迷惑をかけない大人になってほしい」というものが、あらゆる調査において上位に入ってきます。
「まわりに迷惑をかけない大人になる」ということをもう少し深く考えると、「まわりの役に立てる大人になる」となります。これらは、人間が多くの他人とともに構成するコミュニティーで生活を営む社会的動物である以上、自然にもつ欲求と言えます。もっと言えば、人類の長い歴史のなかで刻まれた本能のようなものであり、私たちが誰かに「ありがとう」と言われるだけでも大きな喜びを感じるのはそのためです。
この社会性が欠けていると、他者との協調や譲り合いができない、相手の立場や気持ちを十分に理解することができないといったことから人間関係に大きな支障をきたし、社会的に孤立してしまうようなことにもなりかねません。
先に、人間は「そもそも社会的動物」だといいました。社会性に欠けていると、極端にいえば生きていくことが困難になってしまうでしょう。社会性の重要性は、ここにあるのです。

親同士が喧嘩する姿を子どもに見せるのはご法度
では、子どもの自制心と社会性を育むにはどうすればいいでしょうか。その答えは、いずれも「親が望ましい姿を見せる」ということに尽きます。
コロナ禍を経て在宅ワークを選択できる人も多いでしょう。そういう人であれば、たとえば決まった時間にテレビを消し、スマホを置いて必ず仕事を始めるといった姿を子どもに見せるのです。これは、他者の行動を観察して模倣することで学習するという心理学の概念である「モデリング効果」を活用して子どもの自制心を育む方法です。
子どもの立場から考えてみてください。ソファに寝転がってぼーっとスマホを眺めている親から「ちゃんと宿題しないと駄目だからね」なんて言われても、子どものやる気は湧いてくるはずがありません。親がいつも決まった時間に仕事をしている姿を見るからこそ、子どもは「遊びたいけれど、自分もきちんとしよう」と思い、自制心が伸びていくのです。
在宅ワークではない場合でも、たとえばジョギングなどの運動、読書や資格勉強、あるいは日常の家事などを決まった時間に必ずきちんと行なうという姿を見せることで、同様の効果が期待できます。
社会性を育む場合であれば、子どもが友だちと喧嘩をしてぶってしまったようなときに、叱り飛ばすなどはやはりよくありません。そうではなく、「どうしてそうしたの?」と子どもなりの言い分を聞いたうえで、「でも、ぶつのは絶対にやっちゃ駄目だからね」と、その行為が望ましいものではないことを繰り返し繰り返し諭すという手もあります。
それでもやはり、大きな鍵となるのは親の姿です。家庭内でパートナーといつも喧嘩ばかりしているということはありませんか? そんな状況では、モデリング効果が悪い方向に働き、子どもは「誰かを嫌だと思ったら喧嘩すればいい」と学んでしまいます。
夫婦であっても他人同士ですから、意見が対立することもあるでしょう。でも、そこで感情的に喧嘩をする姿を子どもに見せない努力は必要です。むしろ、そのようなときこそ冷静になってお互いの意見を交わし、妥協点を見出して解決を図る姿を見せてほしいのです。意見の食いちがいはネガティブな要素かもしれませんが、やりようによっては、子どもの社会性を伸ばすチャンスにもなり得るのではないでしょうか。

『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』
ボーク重子 著, 中山芳一 著/Gakken (2025)
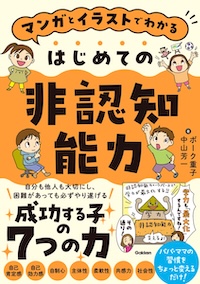
■ 国際コーチング連盟ライフコーチ・ボーク重子さん インタビュー一覧
第1回:「非認知能力が高い子ほど、勉強も伸びる」——“自走する子” の育て方をボーク重子さんに聞く
第2回:親が話すのはたった2割。「80対20の法則」で子どもの心が育つ
第3回:幸せも成功も、“自制心” からはじまる——人間関係をこじらせない子の育て方
【プロフィール】
ボーク重子(ぼーく・しげこ)
福島県出身。合同会社BYBSコーチング代表、Shigeko Bork BYBS Coaching LLC 代表。ICF(国際コーチング連盟)会員ライフコーチ。30歳目前に単独渡英し、美術系の大学院サザビーズ・インスティテュート・オブ・アートに入学、現代美術史の修士号を取得する。1998年に渡米、結婚し娘を出産する。非認知能力育児に出会い、研究・調査・実践を重ね、自身の育児に活用。娘・スカイが18歳のときに「全米最優秀女子高生」に選ばれる。子育てと同時に自身のライフワークであるアート業界のキャリアも構築、2004年にはアジア現代アートギャラリーをオープン。2006年、アートを通じての社会貢献を評価され「ワシントンの美しい25人」に選ばれた。現在は、「非認知能力育成のパイオニア」として知られ、日米で非認知能力の育成を目的とするコーチング会社2社の代表を務め、全米・日本各地で子育てや自分育てに関するコーチングを展開中。大人向けの非認知能力の講座が6カ月の予約待ちとなるなど、好評を博している。『子どもを壊さない中学受験』(KADOKAWA)、『大人の「非認知能力」を鍛える25の質問』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『しなさいと言わない子育て』(サンマーク出版)、『子育て後に「何もない私」にならない30のルール』(文藝春秋)など著書多数。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。



















