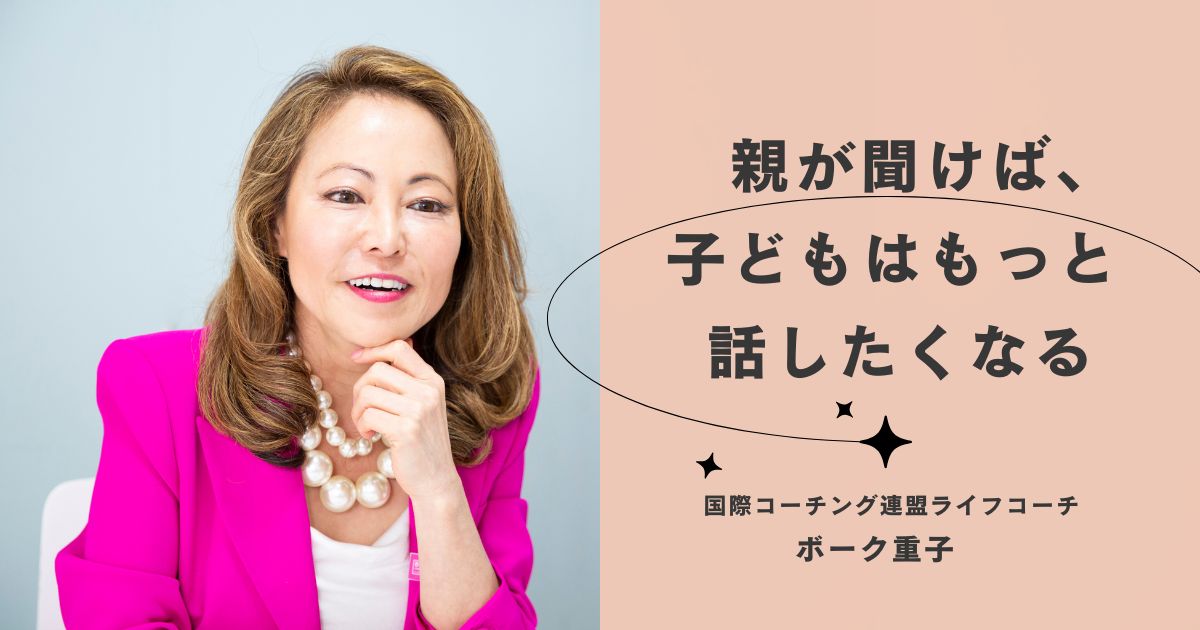一般的に「IQや学力テストなどでは測れない、心の働きにかかわる能力」とされる「非認知能力」ですが、心理学や発達研究の観点からは、子どもの非認知能力をもっとも左右するのは、親子のコミュニケーションだといわれます。具体的に、どのようなコミュニケーションが望ましいのでしょうか。「非認知能力育成のパイオニア」と呼ばれるボーク重子さんが教授してくれたのは、「子どもの非認知能力を伸ばす親の伝え方」の大原則でした。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人(インタビューカットのみ)
目次
「これさえ言っておけばいい」というフレーズは存在しない
「子ども」とひとことで言っても、その性格は十人十色です。それだけでなく、親子であっても性格が正反対ということも珍しくありません。もって生まれた気質は人それぞれに異なって当然です。
気質を広くとらえると、「ものごとへの向き合い方」という見方もできます。たとえば、なんらかの失敗をしたなどネガティブな出来事が起きたとき、がっくりと落ち込んでしまう人もいれば、「こういうこともある」とのんびりと受け止められる人もいますし、「もう絶対に同じミスはしないぞ!」と奮起する人だっています。
ですから、「子どもの非認知能力を伸ばすためには、このフレーズさえ言っておけばいい」といった便利な言葉は残念ながら存在しません。大人だってそうですが、たとえ同じ言葉を同じいい方で伝えたとしても、そのとらえ方は気質次第で大きく変わりますよね?
しかし、どのような気質の子どもであっても、非認知能力を伸ばすために効果が高い「親の伝え方の原則」と言えるものが存在します。
②「80対20の法則」で「聞く」を徹底
③込める思いは「愛・思いやり・受容」

子どもの言葉に耳を傾け、肯定する
最初の原則は、「①言葉で伝えるときは『肯定・質問・論理』」というものです。子どもがなんらかの考えを示したとき、大人から見ればおかしく感じる考えだったとしても否定してはいけません。親というもっとも信頼を置く人間から肯定されることで、子どもは「このままの自分でいいんだ」と、重要な非認知能力のひとつである自己肯定感を育んでいけます。
肯定した次は、「どうしてそう思うの?」と質問をしましょう。子どもに自分で考えるように促すことで、子どもの思考力が育まれます。
ただし、子どもや周囲に危険が及ぶ可能性があるとか、社会的なマナー違反にかかわるような、しつけをしてルールを教える必要がある場面では、そのまま肯定するわけにはいきません。でも、感情的になって叱り飛ばすのは、やはりよくない行動です。
そのような場面では、叱責や命令、指示といった「感情」ではなく、「論理」的に伝えることを考えましょう。幼く成長途上にある子どもは、「なぜそうしてはいけないのか」がまだわかっていないだけなのです。そこを丁寧に論理的に教えてあげればいいだけの話です。
また、子どもとの会話では、「 ②『80対20の法則』で『聞く』を徹底」することを心がけましょう。親は「子どもから聞くのを80%、自分が話すのを20%」の割合にするのです。大人でも、落ち込んでいるとき、誰かにただ話を聞いてもらえるだけでも安心しますよね。そう思える理由は、「自分は大切にしてもらえている」「ここにいていいんだ」と自分を肯定できるからです。これが、自己肯定感の育成につながります。
ほかにも、親が聞く時間が長ければ長いほど、子どもが自分で考えて答えを出す機会が増えますから、「自分でできる」という自己効力感が高まるだけでなく、親が子どもの話にしっかり耳を傾ける姿勢をモデルにして共感力が高まるなど、非認知能力を総合的に伸ばすことができるのです。

子どもが「素の自分」を見せられる家庭にする
最後の原則は、「③込める思いは『愛・思いやり・受容』」です。ここまでややテクニカルな内容について解説してきましたが、子どもとのコミュニケーションにはなによりも愛と思いやりを込めてほしいですし、子どもを受容してあげてください。
これは、大人であるわたしたちも同様で、外では強がっていても、愛する家族の前では素の自分でいたいはずです。ときには、弱い自分を見せて慰めてもらったり励ましてもらったりと、誰かに受け入れてほしい願望は多くの人がもっているでしょう。
幼い子どもでも、家では泣き虫でもお友だちの前では泣かないように我慢するというように、しっかりと「外の顔」があります。それなのに、もし家庭で安心して素の自分を見せられなかったらどうなるでしょうか?
「自分をそのまま出すと否定される……」と自己肯定感が低下したり、子どもの内面でフラストレーションが溜まることで感情を調整できなくなったり、あるいは、「親の言うとおりにしなければいけない」と主体性が低下したりするなど、非認知能力の育成に大きな悪影響が及んでしまいかねません。
親であれば、子どもに「いい子に育ってほしい」と願って当然です。しかし、その思いが強過ぎるあまりに、子どもに厳しいだけの親になり、ひいては家庭を子どもが安心できない環境にしてしまうことは避けてほしいのです。人間にはいいところも悪いところもあって当然なのですから、それらのすべてを子どもが安心して見せられるような家庭環境を築くことを意識してほしいと思います。

『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』
ボーク重子 著, 中山芳一 著/Gakken (2025)
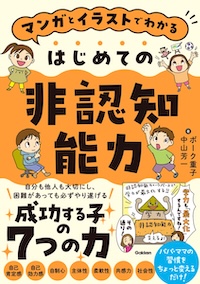
■ 国際コーチング連盟ライフコーチ・ボーク重子さん インタビュー一覧
第1回:「非認知能力が高い子ほど、勉強も伸びる」——“自走する子” の育て方をボーク重子さんに聞く
第2回:親が話すのはたった2割。「80対20の法則」で子どもの心が育つ
第3回:幸せも成功も、“自制心” からはじまる——人間関係をこじらせない子の育て方
【プロフィール】
ボーク重子(ぼーく・しげこ)
福島県出身。合同会社BYBSコーチング代表、Shigeko Bork BYBS Coaching LLC 代表。ICF(国際コーチング連盟)会員ライフコーチ。30歳目前に単独渡英し、美術系の大学院サザビーズ・インスティテュート・オブ・アートに入学、現代美術史の修士号を取得する。1998年に渡米、結婚し娘を出産する。非認知能力育児に出会い、研究・調査・実践を重ね、自身の育児に活用。娘・スカイが18歳のときに「全米最優秀女子高生」に選ばれる。子育てと同時に自身のライフワークであるアート業界のキャリアも構築、2004年にはアジア現代アートギャラリーをオープン。2006年、アートを通じての社会貢献を評価され「ワシントンの美しい25人」に選ばれた。現在は、「非認知能力育成のパイオニア」として知られ、日米で非認知能力の育成を目的とするコーチング会社2社の代表を務め、全米・日本各地で子育てや自分育てに関するコーチングを展開中。大人向けの非認知能力の講座が6カ月の予約待ちとなるなど、好評を博している。『子どもを壊さない中学受験』(KADOKAWA)、『大人の「非認知能力」を鍛える25の質問』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『しなさいと言わない子育て』(サンマーク出版)、『子育て後に「何もない私」にならない30のルール』(文藝春秋)など著書多数。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。