いまや子育てを語る際にすっかり浸透した感のある「非認知能力」という言葉ですが、非認知能力の育成に特化したコーチング会社を日米で2社経営し、自らもライフコーチとして講演会やワークショップを展開するボーク重子さんも、非認知能力を重視して子育てをしたひとりです。その結果、娘のスカイさんは、全米の女子高生が知性や才能、リーダーシップを競う大学奨学金コンクール「全米最優秀女子高生」で優勝するという偉業を成し遂げました。「非認知能力育成のパイオニア」ともいえるボークさんに、あらためて非認知能力の重要性についてお話を聞きました。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人(インタビューカットのみ)
目次
非認知能力の重要性が高まっているわけ
すでに広く知られるようになりましたが、テストの点数や偏差値といった数字で測れる能力である「認知能力」に対し、数字では表すことができない能力を「非認知能力」と呼びます。その能力の幅は広く、私が重要だと考えるものなら、たとえば自己肯定感、自己効力感、自制心、主体性、柔軟性、共感力、社会性などが挙げられます。
非認知能力の注目度がますます高まっている最大の理由は、時代の変化でしょう。かつてなら認知能力、つまり、単純にいえば学力を伸ばすことが絶対的な正義だとされてきました。でも近年、一般入試で大学へ進学する割合は半数以下となり、推薦入試や総合型選抜などで進学する割合が増加傾向にあります。
もちろん、推薦入試や総合型選抜においても一定の学力が求められますが、より重視されるのは「プラスαの能力」です。これらの形式の入試では、エッセイや面接、活動報告書(ポートフォリオ)などを通じ、学力のみでは測ることができない、受験生の非認知能力を多角的に評価するのです。
なぜ大学は非認知能力を問うようになったのでしょう? それは、シンプルに社会で求められる能力が変わったからです。インターネットの普及やAIの台頭により、正解がある課題に対していち早く解答するといった認知能力の重要性はかつてより大きく低下しました。情報収集や要約、分析、データ処理といった作業はAIに任せればよくなったからです。
代わりに社会人に求められるようになったのは、たとえばどのような課題があるのかを見抜く課題設定力や、新たな価値を生む創造性といったもの。そうした能力は、「私ならきっと新たなアイデアを生み出せる」という自己効力感や、自らを律して自発的にものごとに取り組む自制心や主体性、柔軟に考える力などと大きな関連があることは明らかです。

非認知能力は認知能力のベースにもなる
ただ、非認知能力の重要性が高まっているからといって、認知能力が不要になったわけではありません。いくら非認知能力が高くても、基本的な知識、数的処理能力、読解力などに欠けていれば、理解や判断の誤りが増えたり、複雑な課題には太刀打ちできなかったりするでしょう。
ですから、認知能力を高めることをおろそかにはできませんが、それでも重要なのは、やはり非認知能力も同時に育むことです。なぜなら、「非認知能力を高めれば、認知能力も伸びていく」という研究結果が世界中に数多く存在するからです。非認知能力は、認知能力のベースとなるのです。
そうした研究の内容を知らなくとも、このことはちょっと考えれば納得できるはずです。子どもの宿題を例に挙げましょう。自制心をもつ子は、いま現在だけではなく先を見通すことができます。遊びに夢中になっていても、「宿題をやらなければ、明日困ってしまう」と考えて宿題にきちんと取り組むことができるのです。
あるいは「自分にはきっとできる」という自己効力感がある子は、「今日の宿題はちょっと難しいけれど、頑張ってみよう」と途中で投げ出すことなくチャレンジを続けられます。そのようなかたちで、非認知能力は「自分自身を一歩前に進めてくれる」のですから、非認知能力を高めれば認知能力も自然と伸びていくのです。
このことは、逆のケースを考えたほうがわかりやすいかもしれません。自制心がない子は、宿題をやらなければならないとわかっていても目の前の遊びをやめることができません。ちょっと難しい課題にぶつかればすぐにあきらめてしまいます。そんなことでは、たとえもともとの地頭がよかったとしても、それをさらに磨くことは難しいと言えます。

子育てのゴールは、「自走する子」を育むこと
先の宿題への取り組み方の例からも見えてきますが、非認知能力が高い子どもは、自ら考えて主体的にやるべきことにしっかりと取り組める、「自走する子」に育っていきます。この自走する子を育むことこそが、私が考える「子育てのゴール」です。
なぜなら、自走することは「幸せ」に直結するからです。自走できる子は自分のことを自分で決められますが、自分で決めるためには、自分自身の正解(考え)が必要です。まわりになんと言われようが、「自分はこれがいいんだ」と言えるのです。
すると、そこには責任が生まれます。自分の考えに基づいて決めたのですから、仮に問題が発生する結果になったとしても、それを他人のせいにはしません。だからこそ、その子は頑張ることができるのです。自らの責任において、かけがえのない人生を自分らしく生きていけることこそが、幸せなのではないでしょうか。
自走する子を育むためにも、親御さんには自分の考えに対していわゆる「クリティカル・シンキング(批判的思考)」をもってほしいと思います。親ですから、愛するわが子に期待したりその将来を心配したりするのは当然のことです。
しかし、だからといって「こうするべきだ!」と自らの考えを子どもに押しつけてはすべてが台無しです。親の正解はあくまでも親の正解に過ぎないのですから、ひとりの独立した人間である子どもの考えを尊重してあげてください。
子どもに対して「こうしてほしい」と思うことがあれば、その都度、「私はこう思うのだけれど、あなたはどう思う? どうしたい?」と子どもに尋ねる習慣を身につけましょう。そうすれば、子どもは子どもなりに「どうするのがいいかな」と自ら考えるようになります。その積み重ねにより、自ら考えて自分のことを決められる、自走する子に育っていくのです。

『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』
ボーク重子 著, 中山芳一 著/Gakken (2025)
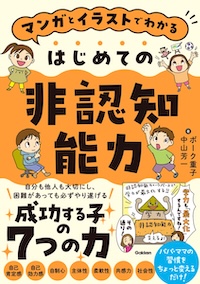
■ 国際コーチング連盟ライフコーチ・ボーク重子さん インタビュー一覧
第1回:「非認知能力が高い子ほど、勉強も伸びる」——“自走する子” の育て方をボーク重子さんに聞く
第2回:親が話すのはたった2割。「80対20の法則」で子どもの心が育つ
第3回:幸せも成功も、“自制心” からはじまる——人間関係をこじらせない子の育て方
【プロフィール】
ボーク重子(ぼーく・しげこ)
福島県出身。合同会社BYBSコーチング代表、Shigeko Bork BYBS Coaching LLC 代表。ICF(国際コーチング連盟)会員ライフコーチ。30歳目前に単独渡英し、美術系の大学院サザビーズ・インスティテュート・オブ・アートに入学、現代美術史の修士号を取得する。1998年に渡米、結婚し娘を出産する。非認知能力育児に出会い、研究・調査・実践を重ね、自身の育児に活用。娘・スカイが18歳のときに「全米最優秀女子高生」に選ばれる。子育てと同時に自身のライフワークであるアート業界のキャリアも構築、2004年にはアジア現代アートギャラリーをオープン。2006年、アートを通じての社会貢献を評価され「ワシントンの美しい25人」に選ばれた。現在は、「非認知能力育成のパイオニア」として知られ、日米で非認知能力の育成を目的とするコーチング会社2社の代表を務め、全米・日本各地で子育てや自分育てに関するコーチングを展開中。大人向けの非認知能力の講座が6カ月の予約待ちとなるなど、好評を博している。『子どもを壊さない中学受験』(KADOKAWA)、『大人の「非認知能力」を鍛える25の質問』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『しなさいと言わない子育て』(サンマーク出版)、『子育て後に「何もない私」にならない30のルール』(文藝春秋)など著書多数。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。
















