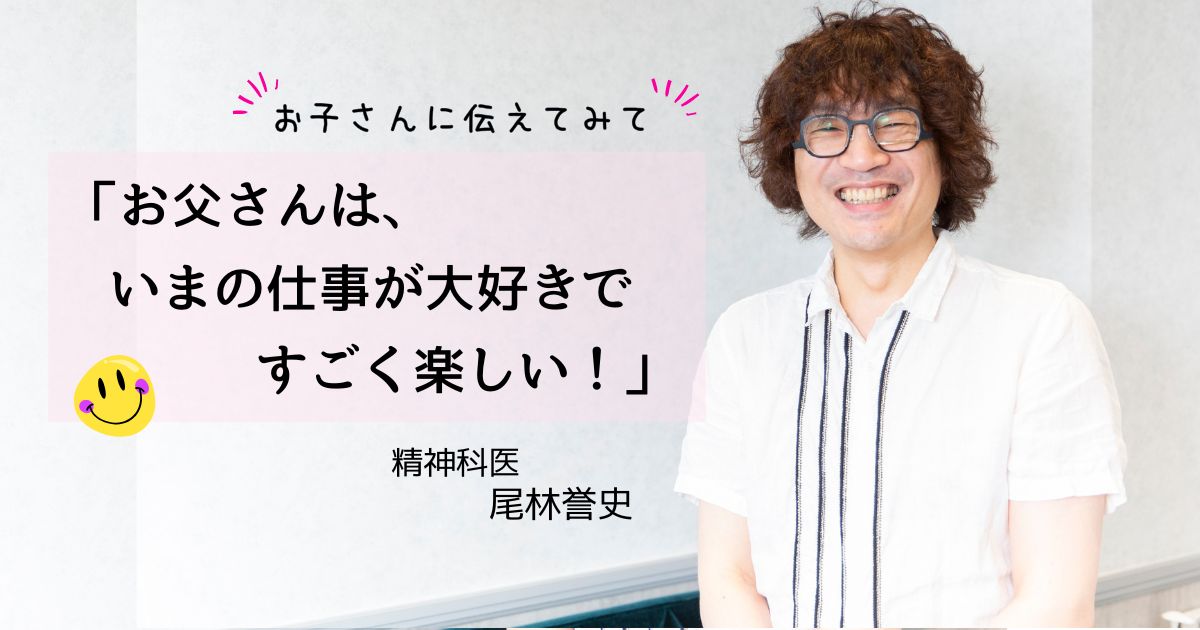いつでもどこでもインターネットを使える時代、生成AIの登場も相まって、知らないことやわからないことがあれば即座に調べられるようになりました。しかし、そのあまりに便利な状況が、子どもの「自己肯定感」の育成に暗い影を落としている可能性があります。産業医として活動する精神科医の尾林誉史先生は、「自己肯定感を育みにくいいまこそ、親の振る舞いが問われている」と警鐘を鳴らします。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人(インタビューカットのみ)
目次
周囲に合わせるなかでは自己肯定感は育たない
子育てや子ども教育の場で注目されているキーワードのひとつに、「自己肯定感」があります。この言葉の意味はすでに広く知られるようになっていますが、自己肯定感とは、「他人からの評価に左右されず、ありのままの自分を認めて自分の価値を肯定できる感覚」を意味します。
ただ残念ながら、子どもの自己肯定感を育みにくいのが現代社会なのです。見方を変えれば、育みにくいからこそ自己肯定感がより注目されるようになってきているのかもしれません。
その背景として見逃せないポイントが、インターネットの普及によって「情報検索が容易になった」ことです。ひとむかし前なら考えられないような状況ですが、子どもたちでさえ、日常的にネット検索をしたり生成AIを利用したりできるようになりました。
たしかに便利な時代です。しかし、あたかも「正解らしきもの」がすぐに提示されるため、自分でじっくりと考えたり、自らの経験から学んで「これこそが自分にとっての答えだ」と思えるものを見つけたりする機会が極端に減っているのです。
その結果、「こういうときはこうしたほうがいい」といった、ネット検索で示された「正解らしきもの」というモデルから外れないようにすることばかりを優先してしまい、子どもたちは冒険しなくなり、無難なところに落ち着こうとします。
こうした傾向は、「人とちがうことをしたらいけない」「好奇の目で見られないようにしよう」といった同調圧力を強めることにつながっていきます。そしてなにより問題なのは、「まわりに合わせることが正義だ」と考える状況では、「自分には価値がある」という自己肯定感を育むことが難しくなってしまうということです。

SNSがもたらす「攻撃するか」「逃げるか」の二択
また、情報検索の他に、「SNSの浸透」も自己肯定感育成の障壁となっていると見ています。黎明期のSNSなら、「うちの子どもがはじめてつかまり立ちをした!」「昨日、ちょっと背伸びをして高級レストランでご飯を食べた」といった、それこそただの「つぶやき」といえる、一般の人たちのシンプルな日常の投稿が多かったように思います。そして、それに対して「いいね」をもらえることで投稿者は嬉しい気持ちにもなれました。
ところが、SNSが完全に浸透したいまはそうではないようです。インフルエンサーなどが「いいね」の数を競うなか、ちょっとしたことで「炎上」することも頻繁に起こります。その流れから、SNSには人を叩く、人を傷つける言葉があふれているように思います。
いまのSNSは、人と良好な関係を維持しながら相手の考えにある問題点をやんわりと指摘するとか、人の考えを尊重しながら「でも、自分はこう思うな」と主張するといったことが難しくなっているのです。そんなSNSに触れる子どもたちが、悪影響を受けないわけがありませんよね?
そんな状況では、子どもたちの選択は、「徹底的に誰かを叩く」か、それとも「まったくの無風地帯に逃げ込む」かの二択になっていきます。徹底的に誰かを叩く場合、「自分は正しい」と考え、自己肯定感が高まっているように思えるかもしれません。ただしそれは、相手を否定することで成り立っており、他人との比較をベースにしているため、真の自己肯定感を育むことにはつながらないのです。
一方、まったくの無風地帯に逃げ込む場合は、周囲から攻撃されないよう「目立たないようにまわりと合わせる」という思考におちいるため、やはり自己肯定感を育むことにはならないでしょう。

子育てばかりに集中せず、親自身の「好き」を見せることも大切
こうした状況のなか、子どもの自己肯定感をしっかり育むために親にできることはなんでしょうか? 精神科医であり、ひとりの親でもある私としては、親自身が思うよき振る舞いやよき夫婦関係、家族関係というものを目指すことが最善だと考えます。もう少し言及すると、親として、夫婦として、あるいはひとりの大人として、どのような振る舞いがいいのかと考えてください。
なぜなら、子どもは親を映す鏡だからです。「どうせ私には無理」など日常的に自分を卑下する言葉ばかりを口にしたり、「失敗したら恥ずかしいから」と新たなチャレンジを避けたりする親の姿を日常的に見せられた子どもが、「自分には価値がある」「きっとできる」と考えるようになることはまずありません。
そして、「子育てに集中しない」という意識をもつことも大切であると考えます。親が子どものことを最優先に考えるのは当然ですが、その意識が強過ぎると、「子どもにはこういう姿を見せたほうがいいだろう」と、他人軸での考え方になってしまうのです。いい意味で子育てに集中せず、たとえばみなさん自身が強い興味をもっている趣味や仕事について子どもに熱く語るということでもいいですよね。
私自身、ふたりの娘に対しては、「お父さんはいまの仕事が大好きですごく楽しい」「たくさんの人の役にも立てているとも思う」「仕事を通じてお父さん自身も学ぶことが多いから、どうしても一生懸命やっちゃうんだよね」というように、仕事についていろいろと話すようにしています。
そのような言葉や姿から、「そんなに好きなことがあるってすごいな」「私が好きなものってなんだろう?」と子どもが考えることもあるでしょう。ひいては、子ども自身が好きなことを見つけ、それに打ち込むなかで失敗しながらも成功体験を積み、自己肯定感を高めていくことにもつながっていくはずです。

『精神科医が教える 休みベタさんの休み方』
尾林誉史 著/すばる舎 (2025)
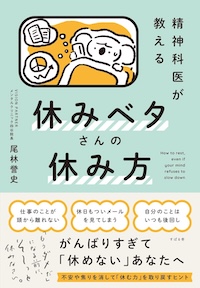
■ 精神科医・尾林誉史先生 インタビュー一覧
第1回:【不登校34万人】小中学生が出す“心のSOS”──親が気づくサインとは?
第2回:自己主張できる子は強い? 精神科医が語る「いい子」が抱える見えないリスク
第3回:人と同じじゃないと不安――「正解ばかり探す子」に精神科医が伝えたいこと
【プロフィール】
尾林誉史(おばやし・たかふみ)
1975年4月29日生まれ、東京都出身。精神科医、産業医。VISION PARTNERメンタルクリニック四谷院長。株式会社産業医代表取締役。東京大学理学部化学科卒業後、株式会社リクルートに入社。社内外や年次を問わず発生するメンタル問題に多数遭遇。解決に向けて付き添うなかで目にした産業医の現状に落胆するも、とあるクリニックの精神科医の働き方に感銘を受ける。2006年、産業医を志して退職。退職後、弘前大学医学部に学士編入。産業医の土台として精神科の技術を身につけるため、東京都立松沢病院にて初期臨床研修修了後、東京大学医学部附属病院精神神経科に所属。現在はnote、面白法人カヤック、ジモティーなど23社の企業にて産業医およびカウンセリング業務を務める他、メディアでも精力的に情報発信を行っている。著書に『働く人のためのメンタルヘルス術』(あさ出版)、『がんばらない めんどくさくない 人間関係を築くコツ』(ナツメ社)、『先生、毎日けっこうしんどいです。』(かんき出版)などがある。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。