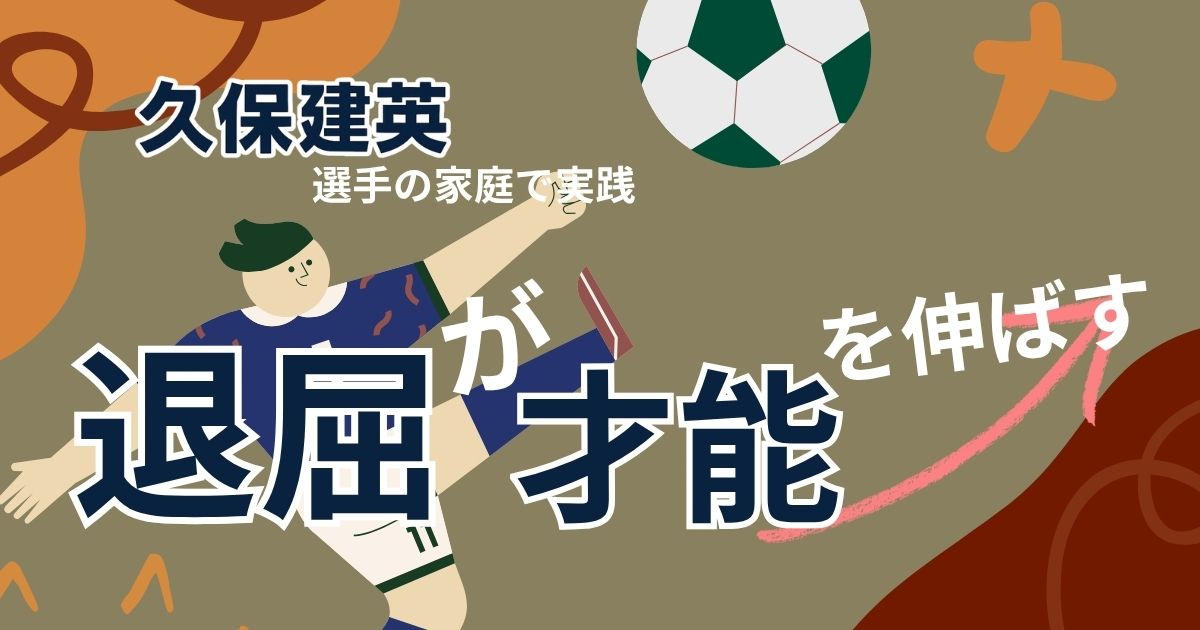「子どもが退屈しないように」と、つい新しいおもちゃを買い足したり、習い事の予定を詰め込んだりしていませんか?
でも、スペインで活躍するサッカー日本代表・久保建英選手の家庭は違ったようです。あえて “退屈な時間” や “余白のある環境” を大切にしていたのです。
じつはこの「子ども自身が考える余地」こそが、子どもの才能を伸ばすチャンス。今回は久保選手の幼児期をヒントに、あえて余白をつくり、才能を伸ばす子育て術を3つ紹介します。
目次
1. 「おもちゃを減らす」子育て術
なぜなら、刺激が多すぎると “外で工夫する力” が育ちにくいから
久保選手の母親は、いくつかの頂き物以外、家におもちゃを置きませんでした。その理由は、家の居心地がよいと外遊びをしたがらなくなるから。
その結果、久保選手は2歳からボールを蹴り始め、毎日のように外で遊んでいました。父親は仕事前の毎朝1時間、近所の公園で一緒にサッカーをしたといいます。1年のうち350日以上はボールを蹴っていたそうです。
トレド大学の研究では、おもちゃの数が少ない環境の方が、子どもの集中力が高まり、創造的な遊びが増えることが明らかになっています。
この「限られた環境で工夫する経験」が、試合中に最適解を導く力の土台になったと考えられます。
- おもちゃは厳選し、すべてを出しっぱなしにしない
- 「いまあるもので何ができるか」を考える習慣が、工夫する力を育てる
- 外遊びの時間を意識的に増やす

2. 「テレビをつけず、読書の時間をつくる」子育て術
なぜなら、受動的な刺激より能動的な思考が大切だから
久保選手の家庭では、小さいうちはテレビをつけない方針でした。その代わり、両親が絵本を読み聞かせ、家には400冊ほどの絵本がありました。やがて図書館で毎週20冊以上借りて読むようになったといいます。
父親によれば、本を読んでいる時にわからないことがあると止めて質問していたそうです。自分のペースで読み進められるのが読書のいいところ。理解力や試合での判断力など、サッカーをする上でも大事な能力が読書で磨かれたと振り返っています。
Scientific Reportsに掲載された研究では、読書時間が多い子どもほど認知能力が高く、脳の言語処理に関わる領域が発達していることが示されました。一方、テレビ視聴は認知能力の低下と関連していました。
読書を続けてきたことで、わからないことはすぐに聞くというコミュニケーション能力も育ったといいます。この子育て方法が、バルセロナ入団という快挙につながる基礎を築きました。
💡Tip②:能動的に考える時間をつくる(読書する習慣を)
- 小さいうちは読み聞かせから始める
- 図書館を活用し、子どもが好きな本を選ばせる
- テレビやYouTubeの時間を見直す

3. 「 “どうしたい?” と問いかける」子育て術
なぜなら、子ども自身に考えるチャンスを渡せるから
久保選手が6歳のとき、「バルサに入りたい」と言い出しました。両親は「それなら、やってみよう」と自然に受け入れ、本人の意思を最優先にしたといいます。
父親は常に問いかけることを大切にしていました。新しい練習に取り組むときも、チームを選ぶときも、常に本人に確認し、その気持ちを最優先にしていたそうです。
ロチェスター大学の研究では、自分で選んだ行動のほうがモチベーションが長続きし、学習効果も高いことが示されています。
久保選手の「自分で状況を判断し、最適なプレーを選択する力」。その背景には、幼少期からの「自分で決める経験」の積み重ねがあるのではないでしょうか。この教育方針が、世界で活躍する天才サッカー選手を育てる鍵となったのです。
💡Tip③:「どうしたい?」の質問を習慣に
- 宿題をする順番
- 遊び場所
- 週末の予定 など
***
工夫の余白、時間の余白、決断の余白——久保建英選手の幼少期に共通していたのは、「余白」でした。そんな環境が、「自分で考え、動く力」を育てたのです。
子どもの才能は、何もない時間のなかでこそ、静かに育っていきます。家庭にあえて “余白” をつくってみませんか?
(参考)
University of Toledo News | Fewer toys lead to richer play experiences, UT researchers find
Scientific Reports | Neurocognitive and brain structure correlates of reading and television habits in early adolescence
Reading Research Quarterly | Television’s Impact on Children’s Reading Comprehension and Decoding Skills: A 3-Year Panel Study
PubMed | Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being
文藝春秋| 息子・建英のバルサ入団まで『おれ、バルサに入る!』
サカイク | 『バルサに入る!』親は息子の夢をかなえるサポート役でありたい―久保建史