「結婚したら、子どもを産んだら幸せになれると思っていたのに、実際には幸せを感じられない……」。忙しさもあって精神的に不安定になりがちな子育て中は、そのような悩みを抱える人も決して少なくありません。幸せな子育てをするためには、どのような意識を大事にすべきなのでしょうか。『幸せを手にできる脳の最適解 ウェルビーイングを実現するレッスン』(KADOKAWA)を上梓した、東北大学准教授で脳科学者の細田千尋先生が、「大前提」となる考え方から解説してくれます。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/塚原孝顕(インタビューカットのみ)
目次
「人は公平であるべきだ」と思うと、不幸になる
私の専門は脳科学ですが、それを応用して「ウェルビーイング」についての研究もしています。懸命に子育てに臨んでいるみなさんが幸せを感じられるために、幸せに関する興味深い研究結果をひとつ紹介しましょう。
それは、人は赤ちゃんの頃から社会的に公平であることを望み、たとえ3歳くらいの幼い子どもであっても、たとえば「まわりの子のほうが、自分よりもたくさんのおやつをもらえた」といった不公平を感じたら、泣き叫んで強い不満を示すというものです。
しかも、この研究には続きがあり、「人はそもそも公平ではないんだ」という認識をもっている人ほど、「困難な状況やストレスに直面した際に適応したりそこから回復したりする力」とされる「レジリエンス」が高いということもわかりました。
つまり、「人は公平ではない」と思っている人は、なにか苦しい状況に陥っても落ち込むことなく立ち直れるため、日々のなかで幸せを感じやすいということです。そして、「全人類は公平で平等であるべきだ」と思っている人は、ちょっとした困難にもひどく落ち込んでしまい、幸せを感じにくいということなのです。
子育て中の親は、どうしてもほかの家庭と自分の家庭を比べがちです。子どもの発達の早さ、習い事の成果、子どもの性格や行動などのほか、パートナーの協力体制や家庭の経済力、生活水準といったものもつい比較してしまう人も多いでしょう。
しかし、いくら他人をうらやんでも、なにかが変わるわけではありません。それどころか、それはむしろ自分を不幸にしてしまう行為なのですから、「人は公平などではない」という前提に立ち、いま自分が手にしているものや置かれている環境のなかで、「どうすればもっと幸せになれるかな?」と考えることが、幸せへ向かう道筋なのです。

人は「なにかをコントロールしたい」と思う生き物
先に、ほかの家庭と比べる要素として「パートナーの協力体制」も挙げました。パートナー、あるいは子どもに対するかかわり方も、幸せという観点からは重要なポイントです。
みなさんのなかに、「パートナーや子どもに対して、私の思うとおりにこうしてほしい、こうやって動いてほしい」と考えている人はいませんか? それは単なるエゴであり、その願いが叶うことは滅多にありませんから、そう考える人はおそらく不満やストレスを募らせ、結果として幸せを感じられなくなっていることでしょう。
人間という生き物は、「なにかをコントロールする」ことに強い快楽を感じます。たとえば、新たなことにチャレンジするようなときに、自分の思いどおりに自分をコントロールしてきちんと成果を出せたなら、誰だって嬉しいはずです。つまりそれは、幸せを感じているという状態です。
もちろん、コントロールしたいと思う対象には、他人も含まれます。子育てに追われるなか、パートナーに対して「わざわざ言わなくても、洗濯物をたたむくらいの協力はしてくれていいのに」とか、「子どもの教育方針については、自分任せにせずに真剣に考えてほしい」などと思うようなことです。
ところが、意識的、無意識的はありますが、相手も自分と同じように「(ある程度)状況が自分の望むようにコントロールできたらよい」という欲求をもっているわけですから、両者はつねに平行線をたどることになります。
もちろんこれは、対子どもの場合も同じです。親が「時間がないんだから、少しだけおしゃべりを我慢して早く朝ごはんを食べてほしい」「遊んだおもちゃはちゃんと片づけてほしい」と思うだけでは、その願いが叶うことはありません。

「こうしてほしい」と思う理由を、子どもと共有する
では、そのような不満を抱えている場合、どうすればいいでしょうか? その出発点は、自分自身が「なぜそう思うのか」という理由を明確にすることにあります。なぜなら、自分では「こうしてほしいと思うのがあたりまえ」と考えていることも、相手にとってはそうではないからです。そして、その理由を相手と共有するのです。
先の子どもの例であれば、「朝ごはんに時間がかかって幼稚園に遅れちゃうと、先生に心配をかけちゃうよ」「朝一番の運動会の練習ができなくなるよ」といった理由を伝えて問題意識を共有したうえで、「だから、もう少し早く朝ごはんを食べたほうがいいよね」と伝えるという具合です。
同じことをさせて同じゴールに向かわせるという結果としては、ただ「早く朝ごはん食べて」と伝えることと変わらないかもしれません。でも、子どもからすると、叱られるから言われたとおりにするのか、それとも「大好きな先生に心配をかけたくない」と思ってそうするのかでは、納得感に大きな違いがあるでしょう。
これは、じつはビジネスにおける組織マネジメントとまったく同様のものです。上司であれば、なんらかの問題がある部下に対しては、「部下にはこうしてほしい」と考えますが、それをそのまま伝えてもうまくいくことは多くありません。「なぜこうしてほしいと思うのか」という理由を部下に伝え、「確かににそのとおりだ」と部下が納得するからこそ、行動変容が起きるのです。

『幸せを手にできる脳の最適解 ウェルビーイングを実現するレッスン』
細田千尋 著/KADOKAWA(2023)
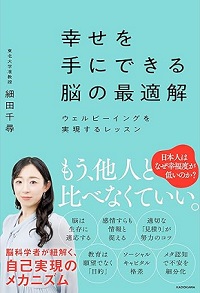
■ 脳科学者・細田千尋先生 インタビュー一覧
第1回:早期教育が“幸せ”を奪う? 脳科学でわかった、「親の期待」が子どもを苦しめるメカニズム
第2回:癇癪もわがままも“異常”じゃない──脳科学者が教える「イヤイヤ期」の本当の意味
第3回:「こうしてほしい」はあなたのエゴ。コントロール欲を手放すことから始まる【幸せな子育て】
【プロフィール】
細田千尋(ほそだ・ちひろ)
医学博士・認知神経科学者・脳科学者。東北大学加齢医学研究所及び、東北大学大学院情報科学研究科准教授。東京医科歯科大学大学院医歯学総合博士課程修了。国立精神・神経医療研究センター流動研究員、(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)専任研究員、東京大学大学院総合文化研究科特任研究員、JSTさきがけ専任研究員などを経て、現職。仙台市教育局「学習意欲」の科学的研究に関するプロジェクト委員会委員、日本ヒト脳マッピング学会委員などを務める。著書に『脳科学が教える 一瞬で心をつかむ技術』(PHP研究所)、『幸せを手にできる脳の最適解 ウェルビーイングを実現するレッスン』(KADOKAWA)がある。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。
















