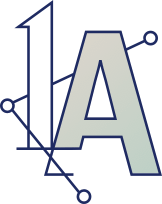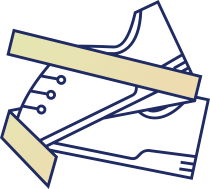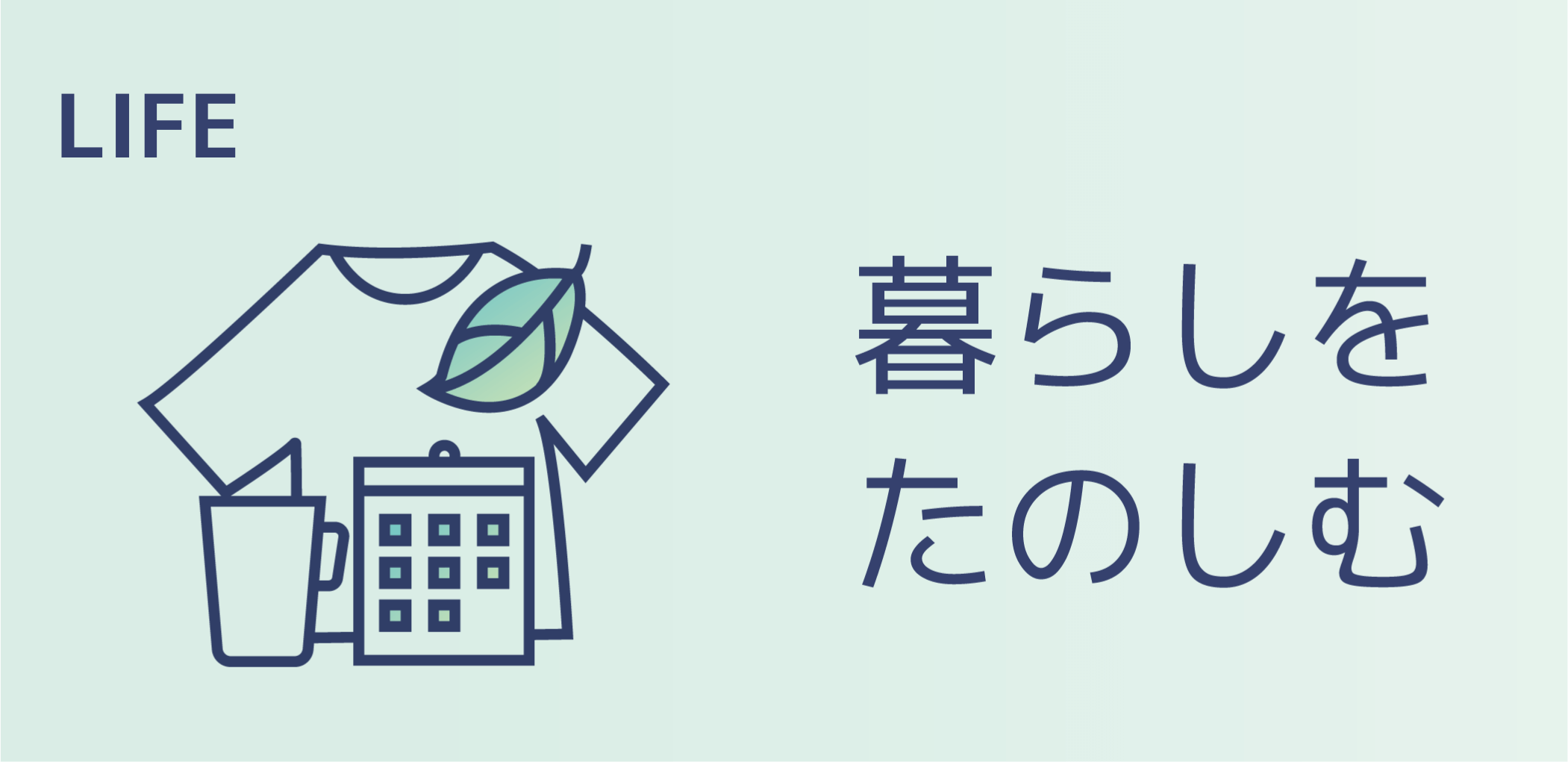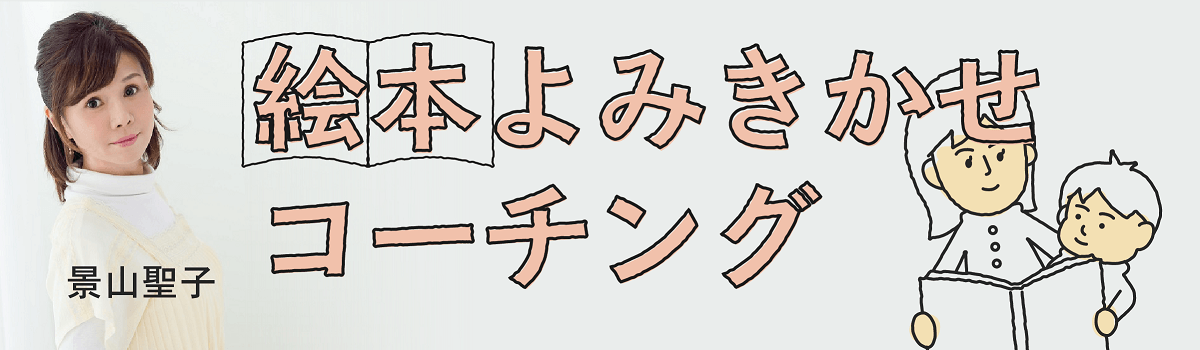これからやってくる社会では、産業構造の変化や人口構造の変化、テクノロジーの劇的な進化などによってこれまで体験したこともないさまざまな問題が起こると言われています。未来の子どもたちもそれらの問題と無縁で生きていくことはできないなか、「より良い社会」を構築していくためには、いったいどのような社会で生きることが「幸せ」と言えるのでしょうか。鈴木謙介先生(関西学院大学 社会学部准教授)のインタビュー最終回は、これから子どもたちが支えていく「未来の社会像」に迫ります。
構成/岩川悟 取材・文/辻本圭介 写真/玉井美世子
目次
現在は「他人事ではない」問題があらゆる人に降り掛かる時代
生きる社会によって「頭の良さ」が変わっていくのと同じように(※鈴木謙介先生1回目、2回目のインタビューを参照)、人生で追い求める「幸せ」の基準やあり方もまた、社会や時代の変化によってその姿を変えていくと言えるのでしょうか。
「かつての高度成長期以降の日本社会では、幸せというものは親と子どもという核家族のなかでつくるものという前提がありました。つまり、幸せになろうとするなら、高い学歴を得ていい会社に入り、そこで得た収入を子どもに投資するという核家族のなかのサイクルだけが幸せを保証する唯一のリソースだったのです」
このような社会の良い点は、親や実家や共同体に縛られることなく、自由に自分たちがつくりたい家庭を持ち、自分たちの理想の子育てができることでした。
「一方、悪い点としては、たとえば政治を変えることや大きな社会問題に対して、ネガティブな態度を取る傾向が生まれることです。核家族のなかだけで十分な『幸せ』を得ることができるのなら、余計な手間をかけて社会の問題などにわざわざ関わっていく必要性は低くなります。そんなことをしなくても、自分たちが直接悪い影響を被るわけではないので、当然と言えば当然のことだったのです。ところが、現在ではもはや他人事とは言えない多くの社会問題が起きています。環境問題や、東日本大震災で顕在化した原発事故の問題、あるいはAIやロボットによる雇用の変化もそのひとつと言えるでしょう。近い将来、AIやロボットが社会に浸透すれば、雇用自体は減らなくても『いまの時代にある仕事』は、かなりの数がなくなっていくと言われています」

「椅子取りゲーム」の椅子がどんどん減って、極端な格差社会になりつつある
そんなAIやロボットをはじめとするテクノロジーの進化によって、「増える仕事」と「減る仕事」が分かれていくときに、社会にはふたつの「格差」が生じていくと鈴木先生は言います。
「ひとつめは、収入や労働条件における格差。いわゆる『いい仕事』とされる仕事には、テクノロジーの進化にキャッチアップできたごく一握りの人だけが携わり、それ以外の大多数は、そうした人たちをサポートする仕事に就く可能性が高くなるでしょう。たとえば、深夜まで営業する外食産業もそのひとつでしょう。たとえ新しく雇用が生まれても、そうした仕事は給料が低く、不安定なものになると言われています。そしてふたつめは、『いい仕事』がますます都市部に集中していくことによって生じる格差です」
「給料がいい仕事」と「それをサポートする仕事」の2極化、そして「都市」と「地方」の2極化が、新しい技術革新によって起こってくるという事実。これからの社会では、大多数の人はどれだけ努力してもなかなか「いい仕事」に就くことができず、不安定に働かざるをえない人が増えていく可能性が高いのです。
「こうした2極化した社会では、さらに新たな仕事として『不安定な立場の人を支える仕事』が必要になってきます。たとえば、シングルマザーをサポートする仕事かもしれないし、遅くまで働かざるを得ない親のために子育てを助ける仕事かもしれません。そしてこうした仕事もまた、決して高い給料をもらえるような仕事ばかりではない可能性がある。ただわたしが言いたいのは、こうした弱い立場の人を支える仕事がないかぎり、これからの日本社会は極端な格差社会にならざるを得ないということです」
このような社会を、鈴木先生は「椅子がどんどん減っているのに、椅子取りゲームを必死に続けている」社会だと表現します。
「これまでは、それなりに椅子の数も足りていたので椅子に座るための学歴を得る競争に邁進することが重要でした。しかし、そんな競争をしても安定した仕事に就けない人が増えていけば、ごく一部の者だけが富むことでバランスが極端に崩れ、社会の根底が成り立たなくなります。そこで、これからはできる限りみんながそれなりの生活を享受できるように支援し合い、みんなが幸せになる社会を目指していくことがなにより大切なことなのです」
みんなが幸せになる社会にしなければ、あなただって幸せにはなれない
では、これからやってくるそんな社会の実像を、できるだけ具体的に子どもに伝えて社会のあり方に目を向かせていくためには、親としてどのような働きかけをすればいいのでしょう。
「たとえば、ボランティアを体験するのはひとつの手段だし、そこまで能動的でなくてもNPO団体や支援団体に対して寄付などの協力をするのもいいと思います。そうした団体は、説明責任を果たすために詳細なレポートを発行することが多いでしょうから、親子でそうしたレポートを一緒に読むだけでも、子どもは自分が支援したことがなにに役立ったのかを知り、社会に対して当事者意識を持つことができると思います」
もちろん、当事者意識を持つことはボランティアや支援団体などへの協力だけに限ることではありません。
「子どもたちが毎日食べている食材について調べてみるのもいいですね。生産者と直接コミュニケーションをとることでリアリティーを持つことができ、子どもにとっては大きな糧となっていくはずです。これまでの自分が普通に生きているだけでは出会えなかったことと出会い、自分の認識の至らなさを思い知りながらも、知らなかったことを知ることの感動を味わうことができます。そうしたことは、子どもにとってじつは体験すること以上に大切なのです」
子どもに体験させる機会さえ与えれば、その問題やテーマについてわかったような気になってしまうことは、親にとって起こりがちなことかもしれません。
「でも本来は、ものごとに深く関わっていくことではじめて『経験』が『体験』に昇華されるのだと思います。たとえば、『こんなに苦労してつくったニンジンがこんな値段でしか売れないの!?』とか、『自分は普通に勉強しているのに、なぜこの人たちには鉛筆すらないんだろう?』など、自分がこれまで生きてきた世界観が揺らぐような認識を持つに至ってはじめて、子どもたちは自分とは異なる他者や世界があることを知り、そこに自分も関わっているのだという問題意識を受け入れていきます」
そんな問題意識をもって社会に目を向けはじめた子どもたちは、これからどのようにして「より良い社会」をつくっていくのでしょう。
「わたしは、これからの時代の幸せは『みんなが幸せになるような社会にしなければ、わたしも幸せになれない』ということに尽きると考えています。そのために、4回にわたって、多様な人々との『協働スキル』や『アサーティブコミュニケーション』が、これからの社会を生きる子どもにとって非常に重要なスキルであるとお伝えしてきました。ふだんの親子のコミュニケーションをとおしてその大切さを伝えていければ、子どもたちはきっと近い将来に、幸せに生きていくためのスキルを身につけることができるでしょう。そして、そうした人たちが増えていけば、社会全体もより幸せなものになっていくと信じているのです」
※本記事は2019年2月25日に公開しました。肩書などは当時のものです。
■ 社会学者・鈴木謙介先生 インタビュー一覧「20XX年の幸福論」
第1回:“頭が良い”の定義とは? 子どもの知性を伸ばすために親が知っておくべき2つのこと
第2回:“ひとりの天才”をめざすよりも大切なこと。“みんなで協力”できる力の絶大な価値
第3回:スマホ依存の子どもには特徴がある。“異世界の多様な人々”との適切な関わり方
第4回:努力しても“いい仕事”には就けない。子どもは極端な格差社会にどう立ち向かうべきか
【プロフィール】
鈴木謙介(すずき・けんすけ)
1976年生まれ、福岡県出身。関西学院大学准教授。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター客員研究員。専攻は理論社会学。ネット、ケータイなど、情報化社会の最新の事例研究と、政治哲学を中心とした理論的研究を架橋させながら、独自の社会理論を展開している。現代社会の様々な問題についてマスコミでの発信も多い。サブカルチャー方面への関心も高く、2006年より、TBSラジオで『文化系トークラジオ Life』のメインパーソナリティをつとめている。著書に、『カーニヴァル化する社会』(講談社)、『かかわりの知能指数』(ディスカヴァー)、『ウェブ社会のゆくえ』(NHK出版)他多数。
【ライタープロフィール】
辻本圭介(つじもと・けいすけ)
1975年生まれ、京都市出身。明治学院大学法学部卒業後、主に文学をテーマにライター活動を開始。2003年に編集者に転じ、芸能・カルチャーを中心とした雜誌・ムックの編集に携わる。以後、企業の広報・PR媒体およびIR媒体の企画・編集を中心に、月刊『iPhone Magazine』編集長を経験するなど幅広く活動。現在は、ブックライターとしてもヒット作を手がけている。