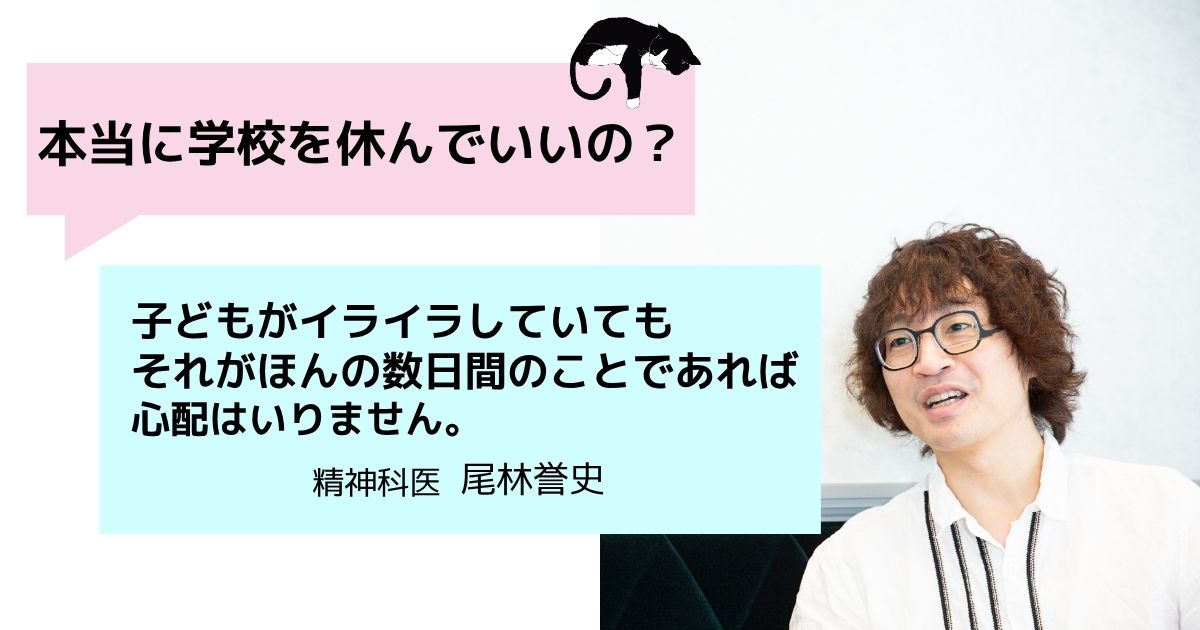現在の小中学生はメンタル不調という深刻な問題にさらされています。その背景にはいったいなにがあるのでしょうか。産業医として活動する精神科医の尾林誉史先生は、「コロナ禍」をその要因に挙げます。事実、文科省の調査でも、コロナ禍以降に不登校児童生徒数が大きく増加していることが明確に示されており、2018年に約16万4500人だった不登校児童生徒数は、2023年には約34万6500人と倍増しているのです。コロナ禍の影響、子どもたちが出すメンタル不調のサイン、親としてとるべき行動を教えてもらいました。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人(インタビューカットのみ)
目次
コミュニケーション能力を育む機会を奪われた子どもたち
子どもたちのメンタルヘルスにおける問題が増加中だと言われますが、さまざまな要因が考えられるなか、コロナ禍の影響はかなり大きいと私は見ています。いまの小中学生の子どもたちは、まさにコロナ禍に幼少期を過ごしました。そのために、コミュニケーション能力をうまく育むことができなかった子どもが多いのです。
コミュニケーション能力は、友だちと相談しながらルールを決めて遊ぶ、誰かがルールを破ったときにはどうすればいいかを相談する、意見がぶつかったときに折り合いをつける、グループ遊びのなかで協力し合う、あるいは喧嘩をして腹を立てたり落ち込んだり、仲直りをするといった、他者との多種多様な関わりのなかで育まれていくものです。
ところが、当時は「外に出てはいけない」「複数人で遊んではダメ」と言われる状況でしたから、きょうだいがいる子どもならまだしも、多くの子どもたちは、放課後や休日でも友だちと外で元気に遊ぶことができず、ひとり、家のなかで過ごすことがほとんどだったはず。そのため、人との関わりが大きく制限され、コミュニケーション能力を伸ばす機会を奪われてしまったのです。
でも、コロナ禍が終息すると、学校や塾などで友だちや先生とのコミュニケーションが求められるようになりました。その急激な変化のなか、コミュニケーション能力をうまく育むことができていない子どもは、友だちの気持ちがわからない、グループ活動で孤立してしまう、先生に質問や相談ができないなど多くの問題にぶつかります。そのような流れから、メンタル不調におちいってしまうこともあるというわけです。

いまの子どもにとって学校を休むのは「普通の選択肢」
子どものメンタル不調は、たとえば不登校などのかたちで顕在化します。しかし、現在の不登校は、かつての不登校ほどわかりやすいものではなく、ムラがあるという点で注意が必要だと考えます。
文科省の定義に準ずれば、不登校とは「年間30日以上の欠席」を意味します。文科省の調査では、不登校にあたる児童生徒のうち半数以上が年間90日以上欠席していることがわかっています。ただ、それほど多くの欠席はしないものの、「元気に学校に行っているからうちの子は大丈夫と思っていたら、突然『今日は行きたくない』ということもあって心配になる」といった悩みを抱える親も多いようです。
根性論がまかり通っていた50代などの世代であれば、「発熱などはっきりした理由もないのに学校を休む」というのは強い罪悪感を覚える行為でした。しかし、状況は大きく変わったといわざるを得ません。いまの子どもにとって「大きな理由もないのに学校を休む」ということは、至って「普通の選択肢」なのです。
その背景には、「情報検索が容易過ぎる」という現代社会の特性があるように思っています。子どもたちに限らず若い社会人でもそうかもしれませんが、なにかわからないことや知りたいことがあると、すぐに生成AIに質問をしたり検索したりします。そうして「なんとなく正解らしきもの」がすぐに手に入るので、時間をかけて自分の心と向き合い、じっくり考えるということがなくなります。
その結果、「本当に学校を休んでいいのか?」としっかり考えることもなく、「今日は苦手なグループ学習があるから行かなくていいや」「なんとなく体調が悪いから休もう」というように、安易に学校を休む選択をしてしまうのではないでしょうか。

忙しいなかでも家庭では穏やかにゆったりと過ごす
子どもにそういった行動が見られる場合、親はもちろん心配になるでしょう。しかし、「なにか悩んでいることがあるの?」と直接聞いてみても、これまたコミュニケーション不全からか、子どもたちは自分の気持ちを素直に話すことができないケースが多いようです。
そこで親がとるべき行動は、子どもをじっくり観察することです。メンタルの不調は、たとえば笑顔や口数が減る、ぼーっとしている時間が増えるなど、「生気のなさ」として表れます。あるいは、些細なことでイライラするなど、親からすると「どうしてそんなことで怒るの?」と思う場面が増えるというケースも目立ちます。
ただし、子どもにそうした様子が見られるからといって、すぐに専門医に相談しようと考えるのは拙速に過ぎます。大人だって、なにか落ち込むような出来事があって2、3日立ち直れないといったことはあるものです。衝動買いや暴飲暴食をして憂さ晴らしをしたくなることもあるでしょう。そういった気持ちは人間にとってごく自然なものであり、一過性の感情のうねりに過ぎないのです。
ですから、「持続期間」に注目してみましょう。子どもがイライラしていても、それがほんの数日間のことであれば特段、心配はいりません。ただし、「どうも生気がない」「ちょっとしたことで怒る」と感じることが半月から1か月に及ぶようなら、通常の精神状態ではないかもしれませんから、専門医に相談することを考えてください。
ただ、そのように子どもを観察すること以上に、親自身のふだんの振る舞いについて考えてほしいのです。みなさんの生活を振り返ってみたとき、家族一緒にゆっくり食事をしたり、子どもやパートナーと丁寧に会話したりするといったことができているでしょうか? 「そんなあたりまえのこと?」と思うかもしれませんが、多忙である現代の親には、そうできていない人もたくさんいるのが実情です。
そうしたなか、子どもが勇気を出して「ちょっと聞いてほしいことがあって……」と悩みを打ち明けようとしたのに、「いま忙しいからあとにして!」なんていってしまったら目もあてられません。
子どもたちは、親から無償の愛を受け取るなかで、自分から心を開く、人を受け入れるといったことを学んでいきます。親をいちばんのロールモデルとして成長する子どものために、せめて家庭のなかでは穏やかにゆったりと過ごすことを考えてほしいと思います。

『精神科医が教える 休みベタさんの休み方』
尾林誉史 著/すばる舎 (2025)
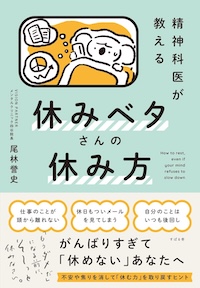
■ 精神科医・尾林誉史先生 インタビュー一覧
第1回:【不登校34万人】小中学生が出す“心のSOS”──親が気づくサインとは?
第2回:自己主張できる子は強い? 精神科医が語る「いい子」が抱える見えないリスク
第3回:人と同じじゃないと不安――「正解ばかり探す子」に精神科医が伝えたいこと
【プロフィール】
尾林誉史(おばやし・たかふみ)
1975年4月29日生まれ、東京都出身。精神科医、産業医。VISION PARTNERメンタルクリニック四谷院長。株式会社産業医代表取締役。東京大学理学部化学科卒業後、株式会社リクルートに入社。社内外や年次を問わず発生するメンタル問題に多数遭遇。解決に向けて付き添うなかで目にした産業医の現状に落胆するも、とあるクリニックの精神科医の働き方に感銘を受ける。2006年、産業医を志して退職。退職後、弘前大学医学部に学士編入。産業医の土台として精神科の技術を身につけるため、東京都立松沢病院にて初期臨床研修修了後、東京大学医学部附属病院精神神経科に所属。現在はnote、面白法人カヤック、ジモティーなど23社の企業にて産業医およびカウンセリング業務を務める他、メディアでも精力的に情報発信を行っている。著書に『働く人のためのメンタルヘルス術』(あさ出版)、『がんばらない めんどくさくない 人間関係を築くコツ』(ナツメ社)、『先生、毎日けっこうしんどいです。』(かんき出版)などがある。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。