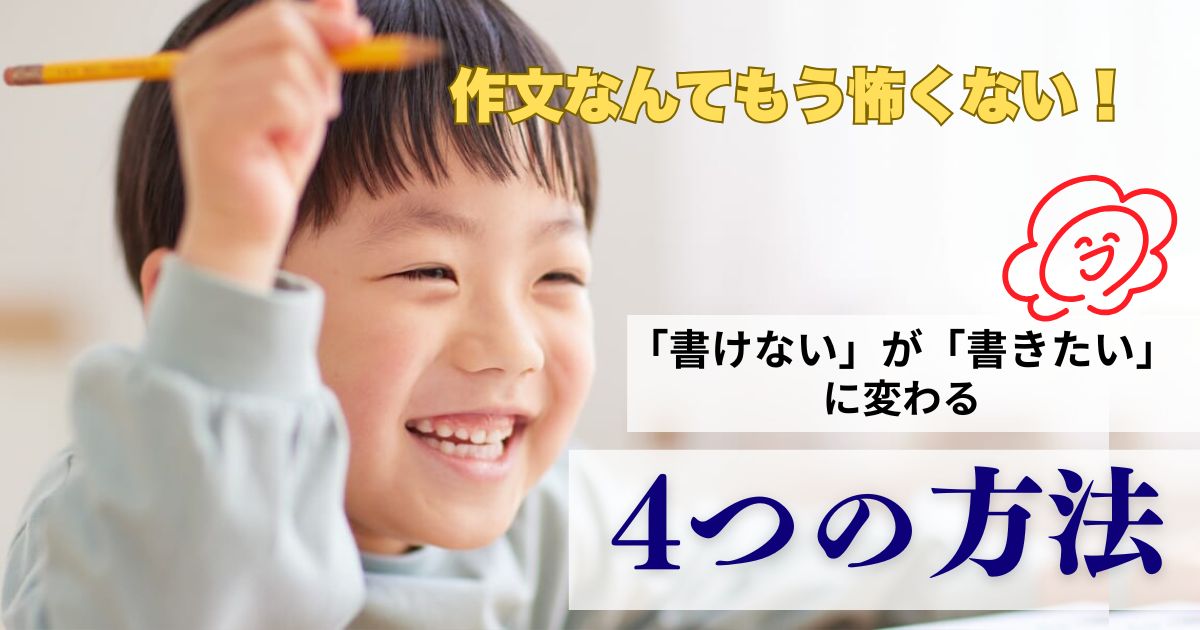10月は、運動会や遠足、社会科見学など、子どもたちの心が動く行事が盛りだくさん。そして学校では、その体験を題材にした作文の課題が次々と出る時期です。
「うちの子、作文が苦手で……」と感じている方もご安心を!
この記事を読めば、子どもが「書けない」から「書きたい!」に変わるヒントがすぐに見つかります。
読んだあとにはきっと、「作文なんて、もう怖くない!」と思えるはずです。
目次
作文力アップ術1:「書くことが楽しい!」と思わせる
子どもが作文を苦手とする大きな理由は、書くことの楽しさを味わえていないから。そのため子どもは、書くことに対して「つらさ」ばかりを感じてしまい、書くこと自体に抵抗をもってしまうのです。まずは、作文力うんぬんの前に、「書くことって楽しい!」と思わせることから始めてみましょう。
【「作文って楽しい!」と思わせるコツ】
コツ1:まずは「書きたい!」と思えるテーマを一緒に探す
「今日一番楽しかったこと」「おもしろかったテレビ」など、子ども自身が “話したくなる” 話題を選びましょう。
コツ2:親子で “物語リレー” をする
親が1文書いたら、次は子どもが1文書く。想像を膨らませながらストーリーをつなぐ遊びです。創造力が育ち、書くハードルも下がります。
コツ3:書く前に口で話す時間をつくる
文章を書く前にまず話して整理することで、構成力が育ちます。親が「それでどう思った?」と聞いてあげるのがポイントです。
書く喜びを知った子は、作文を好きになり、力をぐんぐん伸ばしていきます。作文力を伸ばすことで得られるメリットは、論理的思考力や表現力、伝える力など多岐にわたるため、コミュニュケーション能力の向上や社会生活の充実度にも直結します。

作文力アップ術2:書くことが好きになる言葉がけを!
「作文が苦手」「嫌い」という気持ちを強めてしまうのは、周囲の大人の言葉かけが大きく影響します。子どもの作文を否定的に評価してしまうと、子どもは「自分自身が否定された……」と受け取ってしまい、書く意欲を失うこともあるため注意が必要です。以下の言葉がけを意識してみてくださいね。
【書くことが好きになる “親の言葉がけ” のコツ】
コツ1:「上手に書けたね」より「ここがいいね」と具体的にほめる
「文のはじめが工夫されてるね」「気持ちが伝わったよ」など、具体的な言葉で評価すると、子どもは次も挑戦したくなります。
コツ2:失敗を “発見” として受け止める
誤字や言い回しの間違いを見つけたら、「新しい表現を見つけるチャンスだね」と伝えましょう。ミスを恐れずに書けるようになります。
コツ3:書いたあとに “読んでもらう相手” を意識させる
「おじいちゃんに読んでもらおう」など、伝える相手を決めて書くと、言葉の選び方が自然に磨かれます。
親が心がけるべきベストな対応は「認める・受け入れる・ほめる」の3つ。作文には、子ども自身の体験や思いが詰まっています。未完成であっても、まずは「書けた」ことを大きく認めてあげましょう。
日頃から肯定的なフィードバックを受けている子は「何を書いても大丈夫」と安心し、自信をもって表現できるようになります。その積み重ねが作文好きにつながり、文章力を大きく伸ばしていくのです。

作文力アップ術3:インタビューごっこで考えを言葉にする
作文は、頭のなかのぼんやりした考えを言葉にする作業。その過程で「なぜそう思ったのか」「どんな気持ちだったのか」と問いかける力が必要となります。「インタビューごっこ」で、考えを言葉にする作業を練習してみましょう。
【インタビューごっこのコツ】
コツ1:おうちで “記者になりきる” 遊びをする
「どうしてそう思ったの?」「どんな気持ちだった?」と質問し合うインタビューごっこで、考える力と説明力を育てましょう。
コツ2:録音して “自分の声” を聞く時間をつくる
自分の話を聞き返すことで、「この言い方だと伝わりやすい」「ここをもっと説明したい」など、文章表現のヒントが見えてきます。
コツ3:新聞や本のインタビュー記事を親子で読む
プロの質問や答え方を参考に、「どうしてこの質問をしたのかな?」と考える習慣をつけると、構成力が高まります。
親が記者役になり、子どもの経験や感想を質問するという「インタビューごっこ」を通して、子どもは自分の気持ちや考えを整理し、作文に生かせる材料を見つけていきます。注意点は、「誘導尋問をしない」ことと「答えを否定しない」こと。子ども自身の素直な言葉を引き出せれば、確実に作文力アップにつながるでしょう。

作文力アップ術4:「推敲」の習慣をつける
作文力を高めるうえで欠かせないのが「推敲(すいこう)」の習慣です。書きっぱなしではなく、時間をおいて読み直す、音読して耳で確認するなどの工夫で、誤字脱字や表現の改善点に気づけます。
【書いたものをブラッシュアップするコツ】
コツ1:推敲の前に “声に出して読む” 習慣をつける
声に出すことで、文のリズムや言葉のつながりの違和感に気づけます。「ここ、言いにくいね」と気づけたらOKです。
コツ2: “赤ペンチェック” を一緒にする
親が修正するのではなく、「ここ、どう直したい?」と本人に尋ねながら、自分で考える時間を大切に。自己修正力が育ちます。
コツ3: “ほめメモ” を残す
作文のなかでよかった部分を親がメモしておき、次に書くときに「前回はここがよかったね」と伝えると、自信が積み重なります。
「書いて終わり」ではなく「よりよくする」姿勢を身につけることで、文章力はぐんぐん成長していくでしょう。

よくある質問Q&Aーー子どもの作文の悩みを解決!
Q1. 子どもが作文を書くのを嫌がるとき、どうすればよいですか?
A. 無理に書かせず、会話のなかで気づいたことをメモするなど「言葉をためる」習慣から始めましょう。
Q2. 作文を直すときに、ダメ出しは必要ですか?
A. 最初は認めてほめることを優先し、改善点は「こうするともっとよくなるね」と一緒に考える形で伝えましょう。
Q3. 家庭でできる文章力アップの習慣はありますか?
A. 読書後の感想を一言話す、日記をつける、インタビューごっこをするなど、日常生活で「言葉にする」機会を増やすことが効果的です。
***
子どもの文章力は、身近な体験を言葉にすることで伸びていきます。そして、「楽しさを味わう」「認めてほめる」「自問自答する」「推敲を繰り返す」といったプロセスが、自信と表現力を育てます。文章力は国語の成績を上げるだけでなく、自己肯定感やコミュニケーション力を支える一生ものの力。日常の小さな工夫から、子どもの未来を豊かにする文章力を育んでいきたいですね。
(参考)
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|作文能力を伸ばすことで得られる5つのメリットーー「書く楽しさ」と「書く喜び」が自信につながる
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|親の誤った声がけが、子どもの作文力の芽を摘む?ーー「作文好き&得意」な子どもと「自己肯定感」の関係
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|子どもの作文力を育む「インタビューごっこ」のススメーー文章作成に必要な「自問自答」の習慣づくり
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|【親子でとりくむ読書感想文 書き方レッスン】第5回:質問と答えをセットにしてみよう
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|【親子でとりくむ読書感想文 書き方レッスン】第7回:推敲の仕方