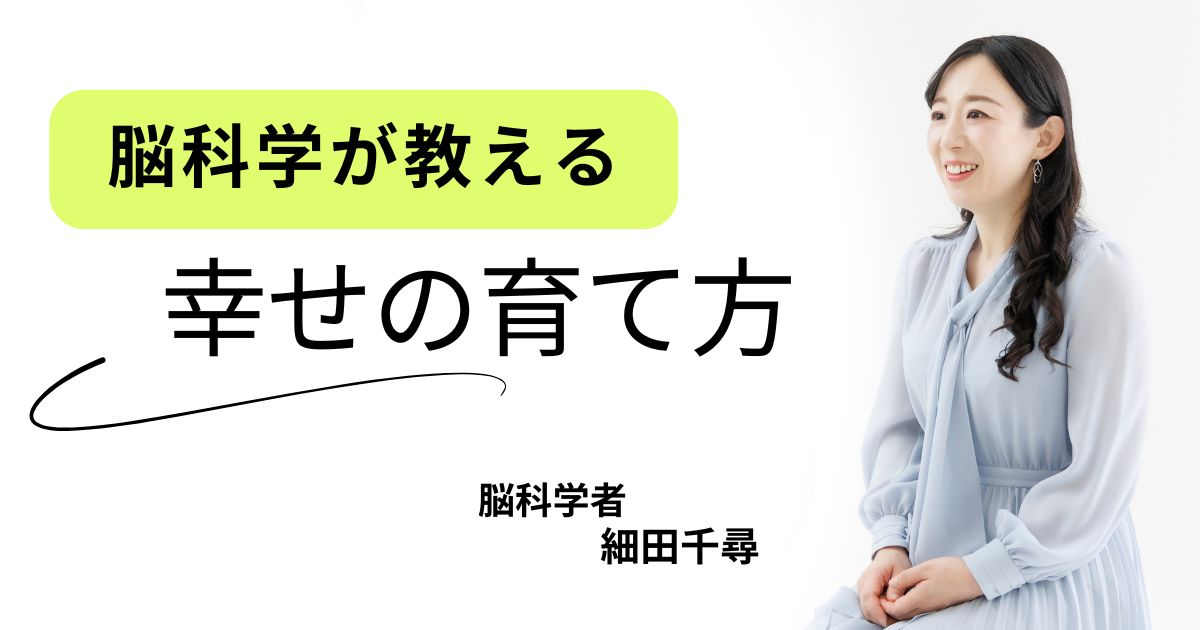少子化が進むなか、ひとりの子どもに対しての教育熱はますます高まっています。「子どものために」と考え、いわゆる早期教育をしている家庭が増えているのが実情です。しかし、『幸せを手にできる脳の最適解 ウェルビーイングを実現するレッスン』(KADOKAWA)を上梓した、東北大学准教授で脳科学者の細田千尋先生は、「早期教育が子どもを幸せから遠ざけてしまっているケースもある」と警鐘を鳴らします。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/塚原孝顕(インタビューカットのみ)
目次
子どもの幸せに欠かせないのは、「自分の意見を聞いてもらえる場」
私は、専門とする脳科学を応用しながら、「ウェルビーイング」についての研究もしています。ウェルビーイングを「幸せ」と同じようなものだと認識している人も多いと思いますが、厳密には異なります。
幸せは、一般的には感情を指す言葉です。一方のウェルビーイングは、たとえば健康な体、安全性が担保されていること、家族や他人との良好な関係など、いわば「インフラ」に満足できる環境が整っている状態を意味します。もちろん感情もひとつのインフラといえますから、ウェルビーイングとは、幸せを含むより広範で包括的な概念なのです。
1990年代頃からは、「チャイルドウェルビーイング」の研究も進んできました。子どもたちにとっては、先に挙げたような要素のほか、たとえば適切な教育を受けられる環境といったものも重要なインフラです。それらが満たされてはじめて、子どもの幸せは実現できるのです。
しかしここで注意したいのは、私たち大人と同じように幼い子どもが幸せを感じられるかというと、そうではないことです。脳が未発達の子どもは、自分の感情に対して「これは幸せだ」といった具合にラベリングすることができません。そして、子どもにとっては置かれている環境が世界のすべてであり、しかもその環境が恵まれているのかそうでないのか判断することはとても難しいことです。
ただし、そうした現実のなかでも、もちろん子どもも幸せを感じています。そのために不可欠なのは、身を置く環境のなかに「自分の意見を聞いてもらえる」という場があるか否かです。その環境が、子どもの「これをやりたい」という積極性や自主性につながり、ひいては「自分は自分のままでいいんだ」「自分には価値がある」と思える感覚である自己肯定感や幸せにもつながっていくのです。

なにかができるようになることは、早期教育の副産物
わが子の幸せを願わない親はいませんよね。ただ、親としてあたりまえのことなのかもしれませんが、「子どもに幸せになってほしい」ということにとどまらず、「勉強もスポーツも得意になってほしい」「将来的に有名大学に進学してほしい」など、その願いはどんどん広がってしまうものです。
そうして、早期教育をはじめる家庭もたくさんあります。そこで忘れてはならないのは、先にお伝えした、子どもにとって「自分の意見を聞いてもらえる」と思える場があるかどうかです。
子ども自身が幸せを感じるためには、「自分の意見を聞いてもらえる」と思えることが欠かせません。早期教育の塾や習い事などでいえば、子ども自身が「やりたい」「頑張りたい」と思えることである必要があります。その感情があるからこそ、子どもは多少つらいことも我慢したり気持ちをコントロールしたりしながら努力を続け、「前よりもちょっとだけできるようになった!」という達成感を味わい、成長していくのです。
対して、子ども自身はそれほどやりたくもないのに、親のエゴで「これをやらせたい!」「これをやりなさい!」とやることを与えたらどうなるでしょう? そんなことでは、いわゆる「いい子」として親の願望に従うだけの状態となります。興味がないために、自分ではうまくできたのかそうでなかったのかもよくわからないけれど、親から「できるようになったね」とほめられ、「じゃあ次はこれをやってみて」と言われてまたやりたくないことをやる……そんなループに陥ります。
たしかに、それでスキル自体は高まっていくかもしれません。けれども、その子が幸せを感じているかというと、そうではない可能性が高いでしょう。能力自体は高いのに、幸福感や自己肯定感が低い子どもが多いという背景には、このようなことがあると考えます。
早期教育の目的は、「子どもがなにかをできるようになること」ではありません。子どもが自らの意思でやりたいことを選択し、失敗をしながらも「今度はこうしてみよう」と工夫を重ねるような自主性を育んでいく、自分をコントロールするすべを学んでいくことこそ、早期教育の目的であると思います。なにかができるようになるというのは、その結果としてついてくる副産物に過ぎないのです。

「子どもをコントロールし過ぎない」ことが最重要
繰り返しになりますが、子どもを幸せから遠ざける子育てをしないためには、子どもにとって「自分の意見を聞いてもらえる」と思える場を設けることに尽きます。関連して、親の子どもに対するかかわりでいえば、「コントロールし過ぎない」ことが最重要です。
私は、チャイルドウェルビーイングの研究のなかで、一般の親子のみなさんに協力してもらう実験も数多く行なっています。そのひとつに、さまざまな知育玩具を置いた部屋を用意して、親御さんに「お子さんの好きに遊ばせてください」とお願いするというものがあります。
すると、「お子さんの好きに」と伝えているにもかかわらず、教育熱心な親御さんのなかには、「これで遊んでみたら?」と、その子どもにとってはハイレベルな知育玩具をすすめる人もたくさんいるのです。
もちろん、その子にとってはハイレベルな知育玩具ですから、うまくできません。すると今度は、「こうしたらいいじゃない」とすぐに答えを伝え、わが子をコントロールしようとするのです。
言われたとおりにやれば、その子も時間をかけながらもうまくできるようになります。ですが、その子自身が自ら考えて工夫するといったことが一切ありません。つまり、子どもが達成感を味わい、自主性や自己肯定感を育むチャンスを他ならぬ親が奪ってしまっているのです。
本来であれば、子どもが失敗したときに親はどうすべきでしょうか? 子ども自身が「うまくやりたいのに、どうして失敗したのかわからない」と言うなら、「本当はどうしたかったの?」「だけど、さっきはこうしたよね」「今度はどうしたらいいと思う?」というように、親子一緒に振り返って考えるようなことはやってもいいでしょう。ですが、基本的には、コントロールしようとせず、子どもを信じてその意思を大切にしてあげてほしいと思うのです。

『幸せを手にできる脳の最適解 ウェルビーイングを実現するレッスン』
細田千尋 著/KADOKAWA(2023)
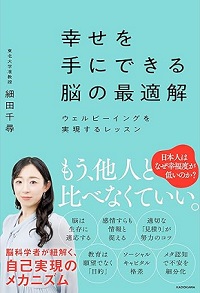
■ 脳科学者・細田千尋先生 インタビュー一覧
第1回:早期教育が“幸せ”を奪う? 脳科学でわかった、「親の期待」が子どもを苦しめるメカニズム
第2回:癇癪もわがままも“異常”じゃない──脳科学者が教える「イヤイヤ期」の本当の意味
第3回:「こうしてほしい」はあなたのエゴ。コントロール欲を手放すことからはじまる【幸せな子育て】
【プロフィール】
細田千尋(ほそだ・ちひろ)
医学博士・認知神経科学者・脳科学者。東北大学加齢医学研究所及び、東北大学大学院情報科学研究科准教授。東京医科歯科大学大学院医歯学総合博士課程修了。国立精神・神経医療研究センター流動研究員、(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)専任研究員、東京大学大学院総合文化研究科特任研究員、JSTさきがけ専任研究員などを経て、現職。仙台市教育局「学習意欲」の科学的研究に関するプロジェクト委員会委員、日本ヒト脳マッピング学会委員などを務める。著書に『脳科学が教える 一瞬で心をつかむ技術』(PHP研究所)、『幸せを手にできる脳の最適解 ウェルビーイングを実現するレッスン』(KADOKAWA)がある。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。