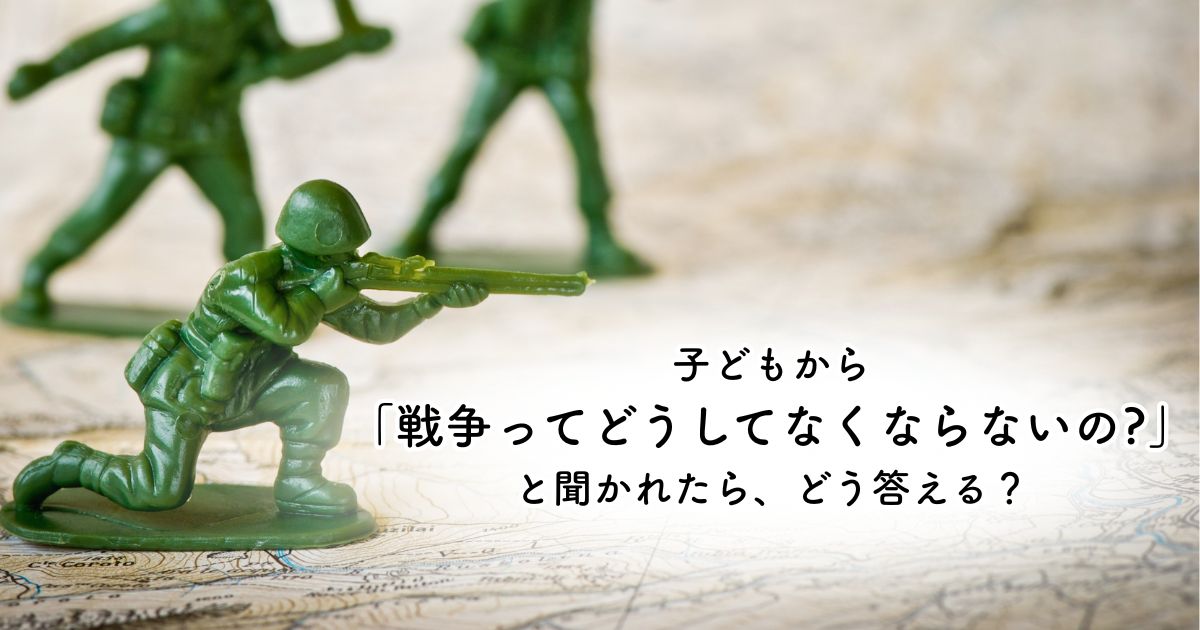テレビやスマートフォンから流れてくるニュースで、「戦争」「停戦」「和平交渉」という言葉を耳にしない日はほとんどありません。世界のどこかで紛争が起こり、多くの人々が苦しんでいる現実があります。
子どもたちも、学校での会話やSNS、ニュース映像を通じて、戦争という言葉や映像に触れています。そんななかで、子どもから「ねえ、どうして戦争ってなくならないの?」と聞かれたとき、多くの親御さんが言葉に詰まってしまうのではないでしょうか。
「正しい答えを言わなければ」「子どもを傷つけないように説明しなければ」──そう思うと、つい「難しいね」と話題を変えてしまったり、曖昧な答えでごまかしてしまったりすることもあるかもしれません。
じつは、この問いに「完璧な答え」を用意する必要はないのです。大切なのは、親自身が「共に考える姿勢」をもつこと。一緒に悩み、一緒に考えることこそが、子どもにとって最も価値ある学びになります。
目次
戦争の原因は「けんかの延長線」?
子どもに戦争を説明するとき、最も理解しやすいのは「国どうしのけんか」というたとえです。戦争は、国家間の利害対立が武力衝突に発展したものと捉えることができます。
戦争が起こる主な理由は、大きく分けて3つあります。
① 資源や土地をめぐる争い
石油や水、食料、豊かな土地など、限られた資源を「自分たちのものにしたい」という気持ちから争いが始まることがあります。歴史的に見ても、資源の獲得や領土拡大を目的とした紛争は数多く存在してきました。
国連の報告によれば、過去60年間の紛争の40%以上が天然資源と関連しており、資源をめぐる争いは現代の紛争の主要因の一つとなっています。*1
② 考え方や宗教の違い
「こうあるべきだ」という価値観や、信じる宗教が違うことで、お互いを理解できなくなることがあります。文化的・宗教的な違いが対立の火種となり、それが武力衝突につながるケースも少なくありません。
③ 自分の国を守りたい気持ち
「攻められそうだから先に守らなきゃ」という恐怖心や、「自分たちの国を守るためにはやむを得ない」という防衛意識も、戦争の原因になります。
💬 話し方のヒント
「たとえば、同じクラスの子と意見が違うときもあるよね。お互いに『自分が正しい』って思っていると、けんかになることがある。それが国と国になると、とても大きなけんかになることがあるんだよ」

「やめたいのにやめられない」──人間の心理も関係している
「じゃあ、なんでやめないの?」──子どもからこう聞かれたとき、どう答えますか?
じつは、戦争が長引く背景には、人間の心理的なメカニズムも深く関わっています。行動経済学では、これまで投資した時間や労力を無駄にしたくないという心理を「サンクコスト効果」と呼びます。*2
戦争においても、「ここまで犠牲を払ったのだから、負けるわけにはいかない」「これまでの努力を無駄にできない」という心理が働き、引き返すことが難しくなってしまうのです。
さらに、政治的な理由も絡んできます。権力を握っている人が「戦争をやめる」と決めれば、「弱腰だ」と批判されたり、自分の立場が危うくなったりすることがあります。お金や面子、国内外の複雑な関係性が絡み合って、やめる決断はますます難しくなります。
💬 話し方のヒント
「人は、自分がしたことを無駄にしたくないと思うんだ。でもね、本当の強さって、『間違いに気づいたときに立ち止まれること』なんだよ。勇気を持ってやめる、っていうのも大事な選択なんだよ」
「平和」は “戦争がない状態” ではない
多くの子どもは、「平和=戦争がない静かで安全な状態」だと思っています。でも、本当の平和はそれだけではありません。
ユネスコ憲章の前文には「戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」と記されています。*3 また、ユネスコは「平和の文化」という概念を提唱しており、単に戦争がないことではなく、正義、民主主義、人権の尊重、寛容、対話が実現された状態を平和としています。*4
現代平和学の第一人者であるヨハン・ガルトゥング氏は、「単に戦争がない状態」を「消極的平和」、「貧困や差別などの構造的暴力もない状態」を「積極的平和」と定義しました。*5
💬 話し方のヒント
「戦争がないだけじゃなくて、みんなが『こわくない、悲しくない、安心して暮らせる』と思える社会が、本当の平和なんだよ」

「戦争をなくす」よりも、「平和を育てる」ことを伝える
「戦争をなくすにはどうしたらいいの?」という問いは、子どもにとってあまりにも大きく、遠い話に感じられます。でも、「平和をつくる」ことなら、今日からでも、身近なところから始められます。
たとえば——
- 友達と意見が違ったとき、怒らずに話し合ってみる
- 困っている人がいたら、声をかけてみる
- 自分と違う考えの人の話も、まず聞いてみる
こうした小さな行動が、「平和の種」を育てることにつながります。
💬 話し方のヒント
「友達と意見が違ったときに、けんかじゃなくて話し合いで解決できたら、それも『平和をつくる』一歩なんだよ。世界の平和も、こういう小さなことの積み重ねから始まるんだ」
***
戦争や平和について、「正解」はありません。専門家でも意見が分かれる、とても複雑で難しいテーマです。
だからこそ、親が「どう答えるか」よりも、「どう一緒に考えるか」が大切になります。
1
「もし自分がその国の人だったら、どう感じるかな?」
相手の立場に立って考えることで、共感力が育ちます。
2
「けんかをしないで解決する方法って、どんなものがあるかな?」
対話、交渉、第三者の仲介など、平和的解決の方法を一緒に考えてみましょう。
3
「自分の周りで『平和じゃないな』と思うことはある?」
身近な不公平や争いに気づくことが、平和を考える第一歩です。
(参考)
*1 United Nations|Conflict and natural resources
*2 十文字学園女子大学|サンクコスト効果
*3 文部科学省|国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章)/The Constitution of UNESCO
*4 公益社団法人日本ユネスコ協会連盟|平和の文化に関する宣言
*5 ヨハン・ガルトゥング(2003), 『ガルトゥング平和学入門』, 法律文化社.