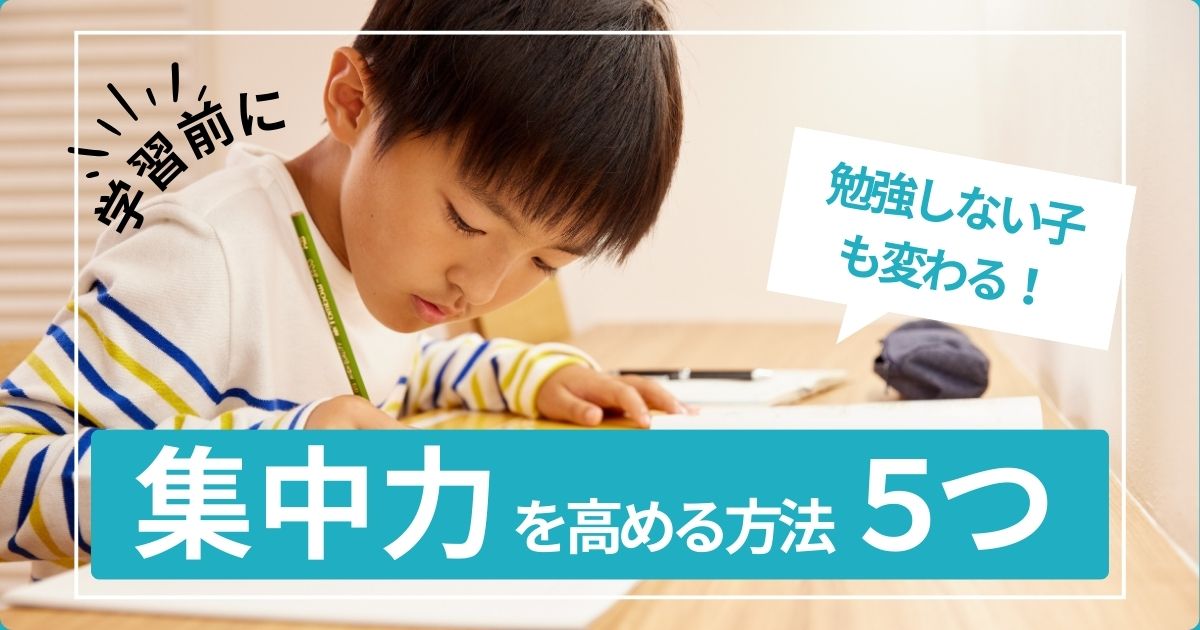宿題の時間になっても、机に座ったまま鉛筆を回していたり、急に「のど乾いた!」と席を立ったり……。親としては「早く始めて!」と言いたくなりますよね。でもじつは、子どもが勉強に入れないのは “やる気がない” からではなく、脳が集中モードに切り替わっていないだけかもしれません。
そんなときに効果的なのが、勉強を始める前の5つの準備ワザです。ほんの数分の工夫で、子どもの集中スイッチが入りやすくなり、「やっと始めた……」から「自然に始められる!」に変わります。今回は、その5つの方法を科学的な根拠やデータを交えて紹介していきます。
目次
学習前に “集中モード” に切り替える 5つの準備ワザ
子どもが勉強を始められないのは、脳が「何をすればいいか分からない」「まだ準備ができていない」と感じているだけかもしれません。今回紹介する5つのワザは、どれも脳科学や心理学の研究に基づいたものです。
どれも特別な準備や長い時間は必要ありません。学習前に子どもの “集中モード” を高めるためには、以下の5つのワザがおすすめです。
- 「今日のゴール」を声に出す
- 視覚トリガーを置く
- 軽いストレッチや深呼吸
- 前回の学習を少しだけ思い出す
- 小さなごほうびをすぐに与える
では1つずつ見ていきましょう。
ワザ① 「今日のゴール」を声に出す——脳の優先順位を決める
「今日は何をやるの?」がはっきりしないと、子どもは手をつけにくいもの。そこで勉強前に、ゴールを声に出す習慣をつけましょう。
- 例:「15分で計算ドリルを3ページやる!」
脳には RAS(網様体賦活系) という情報のフィルターがあり、言葉にした目標を「大事なこと」と認識しやすくなります。さらに心理学の研究でも、具体的な目標は「頑張れ」という声かけよりずっと効果的だとわかっています。 口に出すのが照れくさければ、ふせんに書いて親の前で短く読み上げ→机の見える所に貼るだけでも、始動の合図として十分に機能します。
また、脳科学者の篠原菊紀氏によれば、子どもが勉強に集中できる時間はだいたい15分程度。だからこそ、「今日のゴール」は15分以内で達成できる小さな目標に設定するのがポイントです。
ワザ② 視覚トリガーを置く——無意識の背中押しを仕込む
机に教材を出していても、気持ちが勉強に向かないことってありますよね。そんなときは、視覚のきっかけ(トリガー)を置くのがおすすめです。
- 例:今キーワードふせん、図形の図、プリント、学習ポスターなど
これは心理学でいうプライミング効果。関連するものを目にすると、自然とその内容に意識が引き寄せられるのです。ただし、置くのは1〜2点だけ。刺激が多すぎると逆に注意が散ってしまいます。勉強を始めたら、そのトリガーは裏返す/横にずらすなどして視界のノイズを減らすと、集中が持続しやすくなります。

ワザ③ 軽いストレッチや深呼吸——脳を”起動”する
「やる気が出ない……」というときほど、体を少し動かすのが効果的。ジャンプを10回、肩をぐるっと回す、3秒かけて深呼吸などで十分です。
イリノイ大学の実験では、軽い20分の軽いトレッドミル歩行後に9〜10歳の子どもたちの学力テストや注意力テストのパフォーマンスが向上したという報告もあります。体を動かすと血流が良くなり、脳の前頭前野(集中を司る部分)が働きやすくなるのです。家でもできるように、「1分程度の簡単なルーティン(深呼吸→肩回し→軽く足踏み)」など短い決まりにしておくと、毎回迷わずスッと始められます。

ワザ④ 前回の学習を30〜60秒だけ思い出す——”想起”で記憶を強める
新しい勉強を始める前に、前にやったことを一瞬だけ思い出すようにしましょう。
- 親「昨日は何をやったっけ?」
- 子「かけ算の8の段!」
- 親「じゃあ、思い出して言ってみよう」
この “思い出そうとする行為” 自体が、記憶を強める力をもっています。脳科学では 想起練習(リトリーバル・プラクティス) と呼ばれ、ワシントン大学の研究では、テキストを繰り返し読むよりも、思い出そうとする練習の方が長期記憶の定着に効果的だったとされています。間違えてもOK。「思い出そうとしたこと」が大切です。仕上げに10秒だけノートを確認し、合っていれば丸、抜けがあれば一言メモを添えると “スタート燃料” になります。

ワザ⑤ 小さなごほうびをすぐに与える —— 「またやりたい」を育てる
人の脳は「報酬の予測」によって「次もやろう」と学習します。だから、小さくてすぐもらえるごほうびを用意すると効果的です。
- 例:15分集中できたら
✓チェックとハイタッチ/シール1枚/3分の好きタイム」
ごほうびは豪華である必要はありません。大事なのは「やったらすぐ返ってくる」こと。達成感と快感をセットにすると、「またやりたい」と思えるようになります。ごほうびは結果だけでなく「取り組み方」(静かに続けた/最初の一歩が速かった 等)にも結びつけると、よい行動が習慣として定着します。
また前述の篠原氏によれば、人間の脳には「一度やる気スイッチが入ったら行動に快感を感じる」という仕組みが備わっています。これは祖先がマンモスを追いかけ続けて生き延びてきた名残。つまり、最初の一歩さえ踏み出せば、あとは脳が勝手に続けたくなるのです。
***
子どもが勉強を始められないのは、脳が「何をすればいいか分からない」「まだ準備ができていない」と感じているだけです。
どれも特別な準備や長い時間は必要ありません。大切なのは、子どもが「自分でできた」と感じられる小さな成功体験を積み重ねること。親がサポート役として、始めるきっかけを一緒に作ってあげるだけで、子どもの学習習慣は確実に変わっていきます。
まずは1つ、今日から試してみてください。
(参考)
PMC – NCBI|The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in preadolescent children
The Source – Washington University in St. Louis|Practicing information retrieval is key to memory retention, study finds