子育てにおいて親を悩ますもののひとつが、いわゆる「イヤイヤ期」です。多くの人が、イヤイヤ期は子どもの発達に不可欠の時期だと認識しているはずですが、あらゆることに「イヤ!」と反発したり癇癪を起こしたりする子どもと冷静に向き合うことは簡単ではありません。そこでお話を聞いたのは、『幸せを手にできる脳の最適解 ウェルビーイングを実現するレッスン』(KADOKAWA)を上梓した、東北大学准教授で脳科学者の細田千尋先生。脳科学の観点から見た、イヤイヤ期における子どもとの向き合い方についてのアドバイスです。
構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/塚原孝顕(インタビューカットのみ)
目次
イヤイヤ期は、自我を確立して社会性を育む時期
「イヤイヤ期」とは、1歳後半から3歳頃までの、「子どもが自我(アイデンティティー)を確立して自己主張が強くなる時期」を指します。この時期の子どもは、あらゆることに「イヤ!」と反発したり、自分の思いどおりにならないと激しく泣き叫んだりすることが多く、保護者を悩ませることも少なくありません。
しかし、イヤイヤ期は子どもの発達段階において不可欠なものです。この時期の子どもは、自我を確立しようとすると同時に、「これはやりたくない!」「これはやりたい!」という「自分の意思というものはどこまで世のなかで認められるのか」ということを探っています。社会のなかで「こういうことは許される」「こういうことは許されない」と適切に判断する社会性を育んでいるというわけです。
つまり、もしイヤイヤ期がなかったとしたら、その子は「自分という人間は何者なのか」というアイデンティティーが確立できないために「こうしたい」という自己主張ができないだけでなく、社会とうまくかかわることができない人間になってしまいかねません。
ですから、親としては、まず「頭ごなしに否定しない」という姿勢がなによりも大切です。イヤイヤ期の子どもに対しては、親もつい感情的になってしまいますが、「この子は、アイデンティティーを確立している段階なんだ」「いままさに社会性を育んで成長している真っ最中なんだ」と思えば、その感情もうまくコントロールでき、むしろ喜びを感じられることだってあるかもしれません。
子どもが社会性を育んでいるという点でいうと、子どもの意思がどこまで世のなかで認められるのか、その「境界線」を教えることも親の役割だと考えます。極端な例を挙げれば、子どもが「道路に飛び出したい」といったところで、認めるわけにはいきませんよね? そうした場合であれば、「本当に危ないからこれは絶対にやっちゃ駄目」というように、子どもが境界線を見極める手助けをしてあげてほしいと思います。

子どもは感情のコントロールができなくてあたりまえ
先に、イヤイヤ期の子どもに対しては、親も感情的になってしまいがちだと述べましたが、子どもの感情コントロール能力の発達ともイヤイヤ期は密接に関連しています。イヤイヤ期の子どもは、自己主張が強くなる一方、自らの感情をうまくコントロールすることが難しく、癇癪を起こしたり反抗的な態度をとったりすることも多々あります。
しかし、子どもが自分の感情をうまくコントロールできないのは、脳の発達から見るとあたりまえのことと言えます。脳のなかで感情を生み出すのは「扁桃体」という部分なのですが、それらの感情を「前頭葉」という部分がコントロールしています。ところが、前頭葉の発達は脳のなかでもとくに遅いことがわかっているのです。
「脳の発達は10代で90%ほど完了している」ということを見聞きしたことがある人もいるかもしれません。実際、脳のサイズという意味ではこれは正しいといえます。ところが、機能的な成熟にはもっと時間がかかり、なかでも感情コントロールや意思決定、論理的判断といった高次な認知機能を司る前頭葉の成熟は、20代前半くらいまで続くのです。
つまり、大学生くらいの年齢でもまだまだ前頭葉は発達途中ということですし、それこそもっと年長の人でも自分の感情をコントロールできない人も少なくありません。それを思えば、そもそも脳が未発達の子どもに「感情をコントロールできるようになってほしい」と願うこと自体、無理なものなのです。

「日記」で子どもの癇癪の原因を探る
とはいえ、わが子があまりに感情のコントロールが苦手というのであれば、親としてはやはり心配になるでしょう。そういうケースでは、「日記」をつけることをおすすめします。
頭痛もちの人のなかには、「頭痛日記」をつけるように医師から指示されたという人もいると思います。頭痛日記は、頭痛の頻度や強さ、症状、発生状況などを記録するもので、主に頭痛の種類やその原因となるトリガーなどを特定するためのツールです。それと同じことをするわけです。
子どもが感情的になっているときはその場での対処に追われてしまい、「なぜそうなっているか?」というところまでには意外と意識が向きません。しかも、感情が爆発してしまうトリガーは、その瞬間にあるとは限らないから厄介です。たとえば、前日のお母さんとのやり取りのなかに原因があることも――。
そこで、子どもが感情的になったときの様子はもちろん、普段の子どもとのかかわりについても記録しておくのです。それらを積み重ねていくと、「あれ? この子が癇癪を起こすときは、だいたい前日にこういうかかわりをしているな」といったことが見えてきます。そうして、トリガーや対処法を探っていくのです。
そもそもの話ですが、なにかを我慢するなど、感情をコントロールするために必要な「ウィルパワー(意志力)」には一定期間に使える量に限度があるとも言われています。そうであるなら、子どもが感情的になるということは、どこかでなにかを我慢してウィルパワーを使い切っているからだとも考えられます。ですから、「無理になにかを我慢させていないかな?」という視点で子どもをしっかりと観察し、そうしたことを減らしてあげるということも親にできることではないでしょうか。

『幸せを手にできる脳の最適解 ウェルビーイングを実現するレッスン』
細田千尋 著/KADOKAWA(2023)
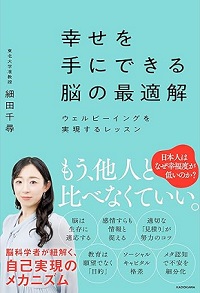
■ 脳科学者・細田千尋先生 インタビュー一覧
第1回:早期教育が“幸せ”を奪う? 脳科学でわかった、「親の期待」が子どもを苦しめるメカニズム
第2回:癇癪もわがままも“異常”じゃない──脳科学者が教える「イヤイヤ期」の本当の意味
第3回:「こうしてほしい」はあなたのエゴ。コントロール欲を手放すことからはじまる【幸せな子育て】
【プロフィール】
細田千尋(ほそだ・ちひろ)
医学博士・認知神経科学者・脳科学者。東北大学加齢医学研究所及び、東北大学大学院情報科学研究科准教授。東京医科歯科大学大学院医歯学総合博士課程修了。国立精神・神経医療研究センター流動研究員、(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)専任研究員、東京大学大学院総合文化研究科特任研究員、JSTさきがけ専任研究員などを経て、現職。仙台市教育局「学習意欲」の科学的研究に関するプロジェクト委員会委員、日本ヒト脳マッピング学会委員などを務める。著書に『脳科学が教える 一瞬で心をつかむ技術』(PHP研究所)、『幸せを手にできる脳の最適解 ウェルビーイングを実現するレッスン』(KADOKAWA)がある。
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。
















