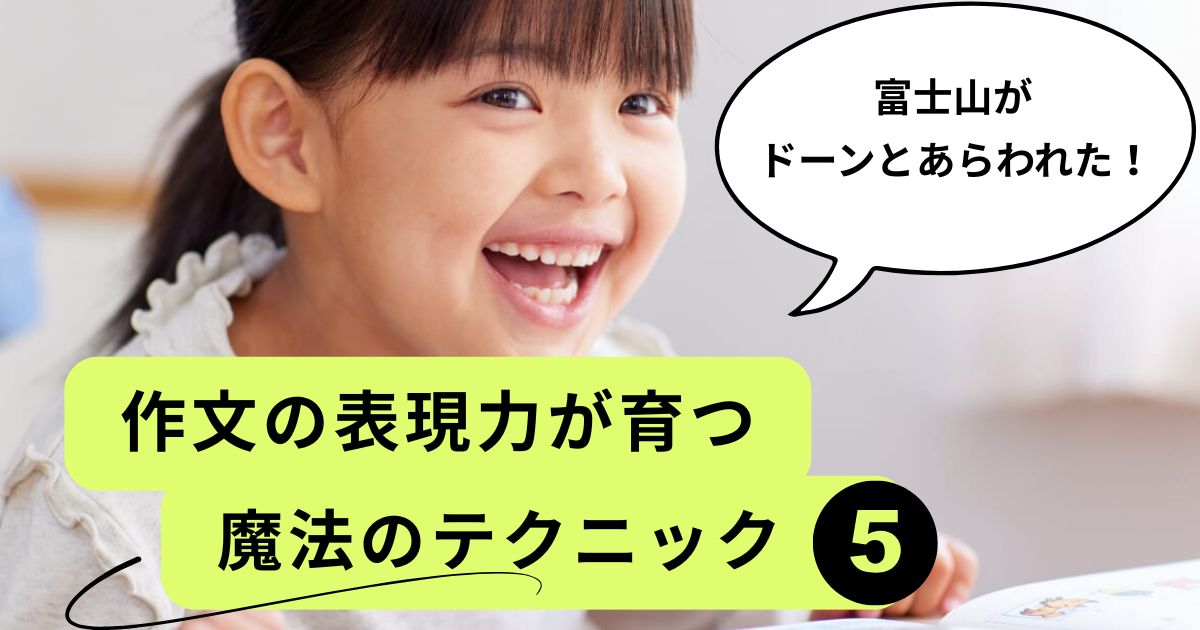読んでも場面が浮かばない、その子らしさが伝わってこない。そんなもどかしさを感じている保護者の方は少なくありません。でもじつは、表現力は日常のちょっとした工夫で驚くほど伸びるんです。
「富士山がドーンとあらわれた」「雲が山の上で踊っている」――そんな生き生きとした表現で、読む人の心をつかむ作文。その子らしさや個性が際立つ魅力的な作品は、特別な才能がなくても書けるようになります。
本記事では、専門家の見解をもとに「子どもの文章表現力を伸ばす5つの具体的なテクニック」を紹介します。今日から家庭で手軽に取り入れられるアドバイスが満載ですよ!
目次
文章表現力の伸ばす方法1:オノマトペを使う
文章に “躍動感” や “リアリティ” を加える方法のひとつがオノマトペです。伝える力【話す・書く】研究所所長山口拓朗氏によれば、オノマトペを上手に使うことで、読んだ人の頭にパッと場面が浮かぶ作文が書けるようになるのだといいます。
【オノマトペ活用のコツ】
コツ1:日常の中でオノマトペを探すゲームを親子で楽しむ
料理中に「この音、どんなふうに聞こえる?」と問いかけ、包丁で野菜をトントン切ったり、フライパンでザッザッと炒めたりと、子どもでもわかるようなオノマトペ探しを楽しみましょう。
コツ2:五感で感じたことを「音」で表現する習慣をつける
鳥の声や風の音、目に入る光など五感を刺激される出来事に敏感になりましょう。「どこかにチュンチュン鳴いている鳥がいるね」「池に映る光がキラキラしてきれいだね」というように、心が動く経験を共有すれば、親子の思い出作りにもなりますよ。
コツ3:子どもの言ったオノマトペをそのまま文章に書かせる
言葉にするだけではなくオノマトペを文章に書かせてみましょう。「雨がザーザー降ってきた」「弟がトコトコ歩いてきた」など、日常の些細な出来事でも一瞬で文学的な表現になります。
たとえば「富士山があらわれた」の代わりに「富士山がドーンとあらわれた」と書くだけで、動きや臨場感が伝わりますよね。ポイントは、子どもの自由な感覚を尊重すること。親が「こう書きなさい」と指示するのではなく、「どんな音が聞こえたかな?」などと問いかけて、子どもの豊かな発想を引き出しましょう。

文章表現力の伸ばす方法2:比喩を使う
作文の表現力を一段階高めるのが「比喩」です。比喩とは、物事を説明するときに別の何かに置き換えること。「ユニークな比喩表現はその子の個性を際立たせる」と山口氏にが述べるように、たとえば「雲が山の上で踊っている」と書くだけで、単なる天気の描写が生き生きと伝わってくるような気がしませんか?
【比喩表現活用のコツ】
コツ1:日常のものを「◯◯は△△のようだ」と例える練習をする
「カレーに入っているこのじゃがいも、猫ちゃんみたいな形だね」など、家のなかでも何かを別のものに例えるといいでしょう。親子の会話がもっと楽しくなりますよ。
コツ2:家族でゲーム感覚で比喩を出し合う
家族でしりとりのように「空は○○みたい」「風は○○みたい」とリレー形式で比喩を出し合うゲームを取り入れるのもおすすめです。語彙が増えれば思いつく比喩表現もアップしますよ。
コツ3:子どもの比喩を否定せず、ほめて作文に反映
大人の考えでは思いつかないような自由な発想も子どもならではです。「どうやったらそう見えるの!?」「ちょっと違うんじゃない?」など否定するのではなく、「よく思いついたね!」とほめて作文に反映させましょう。
日常生活のなかでも、「これは何に似ている?」と日々の観察を “別の何か” に置き換える訓練を繰り返すことで、独創的な表現が生まれます。子どもが思いついた比喩は、どんなに奇抜な表現でも肯定してあげましょう。そして、恥ずかしがらずに作文に取り入れることが大切です。
文章表現力の伸ばす方法3:五感言葉を使う
五感(見る・聞く・匂う・触る・味わう)を文章で意識的に表現することも、表現力を伸ばす大きなポイントです。つい「見た」「聞いた」が文章の主軸になりがちですが、匂いや手触り、味覚にも焦点を当てて表現することで、奥行きのある作文に仕上がります。
【五感表現を鍛えるコツ】
コツ1:五感で感じたことを意識させるために振り返りやメモをとる
家族のお出かけ後に「今日の海の色はどんなふうに見えた?」など、体験を五感に結びつけて振り返る習慣をつけるようにしましょう。簡単な日記に五感で感じたことを書かせるのもおすすめです。
コツ2:日常的に味を文章化する遊びを取り入れる
実際に料理や果物を味わいながら「甘い? すっぱい?」「口の中はどうなった?」と五感に関する質問をすることで、語彙がどんどん増えていきます。
コツ3:聴覚を研ぎ澄まして、音だけでどんな状況か想像してみよう
「玄関の外から足音が聞こえない? どんな感じかお母さんに教えてくれる?」など、耳からの情報だけを頼りに状況を説明してもらいましょう。聴覚を敏感にする癖をつけると、文章表現にも活かせます。
山口氏は、作文を書く前に子どもに「何が見えた?」「どんな音がした?」と質問するだけで、その子独自の描写が生まれることに言及しています。感覚に正解はないため、まずは自由に書かせて、後で語彙を補ってあげるやり方が効果的でしょう。

文章表現力の伸ばす方法4:「もしも~だったら?」を使う
「もしも~だったら?」と想像させることは、子どもの作文に個性と楽しさを加える魔法の言葉になります。山口氏によれば、架空の設定を通じて、子どもの価値観や願望が文章に表れやすくなるのだそう。さらに、想像のなかで他者や動物、物になりきる体験は、書く素材と視点を同時に育ててくれるでしょう。
【「もしも~」を使うコツ】
コツ1:日常的に「もしもゲーム」を取り入れ、発想の幅を広げる
寝る前に「もしも動物と話せたら?」「もしも空を飛べたら?」と一つ質問をして、短い会話を楽しみましょう。子どもの意外な発想力を発端として、話がどんどん膨らんでいくかも!?
コツ2:おもしろい発想はそのまま作文に取り入れる
せっかく思いついた個性的な「もしも」は、そのまま文章にして作文に取り入れてみましょう。自分のオリジナルの発想が立派な文章表現として活かされることで、想像力や発想力がますます研ぎ澄まされるようになりますよ。
コツ3:ネガティブな「もしも」も否定せずに受け止める
「もしも今、大きな地震がきたら……」「もしも試験に落ちちゃったら……」といったネガティブな意味合いで「もしも」を使ったとしても、親は慌てずに受け止めることが大事。不安を乗り越える方法を自分で見つけ出せば、前向きな作文へと昇華されるでしょう。
親は具体的な設定(例:「もしも〇〇くんが空を飛べたら?」)を出して、子どもの反応をほめて広げるだけでOK。想像のなかで五感まで掘り下げると、非日常の豊かな比喩や描写が生まれ、作文に個性が宿りますよ。
文章表現力の伸ばす方法5:言い換え&身体表現を使う
文章力養成コーチの松嶋有香氏は、「単純語の言い換え」と「身体表現を使った具体化」を意識することで表現力はぐっと広がることを指摘します。例えば、「うれしい」を「胸がじんわりした」「思わず笑顔がこぼれた」など身体感覚で表現することで、明らかに説得力が増していますよね。
【言い換えと身体表現を活用するコツ】
コツ1:よく使う語を別の言葉に言い換える練習をする
一日の出来事を話すときに「楽しかった」以外の言葉を探すように促しましょう。最初は「わくわくした」「ドキドキした」など、親が候補を出してあげるとスムーズです。
コツ2:「聞いた」→「耳を傾けた」など具体例を提示して一緒に考える
少し難しいと感じるかもしれませんが、本やテレビのニュースなどで使用される表現を参考にして、身体表現にもチャレンジを。「目を丸くした」「開いた口がふさがらない」など、子どもでもイメージしやすい表現から試してみましょう。
コツ3:親子で一緒に読書習慣を作って語彙インプットを増やす
読書後に「この言葉、ほかの言葉に言い換えると?」と一緒に考え、ノートに言い換えリストを作るのもいいですね。語彙が増えれば表現方法も幅もぐんと広がりますよ。
語彙が少ない場合は親が一緒に類語を出し、楽しく語彙を増やすことが肝心。一緒にテレビを見ているときに気になる表現を耳にしたら、「この感情はこうやって表現するんだね」と確認し合うなど、日常のなかでも表現の幅を広げるチャンスはたくさんありますよ、

よくある質問(FAQ)|親子で取り組む表現力トレーニングの疑問解消
Q1. オノマトペは正式な作文で使っていい?
A. 場面描写の一部として効果的です。ただし使いすぎは稚拙に見えることもあるので、場面の強調に使うかどうか親子で判断するといいでしょう。
Q2. 比喩が思いつかない子はどうすればいい?
A. 強制しないで「○○は何に似てる?」という問いで導く練習を。比喩は訓練で増えます。日常のものを常に「別の何か」に例える習慣が有効です。
Q3. 表現力トレーニングはいつやればいい?
A. 毎日10~15分の短時間を継続するのが効果的。五感メモやお題カードなど短いワークを家庭のルーティンに組み込みましょう。
***
子どもの表現力は、特別な才能ではなく、日々の問いかけや遊び、工夫で育ちます。オノマトペや比喩、五感質問、想像力トレーニング、語彙アップのワークを取り入れることで、作文はぐっと魅力的に。保護者は “問いかけ役” と “肯定の応援団” として、子どもが安心して自由に表現できる環境をつくってあげましょう。
(参考)
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|オノマトペで作文の表現力を伸ばすーー「富士山が”ジョジョッ”とあらわれた」でも間違いではない!?
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|オリジナルの比喩で、表現力のある作文に激変ーー”それ”は”ほかの何”に見えるのか?
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|「五感」を使って活き活きと作文を書くーー子どもの感覚から言葉を引き出す「五感質問」のテクニック
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|「もしも」で想像力&発想力に火をつける!ーー個性的な作文がスラスラ書ける魔法の言葉
STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|【親子でとりくむ読書感想文 書き方レッスン】第5回:質問と答えをセットにしてみよう