「ママ、なんでお月様はついてくるの?」「パパ、どうして雨が降るの?」子どもからの多くの質問に付き合うのは大変……と思ったことはありませんか。
でもじつは、この “なぜなぜ期”こそ、子どもの学びにとって大切な黄金の時間。研究によれば、子どもは2〜5歳の間に約4万回もの質問をするとも言われています。つまり、子どもの成長は「問い」から始まるのです。
その力を引き出す最高のツールが絵本。絵本を通じて親子でやりとりをする「シェアード・リーディング(共同読書)」は、子どもの好奇心や言葉の力を伸ばすことが数多くの研究で報告されています。
目次
なぜなぜ黄金期とは? 絵本で広げる好奇心
なぜなぜ黄金期とは?
ハーバード大学の教育学者ポール・ハリス氏によると、子どもは2〜5歳の間に、なんと約4万回もの質問を投げかけているそうです。これは、起きている間は30分に1回以上「なぜ?」を発している計算になります。
この時期の子どもにとって、目に映るすべてが「?」マーク。心理学では、この旺盛な好奇心を2つに分けて説明しています。
- 拡散的好奇心:いろいろなことに広く興味を持つ好奇心
- 特殊的好奇心:ひとつのことを深く知りたいと思う好奇心
絵本を読んでいるとき、子どもはまず絵本のページをめくるたびに新しい発見をします。「この動物はなに?」「この場所はどこ?」といった具合に、物語の中のあらゆる要素に興味を示します。そのなかで特に気になったことについて「なぜこの子は泣いているの?」「どうしてライオンは強いの?」と深く掘り下げていきます。
つまり「これはなに?」「どこにあるの?」と質問するのは拡散的好奇心の表れ。そこから「どうして?」「なぜそうなるの?」と掘り下げるのが特殊的好奇心です。この二つが活発に育つことで、子どもは頭のなかに「世界地図」を描き始めます。質問すること自体が学習のエンジンであり、探究心の土台になります。
ただし、この芽を伸ばすには大人の関わりが欠かせません。子どものちょっとした疑問に対し「いい質問だね」と応じ、一緒に考えることで、子どもの探究心、そして語彙力はさらに広がります。そのときに最適なのが絵本です。
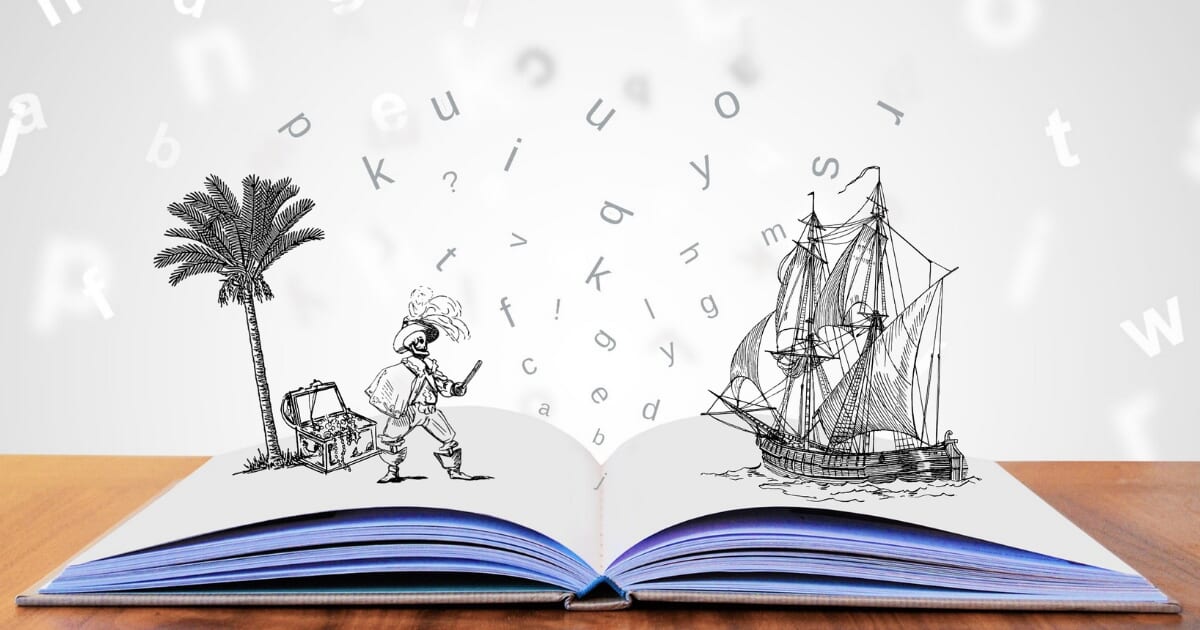
メリットだらけの絵本と“親子の会話” 3つの方法
子どもの「なぜ?」を育てるうえで効果的なのが、シェアード・リーディング(Shared Reading/共同読書)です。これは、親や保護者と子どもが一緒に本を読み、やりとりを交わしながら理解を深めるスタイルのことです。
通常の読み聞かせは、親が読む→子どもが聞く、という一方向になりがちです。一方、シェアード・リーディング(共同読書)では、子どもが「読み手」「語り手」として参加できるのが特徴です。ページを一緒に眺めながら、「これはなに?」「どう思う?」と問いかけや対話が自然に生まれます。
その中でも特に研究され、言語発達への効果が実証されているのが、ダイアロジック・リーディング(Dialogic Reading/対話的読み聞かせ)と呼ばれる方法です。質問と応答を繰り返すことで、子どもが能動的に物語に関わり、語彙力や考える力、感情理解が育つことが研究で示されています。
実際にどう進めればよいのかは、次章で紹介する「3つの方法」で具体的に見ていきましょう。

メリットだらけの絵本と“親子の会話”3つの方法
「ダイアロジック・リーディング(対話的読み聞かせ)」の具体的方法を紹介していきます。その中核になるのが PEER法 と呼ばれるシンプルな4ステップです。
1. 対話的読み聞かせの基本的ステップ「PEER法」
ハーバード大学で開発された「PEER法」は、対話的読み聞かせを誰でも実践できるよう体系化した手法です。4つの簡単なステップで構成されています。
- P(Prompt/促す):「この子は何してるかな?」と問いかける
- E(Evaluate/評価する):子どもの答えを受け止める
- E(Expand/広げる):新しい情報を加えて発展させる
- R(Repeat/繰り返す):キーワードを繰り返して定着させる
親:「どうしてだと思う?」(Prompt)
子ども:「お友達と離れてさみしいのかな」
親:「そうだね。“寂しい”って気持ちなんだね。〇〇ちゃんも寂しかったことある?」(Evaluate+Expand)
この方法で絵本を読むと、子どもは受け身で聞くだけでなく、能動的に物語に参加することができます。
2. 物語の世界から現実の学びへつなげる4つの質問
子どもとの対話を豊かにするためには、質問の仕方がとても大切です。「はい」「いいえ」で答えられる質問ではなく、子どもが自分の言葉で答えられる工夫した質問を心がけましょう。
- 感情を考える:「この子はどんな気持ちかな?」
- 予測する:「次に何が起きると思う?」
- 体験とつなげる:「似たことを経験したことある?」
- 想像を広げる:「自分が主人公だったらどうする?」
こうした質問は、お子さんの思考力、表現力、想像力を同時に育てることができます。正解・不正解を気にせず、親子で答えを楽しむ気持ちが大切です。
3. 絵本→探究の無限サイクル作り
その場で終わらせるのではなく、工夫次第で質の高い対話の時間をつくることができます。
📖読書タイムの質を最大化:
寝る前の15分だけでも、スマートフォンを置いて、子どもと向き合う時間をつくりましょう。この短い時間でも、子どもにとっては「自分だけの特別な時間」として記憶に残ります。
📖「絵本なぜなぜノート」作戦:
すぐに答えられない質問は、「なぜなぜノート」に書き留めておきます。「〇〇ちゃんの質問、とってもいいから忘れないように書いておこうね。週末に一緒に調べようね」と伝えれば、自分の質問が大切にされていることを感じられます。
📖図鑑と絵本をセットに:
リビングや子ども部屋に図鑑を置いておき、「答えは図鑑に聞いてみよう」という習慣をつくります。時には「〇〇ちゃん、図鑑で調べて教えてくれる?ママも知りたいな」とお子さんに調査を任せることで、自分で調べる力も育ちます。
📖日常が絵本の続き:
お料理しながら「卵はなぜ固まるの?」、お散歩しながら「影はどうしてできるの?」、お風呂で「石鹸はなぜ泡立つの?」など、じつは毎日の生活すべてが学びの場になります。
📖家族で読書探究タイム:
兄弟姉妹がいる場合は、上のお子さんの質問に下のお子さんも一緒に参加したり、逆に上のお子さんが下のお子さんの質問に答えてあげるなど、お互いに教え合う機会をつくることで、より深い学びにつながります。

「シェアード・リーディング(共同読書)」が家族の成長エンジンに
シェアード・リーディングは、子どもの探究心や語彙力を伸ばすだけではだけでなく、親自身にとっても大きな価値があります。日々の忙しさに追われる大人にこそ、この時間は新しい発見や学びのチャンスをもたらしてくれるのです。
① 知的好奇心の復活
「ママ、どうして空は青いの?」「パパ、なぜ恐竜はいなくなったの?」——子どもの質問は、私たち大人が当たり前として流してしまっていた事柄に改めて光を当てます。
答えるために図鑑やネットで調べるうちに、「へえ、そうだったんだ!」と自分もワクワクした気持ちを取り戻すことがあります。子どもの好奇心は、親の眠っていた好奇心を呼び覚まし、学び直しのきっかけになるのです。
② リバースメンタリング(子どもから学ぶ体験)
ビジネスの世界で「リバースメンタリング」とは、若手がベテランに新しい視点を与える関係性を指します。実は家庭でも同じことが起こります。
「どうしておうちは四角いの? まるい家でもいいんじゃない?」
「なんで勉強は座ってするの? 寝転んでやっちゃだめ?」
子どもの柔軟な発想は、大人の固定観念を揺さぶり、発想の幅を広げます。仕事でアイデアを求められる場面でも、この “子ども目線” がヒントになることがあります。
姉妹サイトSTUDY HACKERでは、読むを共有する「共読」による効果についてさらに掘り下げて解説しています。
読書は“ひとりで完結”させるな —— 共読があなたの思考と会話を変える
③ 家族の絆と学習習慣の形成
「なぜ星は光るの?」という質問から週末にプラネタリウムに行ったり、「どうして花は咲くの?」から家庭菜園を始めたり。子どもの疑問をきっかけに行動を共にすることで、親子の絆は自然に深まります。さらに、「わからないことは一緒に調べる」という習慣が家族のなかに根づいていきます。
その体験は「親に教えられた」ではなく「一緒に学んだ」という記憶として残り、子どもにとっても親にとっても特別な思い出となるのです。
***
シェアード・リーディングは、子どもだけでなく親にとっても「知的にワクワクする時間」「新しい視点をもらえる時間」「家族の宝物になる時間」。一緒に調べる、一緒に考える、一緒に不思議がる。こうした経験の積み重ねが、子どもの「学ぶ力」と「考える力」を育て、親子の絆を深めていきます。
読み聞かせを “義務” ととらえるのではなく、自分も一緒に楽しむ時間に変えてみることで、毎日の絵本タイムは家族の成長エンジンになっていきます。
(参考)
*1 COACH A E-Newsletter|Living with Questions
*2 A MORE BEAUTIFUL QUSTION|Why do kids ask so many questions—and why do they stop?
*3 Reading Rockets|Dialogic Reading: An Effective Way to Read to Preschoolers
*4 THE BRAGGING MOMMY|5 Unconventional Approaches to Nurturing Your Child’s Inner Strength




















