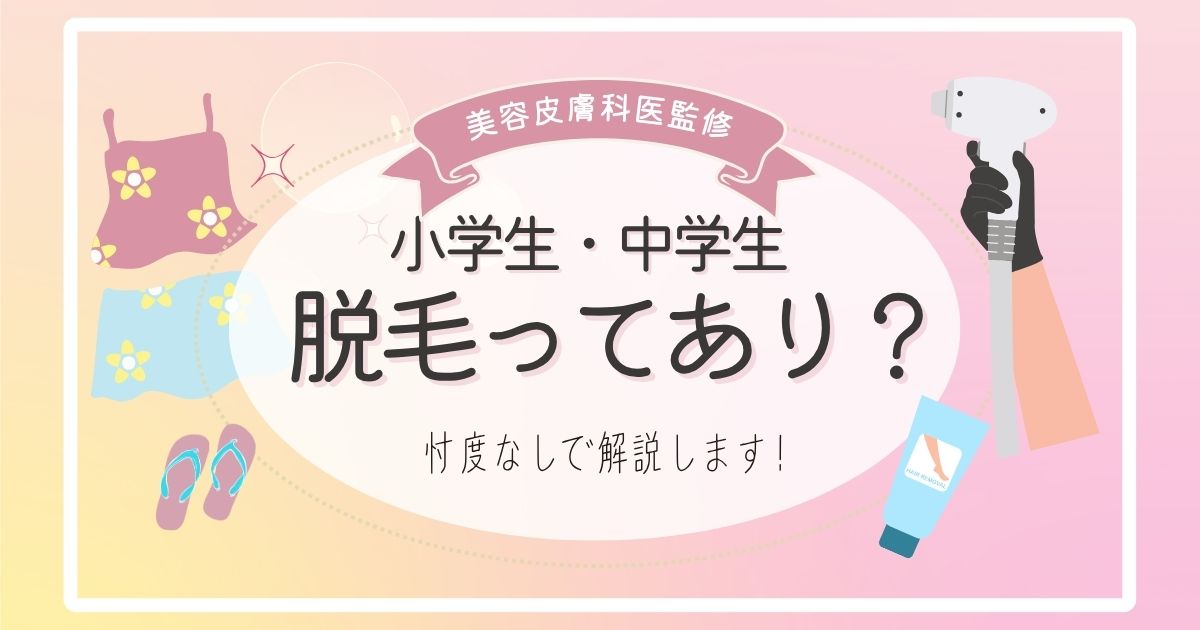「体育の着替えのときに、友だちに毛のことを言われて恥ずかしかった」「プールがいやで仕方ない」「なんで私だけ毛がこんなに濃いの?」お子さんから、そんな相談を受けたことはありませんか?
いまの子どもたちは、大人が思っているよりずっと早く、自分の見た目を意識するようになっています。SNSで美容情報に触れたり、友だちと比べたりするなかで、小学生のうちから「毛が濃い」「恥ずかしい」と悩む子が少なくありません。
「こどもまなびラボ」が2025年に行なったアンケートでは、小学2年生〜中学生の子どもをもつ親112人のうち、約40%が「子どもがムダ毛を気にしている」と回答。特に気になる部位は「腕・脚・指」が多く、決して一部の子だけの悩みではないことがわかります。
このような子どもの体毛への悩みが増えている現状を受けて、今回は美容皮膚科医の久野賀子先生の監修のもと、親としてどう向き合うべきか、適切な対処法について詳しく解説していきます。
ライタープロフィール
美容皮膚科医
2017年東京医科歯科大学医学部医学科 卒業。日大板橋病院にて初期研修終了後、湘南美容クリニックに入職し、5年半勤務。
新宿本院皮膚科医局長として通常の勤務だけでなく、新人医師の指導、VIP対応、トラブル対応に従事。2024年11月新宿二丁目にPRIDE CLINICオープン。
目次
まず知っておきたい子どもの体毛事情——なぜ小学生から体毛を気にするようになったのか
現代の子どもが体毛を気にするようになった背景には、主に3つの要因があります。
◆SNSによる美意識の早期化
スマートフォンやタブレットを通じて、大人と同じ美容情報に簡単にアクセスできるようになりました。インフルエンサーの脱毛体験や、加工された体毛のない画像を日常的に目にすることで、「毛がない状態が普通」という認識をもつ子どもが増えています。
◆学校生活での比較意識
体育の着替え、水泳の授業、修学旅行での入浴など、肌を露出する場面で他の子と比較して悩むケースが多発しています。思春期の敏感な時期だからこそ、周りからの何気ない一言が深刻な悩みとなってしまうのです。
◆親世代の脱毛経験
現在の親世代自身が脱毛を経験していることが多く、脱毛への抵抗感が少なくなったことも低年齢化の一因とされています。子どもが悩みやすい部位として、アンケート結果で最も多かった「腕・脚・指」は、日常的に目につきやすく、学校生活でも露出する機会が多い部位です。特に夏場の半袖・半ズボン着用時や、体育の授業での着替え時に気になる子どもが多いようです。
では、こうした悩みをもつ子どもに対して、親はどのように対応すべきなのでしょうか。「医療脱毛に通わせなければ」と考えるのは早計です。まずは子どもの気持ちに寄り添うことから始めましょう。

「気にしないで」はNG! 対処法はたくさんある
子どもから体毛の悩みを相談されたとき、多くの親が「そんなこと気にしなくていいよ」「まだ子どもなんだから」と軽く流してしまいがちですが、これは逆効果です。
まずは「教えてくれてありがとう」と相談してくれた勇気に感謝を伝え、気持ちに共感することから始めましょう。そして、どの場面で気になるのか、誰かに何か言われたのかなど、具体的な状況を最後まで聞いてあげることが大切です。
体毛があることは自然で、毛の濃さは人それぞれ違うということも優しく伝えてあげてください。ただし、子どもが本当に困っているなら、「そのままでいい」と存在を認めつつ、一緒に解決策を考えてあげましょう。近年では、体毛の悩みに対する対処法は、年齢や状況に応じてさまざまな選択肢があります。

【年齢別】対処方法はいろいろ。どう選ぶ?
体毛の悩みに対する解決策は複数あります。子どもの年齢や悩みの深刻さに応じて、最適な方法を選択しましょう。一般的な対処方法を以下にまとめました。
小学生の場合:
小学生の肌は大人より薄くて敏感で、手先の器用さもまだ発達途中です。そのため、刃物を使った処理は避け、より安全で刺激の少ない方法を選ぶことが重要です。
- 見守る・自然な変化を待つ
一時的な悩みの可能性が高い場合は、あえて何もせず見守る方法も有効です。成長とともに気にならなくなったり、同じような悩みをもつ友だちが増えることで自然に解決することもあります。 - 抑毛ローション
肌への刺激が少なく、毛を細く薄くしていく効果があります。即効性はありませんが、安全性が高いのが特徴です。 - 除毛クリーム
短時間でつるつるになりますが、肌への刺激が強いため、必ず保護者と一緒にパッチテストを行ない、使用方法を守ることが必須です。敏感肌の子どもには不向きな場合もあります。
中学生の場合:
中学生になると手先の器用さや判断力が向上し、より多様な選択肢が安全に使用できるようになります。また、この時期は第二次性徴により体毛が濃くなり、悩みも深刻化しやすいため、積極的な対処を検討する価値があります。
-
正しい自己処理を教える
電気シェーバーを使った安全な自己処理方法を教えることができます。お風呂上がりの肌が柔らかい時に処理し、必ず保湿ケアをセットで行なうことが重要です。度は週1〜2回程度に留め、やりすぎによる肌荒れを防ぎましょう。カミソリより電気シェーバーの方が切り傷のリスクが低くおすすめです。 -
家庭用脱毛器
親子で一緒に使用でき、費用も数万円程度に抑えられます。効果は業務用より穏やかですが、自宅で好きな時にできるメリットがあります。中学生の肌でも比較的安全に使用でき、親がサポートしながら正しい使用方法を身につけることができます。 -
医療脱毛の検討開始
一般的に12〜13歳頃から医療脱毛を受けられるクリニックが多くなります。ただし、第二次性徴の影響でホルモンバランスが不安定なため、脱毛後に毛が再生する可能性があります。本人が強いコンプレックスを感じている場合に限り、慎重な検討が必要です。
中学生以降で本格的な脱毛を検討する場合、近年特に注目されているのが家庭用脱毛器です。コロナ禍でサロンに通いにくくなったことや、親子で一緒に使えることから人気が高まっています。

子どもの医療脱毛ってどう?——医療脱毛を受ける場合のメリット・デメリット
ただし本人が強いコンプレックスを感じて日常生活に支障をきたしている場合や、体毛が原因でからかわれて学校生活を楽しめなくなっている場合は、心理的なケアも含めて早めの医療脱毛を検討する価値があります。その際は、信頼できる医療機関でリスクを十分理解した上で行なうことが重要です。
医療脱毛のメリット・デメリット
メリット
・効果が高く、少ない回数で済む
・医師による安全管理が受けられる
・肌トラブル時の対応が迅速
・長期的には自己処理が不要になる
デメリット
・費用が高額(十数万円〜数十万円)
・痛みが強い場合がある
・成長期は毛が再生する可能性がある
・日焼けや運動などの制約がある
子どもの医療脱毛で特に注意すべきポイント
第二次性徴前や最中の子どもは、ホルモンバランスが不安定なため、脱毛完了後も新たに毛が生えてくる可能性があります。生えやすいタイミングは「20代の成長に伴って」「妊娠出産」「更年期」。これは脱毛の失敗ではなく、成長に伴う自然な変化です。そのため、追加の施術が必要になる場合があることを理解しておきましょう。
また、子どもの肌は大人より薄くデリケートなため、同じ出力でも痛みを強く感じる傾向があります。多くのクリニックでは麻酔クリームの使用や、出力を調整するなどの配慮を行なっています。痛みに不安がある場合は、事前にテスト照射を受けることをお勧めします。
脱毛期間中は日焼けを避ける必要があり、施術後は激しい運動も控えなければなりません。子どもは大人以上に屋外活動が多いため、これらの制限を守ることが難しい場合があります。学校行事や部活動のスケジュールも考慮して施術計画を立てることが大切です。

どの選択肢を選ぶか? 3つの判断基準
子どもの体毛の悩みに対してどの対処法を選ぶかは、慎重に検討する必要があります。以下の3つの視点から総合的に判断することをお勧めします。
1. 子どもの気持ちを最優先に
一時的な悩みなのか、継続的で深刻な悩みなのかを見極めることが大切です。友達に何か言われて一時的に気になっているだけなのか、長期間にわたって悩み続けているのかによって対応は大きく変わります。
また、学校生活への影響も重要な判断材料です。体育の授業を休みがちになったり、プールを嫌がったり、友達との関係に影響が出ている場合は、より積極的な対処が必要かもしれません。一方で、親が心配しているだけで、子ども自身はそれほど深刻に考えていない場合もあります。
2. 家庭のサポート体制
医療脱毛を選択する場合は、数ヶ月にわたる定期的な通院が必要です。仕事を調整して付き添えるか、施術後は日焼けを避けたり激しい運動を控えたりといった約束事を子どもに守らせられるかがポイントです。家庭用脱毛器や自己処理を選ぶ場合は、安全な使用方法を教え、継続的に見守る時間が必要です。また、処理後の保湿ケアや肌トラブル時の対応など、健康面でのサポートも欠かせません。
経済面では、初期費用だけでなく継続的な費用も考慮が必要です。
3. 安全性の確保
信頼できる専門家に相談することから始めましょう。皮膚科医や小児科医、脱毛の専門医など、子どもの身体的特徴を理解した専門家の意見を聞くことが大切です。
また、選択した方法のリスクや副作用について十分に理解し、万が一のトラブルに備えた準備も必要です。家庭用脱毛器を使う場合は使用方法の徹底、医療脱毛を受ける場合は施術後のケア方法など、それぞれに応じた安全対策を講じましょう。
***
脱毛をする・しないに正解はありません。体毛があることは自然なことですが、それが原因で子どもが苦しんでいるなら、解決に向けて動くことも親の役割です。
ただし、無理に親の価値観を押しつけることだけは避けましょう。どの方法を選んでも、「ひとりで悩まないでいいんだよ」というメッセージを届けることが、何よりのサポートなのです。