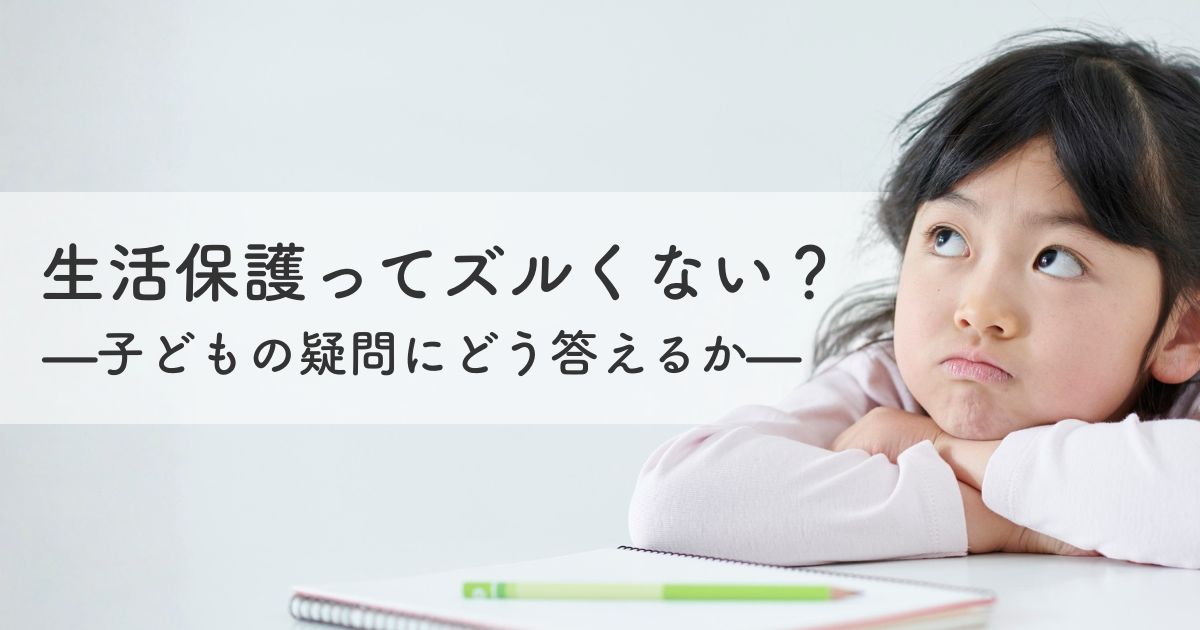「ねえママ、なんで生活保護でお金をもらってる人がいるの? ズルくない?」
公園で遊んでいた帰り道、小学3年生の娘が突然そう言いました。おそらく学校の授業か、テレビのニュースで生活保護のことを耳にしたのでしょう。
「そう見えるかもしれないけど、あれは『困ったときに支え合う仕組み』なんだよ」
私はそう答えましたが、娘の表情はまだ釈然としない様子でした。
子どもが「ずるい」と感じるのは、とても自然なことです。まだ社会の複雑な事情を知らない子どもたちにとって、「がんばっていない人がお金をもらっている」ように見えてしまうのは無理もありません。
でも、生活保護は「特別な人へのプレゼント」ではありません。誰もが困ったときに助けてもらえる、社会を支える大切な仕組みなのです。子どもの素朴な疑問をきっかけに、親子で「支え合う社会」について考えてみましょう。
目次
「平等」と「公平」はちがう
子どもは「みんな同じ=公平」だと思いがちです。運動会でみんなが同じスタートラインに立つように、「同じ条件で競争することがフェア」だと感じるのは当然のことです。しかし、社会における本当の公正さとは、「必要に応じて違う支援を行なうこと」を意味します。
たとえば、家庭のなかを思い浮かべてみてください。風邪をひいた子どもにはおかゆや食べやすいゼリーを用意して、元気な子どもには普通のごはんを出す。これは「不平等」でしょうか? それぞれの状態に合わせた対応をしているだけですよね。
背の低い子が高い棚のものを取るときに踏み台を用意するのも同じです。背の高い子には必要ないけれど、背の低い子には必要。条件が違う人には、違う支援が必要なのです。
哲学者ジョン・ロールズは格差の少ない社会こそが「自由で平等とみなされる市民の間で社会的協働を行う公正なシステム」であると伝えています。*1 つまり、公正な社会とは、社会的・経済的な格差を是正する仕組みがある社会なのです。

生活保護は「みんなの安心」を守る制度
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」──これは日本国憲法第25条で保障されている、すべての国民の権利です。*2 生活保護制度は、この権利を守るためにつくられた、最後のセーフティネットなのです。
生活保護を受けている世帯は全国で約164万世帯。受給している理由の多くは、病気、高齢など、本人の努力だけでは解決できない事情があります。*3
工場で働いていたお父さんが、機械に手を挟まれて大けがをした。治療に時間がかかり、働けなくなってしまった。
お母さんが難病になり、高額な医療費がかかるようになった。家族が介護に追われ、収入が途絶えた。
会社が突然倒産し、50代で失業。なかなか次の仕事が見つからず、貯金も底をついた。
これらは決して「怠けている」わけではありません。予期せぬ出来事によって、生活が立ち行かなくなってしまったのです。
「誰かが “ずるしてる” というより、“生きるのに困ってる人を守るための仕組み” なんだよ。たとえば、お友達が転んで足をくじいたら、保健室まで肩を貸してあげるでしょ? 生活保護も、それと同じなんだ」

「不正受給」は本当に多いの?
「でも、本当にズルしてる人もいるんでしょ?」
子どもからこう聞かれたら、事実をきちんと伝えることが大切です。
たしかに、不正受給はゼロではありません。しかし、その割合は私たちが思っているよりもずっと少なく、保護費全体の0.4%程度。*4
不正受給のニュースは目立ちやすく、記憶に残りやすいものです。でも、99.6%の「本当に困っている人たち」の存在を忘れてはいけません。少数の不正を理由に制度全体を否定してしまうと、本当に助けが必要な人たちまで苦しめることになります。
「クラスに1人ルールを守らない子がいたとして、”だからクラス全員を信じない” っておかしいよね? 大事なのは、ルールを守らない人にはちゃんと注意して、困ってる人はちゃんと助けることだよ」

「ズルい」と感じる気持ちの奥にあるもの
「自分より得をしている人がいるように見える」──子どもがこう感じるのは当然です。ここで親がすべきことは、その感情を頭ごなしに否定することではありません。「なぜそう感じたのか?」を一緒に考えることです。
じつは、この「ズルい」という感情には、人間の本能的な反応が関係しています。
行動経済学の研究では、「不公平回避(inequity aversion)」という現象が明らかになっています。これは、人間が「他者が自分より多く得ること」に対して強い嫌悪感を抱く傾向のことです。
代表的な実験に「最後通牒ゲーム」があります。一方が金額の配分を提案し、もう一方がそれを受け入れるか拒否するかを決めるゲームです。
2人でお金を分ける。A(提案者)が配分を提案、B(応答者)が受け入れるか拒否するか決める。
受け入れた場合:Aの提案どおりにお金を分配
拒否した場合:双方ゼロ
驚くべきことに、人々は不公平だと感じる提案(たとえば、10ドルのうち1ドルしかもらえない提案)を、約50%の確率で拒否します──たとえ拒否すれば自分も何ももらえなくなるとしても、です。
つまり、人間は「自分が損をしてでも、不公平を正したい」という強い衝動を持っているのです。これは子どもだけでなく、大人にも共通する心理です。
生活保護の受給者に対して「ズルい」と感じるのは、この本能的な反応なのかもしれません。でも、この反応は「明らかに不公平な状況」を察知するために進化してきたもの。大切なのは、生活保護が本当に「不公平」なのかを、冷静に考えることです。
「ズルいって思うのは、 “頑張る人が報われてほしい” って思ってるからだよね。その気持ちはとても大事だよ。
でもね、みんなの頑張ることができる条件は同じじゃないんだよ。たとえば、朝ごはんを食べられない子と、ちゃんと食べてきた子が、同じように勉強に集中できるかな? お腹が空いていたら、どんなに頑張ろうと思っても難しいよね。生活保護は、まずみんなが “頑張ることができる状態” になるための支援なんだよ」
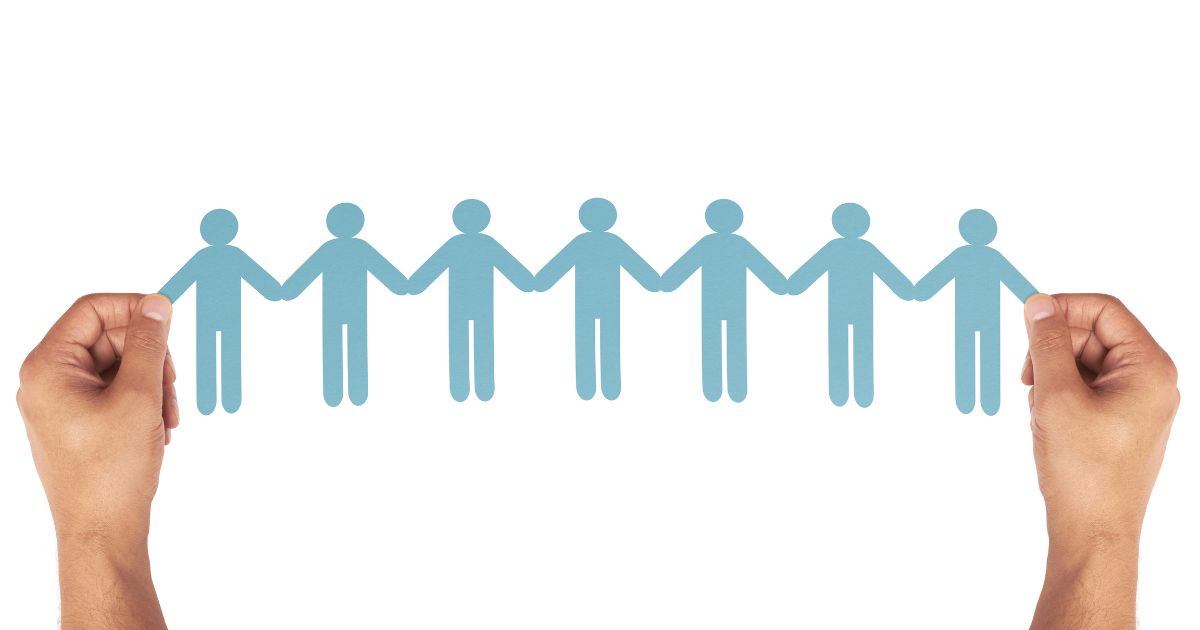
「ズルい」から始まる、やさしい社会への第一歩
「ズルい」という言葉の裏には、子どもの正義感やフェアでいたい気持ちが隠れています。この感情そのものは、決して悪いものではありません。むしろ、この感情をきっかけに、「助け合い」や「思いやり」の形について親子で話し合うチャンスなのです。
誰もが、事故・病気・災害・失業などで、突然支援を必要とする可能性があります。つまり「いま助ける側でも、明日は助けられる側になるかもしれない」。
大事なのは、”正しい答えを教える” ことではありません。”社会を支える気持ちを一緒に考える” ことです。
「もし自分が病気になって、長い間学校に行けなくなったら、どう感じるかな?」
「困っている人を助けると、自分にはどんないいことがあると思う?」
「”やさしい社会” って、どんな社会だと思う?」
答えはひとつではありません。子どもなりの言葉で、自分の考えを話してもらいましょう。そのプロセスこそが、子どもの心を育てていくのです。
***
「生活保護ってズルくない?」──この質問は、子どもが社会の仕組みに興味を持ち始めた証拠です。親として大切なのは、その疑問を否定せず、一緒に考えること。そして、こう伝えることです。
「生活保護は、ズルい人を助ける制度じゃない。誰もが安心して生きられるように、みんなで支え合う仕組みなんだよ」
子どもの「ズルい」という言葉の奥にある正義感を認めながら、少しずつ視野を広げていく。そうすることで、子どもは「自分だけが得をする」ではなく、「みんなが安心して暮らせる」社会の大切さに気づいていくはずです。
(参考)
*1 厚生労働省|第2章 社会保障と関連する理念や哲学
*2 厚生労働省|日本国憲法25条第1項
*3 厚生労働省|生活保護の被保護者調査(令和6年7月分概数)
*4 日本弁護士連合会|生活保護Q&Aパンフ
*5 ScienceDirect|Ultimatum Game