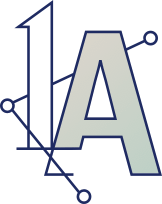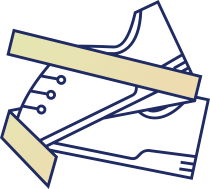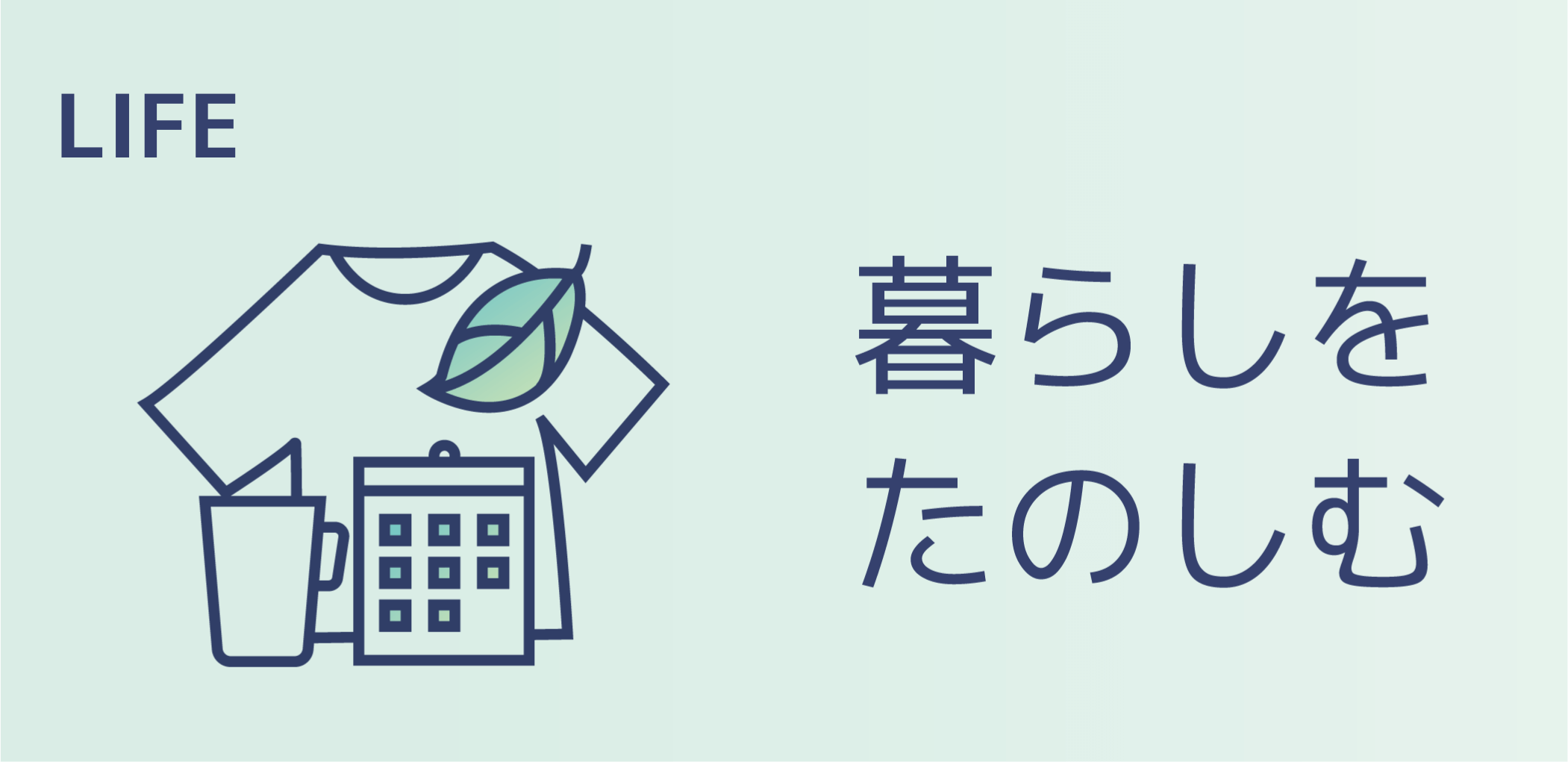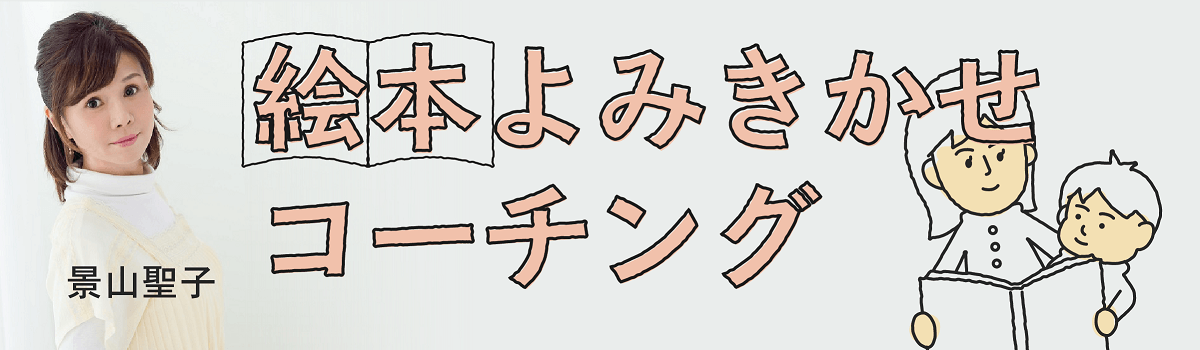北野武監督作品でも人気が高い映画、『座頭市』における下駄タップシーン。その圧巻のパフォーマンスは、映画公開時に世界中の映画ファンを驚かせました。そのタップダンスシーンの振付・指導を担当し、自らもタップダンサーとして出演していたのがHIDEBOHさんです。HIDEBOHさんがタップダンスをはじめたのは、6歳のころ。「プロ」という明確な道標がないダンスの世界……そんななかで、夢を実現していくために大事なポイントはどこにあったのでしょうか。HIDEBOHさんご自身の経験から、夢をつかむために必要なことについてアドバイスをもらいました。
構成/岩川悟 取材・文/洗川俊一 写真/玉井美世子
目次
なにをやりたいのかは自分自身で選択する
――HIDEBOHさんがタップダンスをはじたきっかけを教えてください。
HIDEBOHさん:
僕が6歳のころに、両親がタップダンスのスタジオをはじめたのがきっかけでした。興味があったからというわけではなく、「タップが身近にあったから自然に」という感じですよね。親に強制されたわけではありませんが、スタジオに行けば師匠である父(火口親幸氏)にタップダンスを教えてもらえるので、週に3回ほどスタジオへ行ってました。
――自然にはじめられたということですが、子ども時代にタップダンスをやめようと思ったことはありましたか?
HIDEBOHさん:
もちろんありましたよ。小学生のころに地元のリトルリーグで野球をやっていて、当時はプロ野球選手に憧れていましたからね。それで父には、「中学生になったらタップをやめる」と言っていました。すると父の反応は、「そうなんだ」のひとこと。「タップを続けろ」とも言わないし、やめる理由も聞かない。そう対応されると不思議なもので、子どもながらに「本当にタップをやめていいのかな?」と自分で考え出すものなんです。僕にとっては、この放任主義が合っていたようです。
――HIDEBOHさん自身で出した結論が、「タップを続ける」ということだったんですね。
HIDEBOHさん:
中学校に入ると、自分ができることでなにがいちばん得意なのか、どうしたらこれからの人生を歩んでいくことができるのか。そういったことをさらに考えるようになりました。体格的なものや適性から判断して出した結論が、「得意なのはタップダンスなんだ」ということ。この時点ですごくよかったと思うのは、自分で選択したということでした。
――プロのタップダンサーになるためには、明確な道筋というのはあるのですか?
HIDEBOHさん:
残念ながら、「こうすればなれる」というわかりやすい道はいまでもはっきりとはないと思います。ましてや、僕が子どものころはタップダンスそのものの認知度がかなり低かったですからね。日本でタップダンスが一般の人たちに広く知られるようになったのは、グレゴリー・ハインズ主演の『コットンクラブ』(1984年に公開されたアメリカ映画)が公開されたあたりくらいからではないでしょうか。

途中でやめたらいちばんの負け
――ダンスシーンにおける自分の居場所をつくることからのスタートとなると、かなり大変な道のりになることが想像されます。
HIDEBOHさん:
「自分でレールを敷かない限り道はない」と自覚したのは、中学を卒業するくらいですね。どうしたらタップを知ってもらえるのだろう、お茶の間に受け入れられるのだろう。そんなことばかり考えていたように思います。そこで、高校に入ったら仲間とバンドを組んで、間奏にタップを踏むというところからはじめてみました。『コットンクラブ』が公開されたのは、僕がちょうど高校を卒業するくらいのこと。たしかに、明確にプロのタップダンサーへという道はなかったのですが、逆に僕にとってはタップに自由に向き合えるという大きなメリットもありました。
――自由に向き合えたことによって得たものは?
HIDEBOHさん:
いちばん大きかったのは、「タップはこういうものだ」という既成概念にとらわれなかったことで、「Funk-a-Step」という過去になかったリズムのステップを独自につくれたことです。もちろん、できたばかりのころは名前もついてなかったですけどね。
――それは何歳くらいのときですか? その時点でプロのタップダンサーになれるという自信はあったのでしょうか?
HIDEBOHさん:
17、18歳くらいのときですかね。プロのタップダンサーにはもちろんなりたいと思っていましたが、職業にするとか、収入を得るという意識はそれほど高くありませんでした。それよりも、いろいろなジャンルの音楽でタップを踏むことへの興味や、リズムアーティストになりたいという思いのほうが強かったかな。だから、そのころから両親のスタジオでタップの指導をしていましたが、職業名を聞かれたら「フィーリング創造アーティスト」と答えていました。
――フィーリング創造アーティスト?
HIDEBOHさん:
自分の感覚を創造するアーティストということなのですが、なんだかわからないですよね(笑)。既成概念に反抗する若者特有の行動だったと思います。それが良いか悪いかはともかく、自分で考えて、自分で動くというやり方は、放任主義で育てられたことが大きく影響したと思っています。その点では、父と母には感謝ですね。
――HIDEBOHさんご自身のお子さんにも同じような教育方針をされているのでしょうか。
HIDEBOHさん:
タップやピアノを習っていますが、自分がそうされたように強制はしないようにしています。ただ、そうして見ていると、タップより算数のほうが好きみたいで(笑)。最近も、「タップはやめる」と言い出したのですが、レベルが上がるのがうれしくなったのか、すっかり忘れてタップを楽しんでいます。ただ、子どものころはそれでいいと思います。そして、いつか選択しなければいけないタイミングがきたら、自分で選べばいい。大人は「子どもは未来だ」と言いますが、子どもの未来まで決めるのはどうかなって。
――レールのないところを歩くのは、やはり不安だと思います。HIDEBOHさんが夢を持ち続けられた理由を教えてください。
HIDEBOHさん:
父がいつも言っていたのは、「あきらめずにしつこく続けていれば、だいたいのことは叶う」というものでした。その教えもあって、子どものころからしつこさだけは負けなかった(笑)。「あ、このステップはこんなものだろう」と思っても、それでも粘り強くもっと上達するために練習するという性格だったとは思います。もちろん、タップで結果を出していく過程で思うようにならないことも多々あったわけですが、とにかく粘ることだけはできた。『座頭市』のときに、たけしさん(北野武)とタップの練習をしていたときも父と同じようなことを言われましたよね。「ずっとやるんだよ、それを。やめたらいちばんの負けだからな」と。そのときはじめて、あきらめずにやってきて良かったと思ったし、これからもやり続けようと心に誓いました。
■ タップダンサー・HIDEBOHさん インタビュー一覧
第1回:【夢のつかみ方】(前編)~あきらめずにしつこくの精神~
第2回:【夢のつかみ方】(後編)~ニューヨークで学んだ「自分アピール」の重要性~
第3回:【父から教えてもらったこと】~客観的に子どもを見る視点を持つ~
第4回:【習い事としてのタップダンス】~リズム感、バランス感覚、器用な動作をつくる神経系を養う~
【プロフィール】
HIDEBOH(ひでぼう)
1967年10月7日生まれ、東京都出身。本名、火口秀幸。タップダンサーである父・火口親幸の元で6歳からタップダンスをはじめる。1984年からはタップの指導者としてインストラクターに。1987年からタップダンサーを目指して本格的な修行を開始し、ニューヨークと日本を行き来するようになる。ニューヨークでは、タップダンサーのスターであるグレゴリー・ハインズの師匠である、ブロードウェイの振付師ヘンリー・ルタンに師事。1998年には、オリジナルのタップパフォーマンス形態「Funk-a-Step」を提唱して「THE STRiPES」を結成。2003年、北野武監督の『座頭市』のタップダンスのシーンの振付・指導で一躍脚光を浴びる。2009年には「LiBLAZE」という新しいグループを結成。2015年、コレオグラファー(振付師)のダンスコンテスト『Legend Tokyo Chapter.5』にて、4部門において受賞。2017年には、タップダンスシーンの振付・指導、そして出演もした水谷豊監督作品『TAP THE LAST SHOW』が公開された。父がつくったダンススタジオを継承した、『Higuchi Dance Studio』では、子どもから大人までにタップを含めたダンス指導をしている。
【ライタープロフィール】
洗川俊一(あらいかわ・しゅんいち)
1963年生まれ。長崎県五島市出身。株式会社リクルート~株式会社パトス~株式会社ヴィスリー~有限会社ハグラー。2012年からフリーに。現在の仕事は、主に書籍の編集・ライティング。